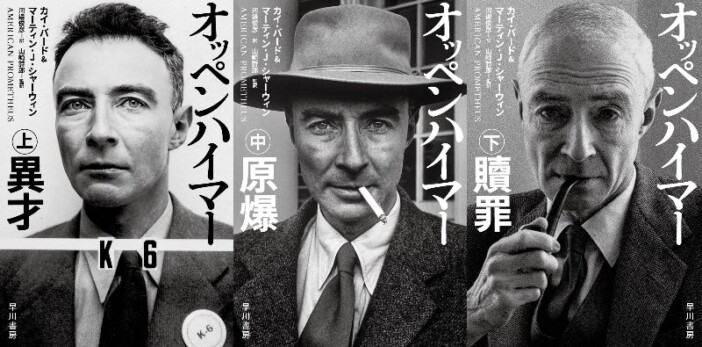ポール・トーマス・アンダーソンが「時代遅れのヒッピー」に託したものーー病んだアメリカと『インヒアレント・ヴァイス』

ポール・トーマス・アンダーソン(以下PTA)は、いつだって時代の狭間から抜け出せない人々を描いてきた。70年代に一世を風靡したポルノ俳優、石油ラッシュの興亡と共に精神が荒廃してゆく富豪、国と教祖(マスター)の支配に縛られた男……。彼らは時代の変化に取り残され、微かな光へと手を伸ばしもがき続ける。このスタイルはPTAが特定の時代に憧憬の目線を注ぐ作家ではないことを意味する。ティーンエイジャーの姿をスケッチした『リコリス・ピザ』(2021)で鮮やかに映された70年代のロサンゼルスだって、あの男にとっては生きづらい時代でしかなかった。そう、ゴルディータ・ビーチで探偵業を営む男、ドック・スポーテッロにとっては。
参考:ポストモダン文学はいかにして映画化されたのか? 『インヒアレント・ヴァイス』前編ーー「語り」と「騙り」に揺れる映像化
60年代に取り残された男と、70年代へと足を進めた女

『インヒアレント・ヴァイス』(2014)の主人公ドックは、70年代になってもヒッピーのライフスタイルを頑なに維持し続けている。起床して眠気覚ましにクサを一服、ランチと一緒にLSD。オヤツ代わりに笑気ガスで正気を保ち、日没には事務所の窓から水平線を眺めながらラインを引く。現実と妄想の境界はドロリと溶け、70年代のロサンゼルスと幻の大陸レムリアは一本の道で繫がる。ドックはそこを歩く。フラリフラリと千鳥足で。
だが世界はすでに変わっていた。マンソン・ファミリーが起こしたシャロン・テート/ラビアンカ夫妻殺人事件によって世間はカルト的コミューンに非難の目を向ける。これはヒッピー・ムーブメント衰退の大きな一因であり、チャールズ・マンソンが「60年代を殺した男」と称されアイコニックな存在となった所以だ。このようにヒッピーとマンソンは切っても切り離せない関係を結び、『インヒアレント・ヴァイス』でも(そして原作「LAヴァイス」ではより多く)その名が度々言及されている。つまるところ、マンソン事件を嚆矢として愛と平和を謳う60年代は終焉を迎え、アメリカは本格的に高度資本主義社会へと突入していったのだ。『インヒアレント・ヴァイス』はそんな時代の転換期、1970年を舞台とした物語である。
物語の冒頭、ドックのもとに元カノのシャスタが現れる。もとヒッピーだったシャスタの格好は今や、原作の言葉を引用するなら「フラットランドの堅物ルック」——すなわち、資本主義社会の下でマトモに働き、家族との小さな幸せこそが至上であると信じる「堅気の」世界のそれであった。彼女の今カレは、不動産デベロッパーとして社交界で幅を利かせる資産家ミッキー・ウルフマン。60年代に取り残された男ドックと、70年代へと足を進めた女シャスタの邂逅を起点として物語の歯車は回り始める。軸であるドックとシャスタの隣に立つのはヒッピー嫌いの刑事、通称ビッグフット。ビッグフットはその立場からも社会に迎合している人間として見られるかもしれないが、その実ドック以上に過去に囚われている。かつての相棒を喪った時からビッグフットの魂は60年代に取り残されており、必要以上にヒッピーを敵視するのもその表出であると解せる。ドック、シャスタ、ビッグフット。この三者が『インヒアレント・ヴァイス』の主要人物だ。
三者の関係性、すなわち60年代に囚われた男たちと70年代を生きる女……これは一見すると対立構造に思えるかもしれないが、シャスタという存在はドックにとって最良の思い出の顕現、つまり60年代のシンボルなのだ。この見地に立つと、シャスタとビッグフットは三位一体的なドックのアルターエゴとも捉えることができよう。前編に書いた通り、PTAは原作「LAヴァイス」のセリフを全て書き出したうえで物語を構築した。そのため、映画におけるストーリーラインは原作から大きく逸脱していない。しかし、様々な人物やカルチャーが縦横無尽に飛び回る原作に対して、『インヒアレント・ヴァイス』は徹底的にドックの影を追う。自分以外が全て70年代に歩みを進めてしまった寂寥感に満ちた影を。
映画『インヒアレント・ヴァイス』と小説「LAヴァイス」の差異

ここで映画『インヒアレント・ヴァイス』と小説「LAヴァイス」の差異について、大きなものをピックアップしてみよう。まずインターネットの存在だ。「LAヴァイス」のドックは捜査にインターネットを使用する。インターネットの誕生は冷戦下の1967年。核兵器にも影響されない通信方法として、国防総省による資金提供のもと軍事利用を目して開発が進められた。「LAヴァイス」では、インターネットの原初とされる「ARPAnet(アーパネット)」がドックに情報をもたらす。60年代のライフスタイルから抜け出せない『インヒアレント・ヴァイス』のドックと対照的に、原作のドックはこの「未来のウェーブ」を乗りこなすのだ。ヒッピー思想とインターネットの共通項は今や常識に近い勢いで語られており、具体的にはダグラス・ラシュコフが著した書籍「サイベリア:デジタル・アンダーグラウンドの現在形」でも纏められている通り。
ヒッピー思想とインターネットについて少し補足すると、ヒッピーがLSDでトリップする世界は「ハイパーテキストの宇宙」であり、これは端末からアクセスするインターネット空間と同一視できる……という考え方がある。「しばらくネットワークをやってたら、なんかサイケデリック・ドラッグをやるのに似た感じになってきたってよ」——これは「LAヴァイス」の一節だが、前述した見識を多分に意識したものとみて間違いない。インターネットが発達を見せた90年代より提唱され始めた思想を、1970年代を舞台に匂わせる。文字通りに「メタ(後出し)」なユーモアである。ピンチョン流ポストモダンな遊びと言えよう。
もう一つの違いはドック自身に関する描写だ。原作には父レオと母エルミナが登場する。ひとりぼっちな印象が強い映画のドックに比して、原作では家族や友人と和気あいあいと接している描写が多い。平たく言えば常に楽しそうなヤツなのだ。いつも瞳に物憂げさを湛えているホアキン・フェニックスを想像して原作に目を落とすと違和感を覚えるに違いない。
さらに言えば、原作と映画でドックの年齢は大きく異なっている。『インヒアレント・ヴァイス』当時のホアキン・フェニックスは40歳。対して原作のドックは30手前なのだ。いくらでもやり直しがききそうな30手前と、人生暗夜行路に直行気味な40歳とでは、ヒッピーのライフスタイルに拘泥する姿への印象は異なる。前者が「まあ、まだ若いしね……」と苦笑いできるものなら、後者には言葉を詰まらせる悲哀がタップリだ。そもそも60年代に30代だとしたらヒッピー集団の中でも年長者の部類だったわけで、それこそトー横キッズの中に混じっている「トー横おじさん」的なものか。ちなみにマンソンよりも5歳上となる。
これらの改変により、「LAヴァイス」の一要素であった「時代に取り残された寂寥感」が『インヒアレント・ヴァイス』では強く前面に打ち出された。それを代表するシーンが映画のミッドポイントとして用意されている。シャスタからの手紙を読むドックに被さるように、2人の過去の映像が流れる。大麻が手に入らない夏の日、ドックとシャスタはソルティレージュ(前編参照)の勧めでウィジャ盤に望みを託す。ウィジャ盤は欧米版こっくりさんとでも言うべき占いの道具だ。盤が示した数字が電話番号だと気づいた彼らはそこに連絡する。「クサがいっぱいあるわよ。でも早く来ないと無くなっちゃうわ」。なんてこった、やったぜ! ドックとシャスタは電話口の声が伝えた住所まで駆け出す。夕刻、空に夕陽の赤色と夜の青色が混ざり始めたとき、彼らに夕立が降り注ぐ。それでも走る脚は止まらない。無我夢中のふたりは訳も分からず笑い出す。もちろんクサを分けてくれる場所なんてあるはずない。ガンギマった彼らの幻聴だ。でもそんなもの、もうどうでもよかった。びしょ濡れのふたりはふと足を止め、互いを抱き寄せる。
映画のハイライトと言える素晴らしいシーンだ。別れた男女がかつて過ごした最高の瞬間が、ひたすら美しく、瑞々しく、ロマンティックに描かれる。誇張無しに映画史に残すべき場面と断言してよい。画面の左手からふたりが走ってきて、途中でドックは踵を返す。シャスタは画面右手に向かって歩き続けるが、引き返してきたドックに連れられて共に左手へと向かう。時代に逆行する男と、先に足を進めてゆく女。彼らの別離と映画の展開を示唆する演出も見事だ。PTAの持ち味がいかんなく発揮されており、この青春の残照と評すべき感覚は『リコリス・ピザ』で最大化され、主人公たちが走るシーンの反復へとつながってゆく。
ちなみにここで流れる曲がニール・ヤングの「過去への旅路」。映画のドックとニール・ヤングの関係性については前編で述べた通り。ドックの姿をニール・ヤングに重ねたことからも分かるように、この選曲ありきで本場面は設計されたと考えて良いだろう。また、言葉通りに映画のミッドポイント——中間点であり転換点であることからも、映画そのものがこの場面の情景を起点に設計されているとも言える。すなわち、ここが、この場面こそが映画において最も重要なのだ。どれだけ手を伸ばしても決して戻ってこない60年代に魂を取り残された男の姿を浮き彫りにする、夕立の疾走が。
ここにPTAが自分の作家性にピンチョンの原作を引き寄せたエゴを見ることもできよう。一方でPTAのピンチョン礼賛は有名だ。熱望した「ヴァインランド」の映画化企画は一度頓挫したと伝え聞くが、レオナルド・ディカプリオを主演に迎える期待の新作『The Battle of Baktan Cross』(2025年8月公開予定)は同書を下敷きにしたものと噂されている。そんなピンチョン狂であるPTAは、なぜ『インヒアレント・ヴァイス』において、己が作家性への引き寄せとも思えるアプローチをとったのだろうか。