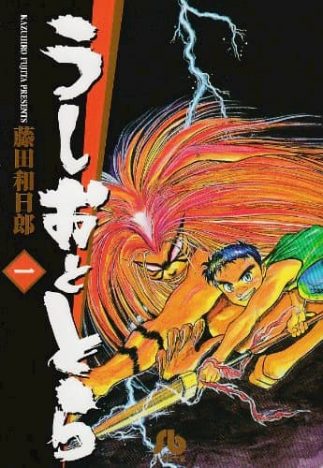藤田和日郎×劇団四季のミュージカル『ゴースト&レディ』劇評 虚構だからこそ語れる“真実”とは

去る5月6日、劇団四季の最新ミュージカル『ゴースト&レディ』が開幕した(演出:スコット・シュワルツ/脚本・歌詞:高橋知伽江/JR東日本四季劇場[秋]にて11月11日まで)。原作は、藤田和日郎の伝奇コミック『黒博物館 ゴーストアンドレディ』(講談社)。主人公は、「クリミアの天使」として知られる看護婦のフローレンス・ナイチンゲールと、元決闘士のゴースト、グレイだ(前者を谷原志音と真瀬はるかが、後者を萩原隆匡と金本泰潤が演じている)。

時は19世紀。ロンドンのドルーリー・レーン劇場に棲むゴースト、グレイのもとをひとりの令嬢が訪れる。令嬢の名は、フローレンス・ナイチンゲール(以下、フロー)。
16歳の時に天啓を受け、看護の道に一生を捧げる覚悟を決めたフローだったが、家族の反対に抗えず、生きる意味を見失い、死を望んでいた。しかし、クリスチャンである彼女は自殺することはできない。だから、シアターゴーストのグレイに自分を取り殺してほしいと願い出るのだった。
一方のグレイは最初は拒むものの、やがて自分も悲劇の“役者”になれるかもしれないと思うようになり、「フローが絶望の底に落ちた時に殺す」という条件でその願いを引き受けることにする。
こうして、世にも不思議な「ゴースト」と「レディ」のコンビが誕生したわけだが、グレイの異能(ちから)を借りて家族の了承を得ることができたフローは、自らの信念を貫くため看護団を結成、クリミア戦争下の野戦病院へと向かう。そこに彼女の使命を阻もうとする恐ろしい“敵”がいるとも知らずに……。
虚構と現実が入り混じる祝祭空間をゴーストが作り出す
なお、『ゴースト&レディ』というタイトルからもわかるように、本作でのグレイとフローはほぼ同格の主人公だと考えていいのだが、物語を主導的に動かしているのは、どちらかといえばフローの方である(グレイは、いわば“語り部”としての役割を担った主人公である)。当然、多くの観客はフローに感情移入することになるわけだが(そして、もちろんその観方で正しいわけだが)、グレイの存在にも注目されたい。
なぜなら、今回のミュージカルでは、グレイのその語り部としての立ち位置を最大限に活かした、舞台ならではのある“仕掛け(演出)”が施されており、開演早々、観る者を虚構と現実が入り混じる不思議な世界へと誘(いざな)ってくれるからだ。
そう、本来、ミュージカルに限らず演劇とは、この世とこの世ならぬものの境界――ある種の祝祭空間を現実世界に作り出す装置であり、とりわけこの『ゴースト&レディ』は、そうした演劇という表現ジャンルがもともと持っている魔法めいた側面が色濃く出ている作品だといえるだろう(そもそも現実の劇場の中に架空の劇場があるという、極めてメタな作品でもある)。

変幻自在なトリックスターが既成概念を破壊する
ところで、善と悪の両義性を持ち、虚構と現実の境界を曖昧にする神出鬼没な存在のことを「トリックスター」と呼ぶ。神話のヘルメスやスサノオ、あるいは、『夏の夜の夢』のパックや『西遊記』の孫悟空、コンメーディア・デラルテ(イタリアの即興喜劇)のアルレッキーノなどがよく知られているところだが、この世とあの世の狭間を漂い、時に日常性を破壊するゴーストのグレイもまた、その系譜に連なるキャラクターだといえるのではないだろうか。
いずれにせよ、グレイという変幻自在なトリックスターが条件つきでの「死」を確約してくれたからこそ、フローは逆に「生」を躍動させ、最後まで自らの信念を貫くことができた。そして、そんなフローが一途に頑張る姿を見て、かつて人間だった頃に心から求めていた“何か”を、グレイもようやく手に入れることができたのだ。
やがてふたりの間には、恋愛めいた感情が芽生えるのだが、その結末は、ぜひ劇場に足を運んで確かめていただきたい(原作の結末とは少々異なる展開が用意されている)。