丸山正樹 × 五十嵐大『デフ・ヴォイス』対談 ろう者やコーダの物語を描くことへの葛藤と意義
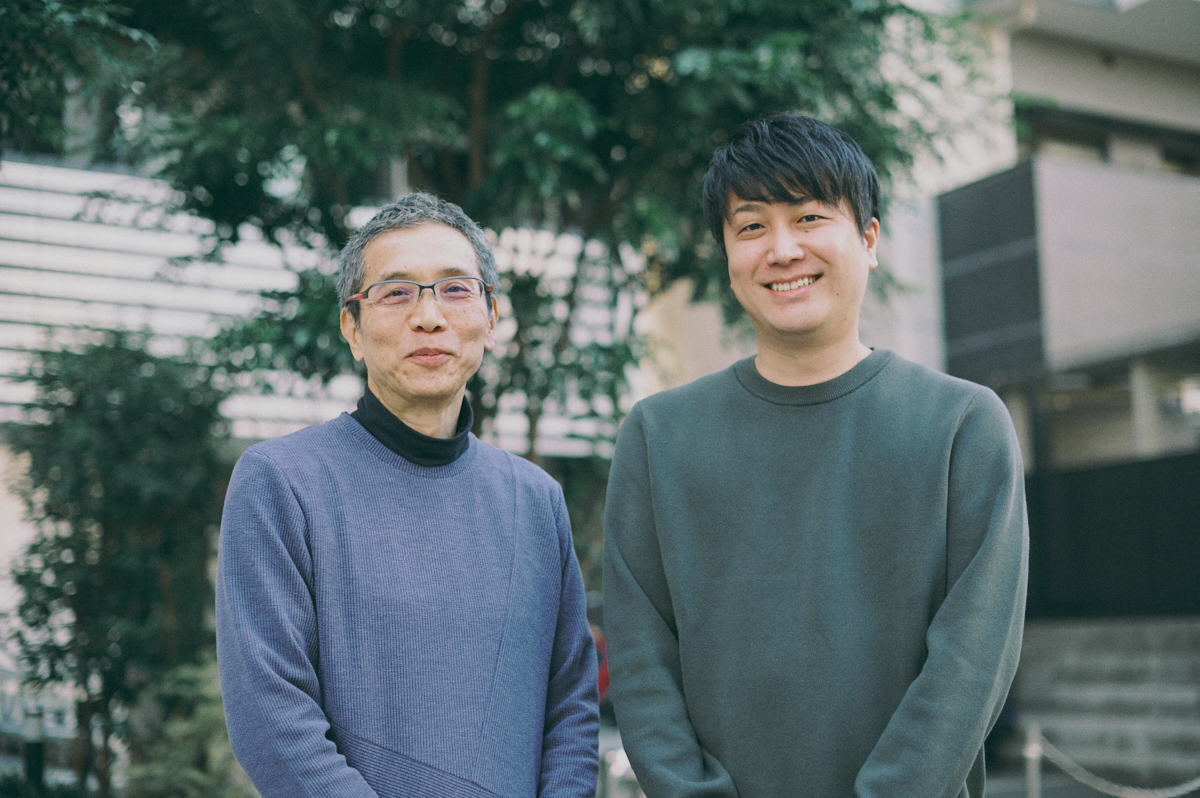
五十嵐「自分の偏見に気づかされた」

丸山:一作目とそれ以降ではかなり違いますね。というのも、二作目以降は、完全に当事者の方々から聞いた話をもとに書いているんです。特別に取材をしたわけじゃないんですよ。SNSなどを通じて知り合った方々と実際にお会いしたりして、日常的におしゃべりするなかで自然と耳(あるいは「目」)に入ってきたことをとりいれているんです。みなさん「書いてくれ」とは言わないけれど、「聞いてほしい」はたくさんある。そんな彼らの声を私以外の人たちにも届けなくてはならない、と思うようになりました。決して、代弁者を気取っているわけではないですし、そんなことができると思うのはおこがましい以外の何物でもありませんが、せめて私にできることをしたい、という気持ちですね。

五十嵐:四作目の『わたしのいないテーブルで』に「ディナーテーブル症候群」の話が出てきますよね。耳の聞こえる家族の中で自分だけが聞こえないと、会話にまざることができず、途方もない孤独を味わう。その状況を確かめるために荒井さんがリサーチするのですが、結果、多くのろう者の悔しさや悲しみの声が集まる。そのリサーチ結果は、実際に丸山さんが見聞きしたものなんですよね。
丸山:そうです。許可を得て、そのまま載せています。
五十嵐:それは丸山さんの「当事者の声を届けたい」という意思の表れだし、意義深いことだと思いました。これは現実なのだと知って改めて読むと、胸が締め付けられるなんて言葉じゃ足りないくらい、苦しくなります。
丸山:膨大な声からどれか一つを選ぶことはできなかったんです。小説としてその手法をとるのはどうなのか、ノンフィクションではないのだから、と迷いがなくはなかったんですけれど、あのエピソードに関しては全部載せずにはいられませんでした。
――逆にミステリー小説だからこそ描けることはありますか?
丸山:二作目の『龍の耳を君に』で書いた、聴覚口話法というろう学校の教育について知ったとき、私自身が驚いたんです。そんな現実があるのか、と。でもそれをそのまま謎として描くのではなく、自分たちの見えている景色がひっくり返ったときにいったい目の前に何が残っているのか、いかに自分たちが偏見によって世界を捉えているのか、気づかされるような反転を用意しなくてはいけないなと思っています。それは、誰より私自身のなかに偏見があると知っているから。
――荒井自身も、自分には偏見があると気づく場面がありますよね。
丸山:それはまさしく、私の想いです。私が代弁者ではないと思っているように、荒井も「自分はコーダの代表ではない」「ろう者のすべてを知っているわけじゃない」ことを自覚しています。実は、荒井のように手話が上手なコーダというのは少数派で、私の知識不足からそういう設定にしてしまったのですが、だからこそ「手話が操れるからといってすべてを理解できるわけじゃない」という彼の自戒につなげ、成長を描いていきたいなと思っています。
五十嵐:偏見が事件の真相を解き明かすカギになっていることは多いですよね。どれ、と言うとネタバレになってしまうので作品名は伏せますが、僕もまさに自分の偏見に気づかされたものがあります。障害があるからといって何もできないわけじゃない、そう知っているはずなのに、侮っていた自分に気づかされたというか。まさに景色が反転した瞬間でしたね。





















