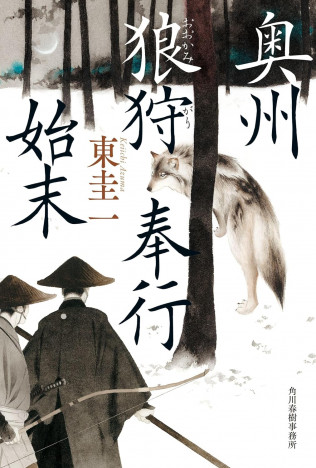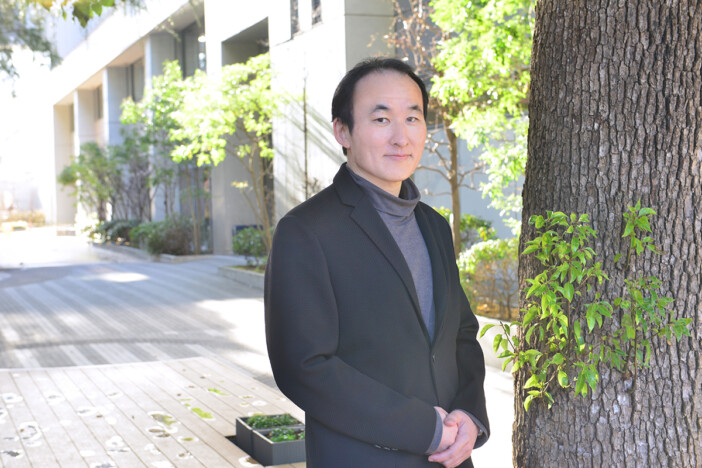杉江松恋の新鋭作家ハンティング 十代の心情をあらゆる角度から描き出す『まだ終わらないで、文化祭』

交替しながら語り手を務めていく登場人物たちにはそれぞれ、胸に秘めた思いがある。それらは言語化が難しく、口にしてしまえば嘘臭くなってしまうようなものだ。たとえば軽音楽部の一年生・艮(うしとら)カレンは、自分の周りを取り囲んでいる目に見えない負荷のようなものを、何かで一掃してしまえないかと思っている。彼女が欲しているのはロックンロールを演奏することだが、それは文化祭の目的には反していると教頭から止められてしまう。体制が奪おうとするものの中にこそロックンロールはあるだろう。
そこで彼女が禁を破って演奏をする、という展開になれば話は早いのだが、そうはならない。カレンがロックンロールを求めている理由は、そうした一時的な発散では追究しきれないものだからだ。学校の指示を受け入れてフォーク、サイモン&ガーファンクルの「America」を演奏しながら、カレンは内なる自分と対話をしていく。
自分の足止めをしている小さな障壁のようなものの存在に気づいても、それが何かがわかることは少ない。簡単に答えが出ないからこそ、そこで足を止めて考えなければいけないのだし、答えが出なくてもどかしい思いをするのだ。そうした姿を見せていく小説で、彼らに普段とは違う場所で考えを巡らせるための舞台装置として文化祭が用いられているわけである。個々のキャラクターが登場し、自分との対話をしていく道筋の随所にポスター掲示の謎に関する手がかりが振りまかれている。
それらを一つひとつ拾っていくと話が進んでいき、少しだけ時間が経って心境の変化したキャラクターたちと再会するという仕掛けである。グランドホテル形式のように、最後に全員を集めて大団円を迎えさせるのではなく、個々に集まって自由解散、みたいな緩い構成になっていることも効を奏している。文化祭は場であって、主題ではないのである。
うまいな、と思ったのはある登場人物の描き方だ。名前は出さないが、このキャラクターだけは印象が二転、三転するように書かれている。卵の殻に少しずつひびが入っていくような感覚とでも言うべきか。読み終わってみると、謎解きと同等かそれ以上の比重で、その人物の揺らぎが描かれていることがわかる。それって何、本当にそうなの、と読者が問いかける対象として置かれているキャラクターなのだ。そういう反響版みたいな人物を置いて、読者の声を物語内に広く響かせていく趣向がおもしろいではないか。
藤つかさのデビュー作は第42回小説推理新人賞を受賞した「その意図」である。「その意図は見えなくて」と改題の上、同題短篇集(双葉社)に収録された。それが最初の著書で、本作が二冊目、そして最初の長篇ということになる。第一作も青春小説として好印象の出来だったが、二作目でさらに技巧に磨きがかかったように思う。十代の心情を、その不完全さ、不安定さを損なわないでよく文章化している。心を描く小説の書き手として、この資質は得がたいものだ。壊れやすいものを描く、その手つきの優しさに感心する。