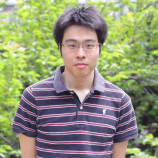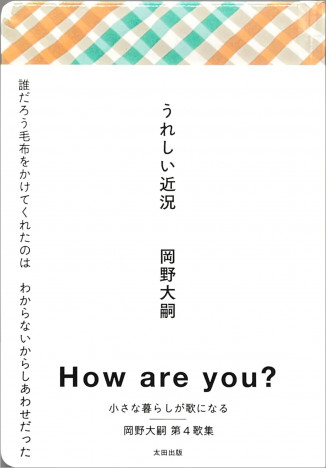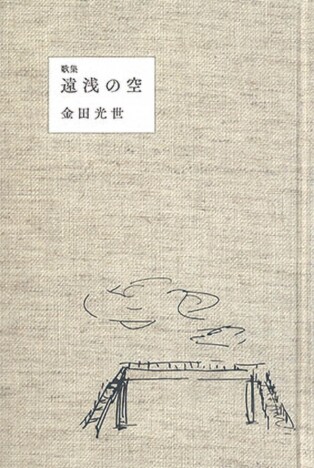女性歌人、36人の短歌を収録『うたわない女はいない』で詠まれる、リアルなライフバランスの難しさ
私はフリーライターだが、「フリー(ライ)ター」などと自虐的に名乗っていた時期がある。20代の頃は「書くこと」だけで生計を立てるのは難しく、単発の書き仕事のほか、派遣のバイトなどで細々と食いつないでいた。それゆえか、堂々と「ライター」を名乗ることに若干のうしろめたさがあり、自己紹介ではわざわざ、カッコつきの形容をすることが少なくなかった(こんな自虐が自分のためにならないことは今なら理解できるが、当時はそれもわかってはいなかった)。
というのは自分語りだが、ただそこまで自分に閉じたエピソードだとも思わない。「書くこと」と「生活の糧を得ること」を両立させる難しさは、多くのライターが直面しているものであろうし、じっさい、同業者の会合などで、そうした話題が出ることも珍しくはないからだ。むしろ、日常茶飯事と言っていいかもしれない。
そして、このような経験は「ライター」という肩書に限らなくとも、書くことを生業とする多くのひとが身に覚えのあるものだろう。歌人にしても例外ではない。「働くこと」を主眼とした、36人の女性歌人たちの歌を収録した『うたわない女はいない』(中央公論新社)においても、まず感じられるのは、それぞれの生活を背負った詠み手たちの苦闘である。彼女たちの多くは専業の歌人ではなく、ほかの仕事を持ちながら生活している。そして、仕事を含めたライフバランスを保つ難しさが、彼女たちの言葉の中に内包されている。
たとえば、花山周子さんの「大変だった仕事のお金月末に家賃で消える鼠のように」という金銭的なやりくりの難しさを詠んだ歌や、十和田有/ひらりささんの「キーボードに置いた手首にギロチンが落ちてきたなら自由だろうか」という(おそらくは)仕事の辛さからの解放を願うような歌。また、短歌に添えられる詠み手たちのエッセイに目を向けると、「昼間は会社で働き、かえって子供の世話をし、真夜中から雑誌などに寄せる短歌や短歌に関する文章を書く」という三重生活の難しさを語る山崎聡子さんの言葉や、「安定はしていないし、ボーナスもないし、体を壊せば収入がゼロになる」と将来への不安を吐露する千原こはぎさんの言葉からも、その一端は読み取れるだろう。
また本書では、「うたわない女はいない」と「女」を前に出していることにも着目する必要がある。それはなにも、女性という性別そのものに特異な感受性を見出そうとする偏狭なジェンダー観の表れなどではない。大きくは、ジェンダーギャップ指数が世界146か国中125位(2023年6月時点)という国に生きる、女性たちの労働環境、ひいては女性たちが日常的に受ける、差別へのまなざしである。
たとえば、浅田瑠衣さんの「業界の未来を語るおじいさんおじさんおじさんおじいさんおじ」という歌。または、橋爪志保さんの「冷えきった中指で売るひとまわり小さな「女性用」の実印」という歌。これらの歌から、業界の最先端から女性が取り残されている、男性優位の構図を見出すことはさほど難しくないだろう。または、北山あさひさんの「ロボットもニュースも男がつくるものビルは勃ちわたしは製水器」という歌や、および彼女の、職場であるテレビ局に“図書館”を作った顛末を書いた「本があるのに」というエッセイに触れ、本来なら社会の変化を牽引するメディア業界においてさえも、根深い差別感情が残っているのだと実感することもできる。
「働く楽しさ」に目を向け
とはいえ、「生活の糧を得ること」は辛さもありながらも、その中に楽しみもあるし、または辛さのなかから創作の種を見出すこともできる。本書は、序盤においては「女が働く現場から」「だいじょうぶじゃないとき」という章タイトルからも読み取れるように、“働く”ことの厳しさを詠んだ歌が印象的だったが、後半では章タイトルに「働くうれしさ」「未来に驚いて」と変化が見られるように、よりポジティブに“働く”をとらえるような歌が目立つようになる。
「うすあおい付箋は落ちるしらじらと花びらが花を離れるように」と、仕事中の何気ない一コマを自然のなかの美しさに重ね合わせる道券はなさん。「パソコンを抱えて帰るバッテリーの熱もいつしか温もりになる」と、本来ならば不具合や故障にもつながるパソコンのヒートアップを、人と人の間に生まれる情愛のようなかたちでとらえる奥村知世さん。「誰の出張が最も過酷だつたかをきらきら比べあふ月曜日」と、出張の過酷さを〈きらきら〉という言葉で昇華させる石川美南さん。こうした歌からは、目の前の苦難やちょっとした変化を、目線を変えて楽しもうとするユーモアの大切さが伝わってくる。
また詠み手たちは、自身のさまざまなアイデンティティのなかで「歌人」を最上位に置き、それ以外の自分をかりそめの姿ととらえているわけではない。
「その「ぬ」が打消ならば皇子は生まれずに始まらざりけむ物語あり」と、『源氏物語』への想いを古典の教師ならではの着眼点で切り取る田口綾子さん。「終刊ののちも車輛に残りたる銀の空箱〈MAGAZINE BOX〉」と、鉄道車内誌を作成する仕事への、ほのかな誇りを歌の中に込める鯨井可菜子さん。「誤字憎し時にはたのし淡々麺、幸子明太子、オレンチジュース」と、校閲の仕事の中で生まれた誤字の面白さに着目する飯田有子さん。これらの歌にあるのは、その仕事に打ち込んできたからこそ生まれる感情や表現の豊かさである。
読者たちは最初のページから流れに沿って読むうちに、「働くこと」には辛いことがいろいろと含まれながらも、同時に自分と切り離せない、血肉のような存在になってもいるのだともより暖かく感じられるようになるだろう。もちろん、本書をどこから読むかは読者の自由だが、私としては最初から順番に、それぞれの詠み手の作品を読んでいくことをおすすめしたい。
「プリキュア」に内包されるもの
本書の終盤では、「短歌が変える私たちの現実」というタイトルのもと、「おしごと小町短歌大賞」の選考委員を務めた俵万智さん、シンガー・ソングライターの吉澤嘉代子さんによる受賞作の紹介と選評、および対談が収録されている。その仔細についてはじっさいに本書をご覧いただきたいが、大賞を受賞したのは「子の熱で休んだ人を助け合うときだけ我らきっとプリキュア」という、遠藤翠さんの歌である。
おもに女子中学生が変身し、悪との戦いを繰り広げる「プリキュア」たちは多くの少女たちの(いや、少女に限らないか)あこがれの的となったヒーローだが、ただ同時に、ヒーローとしての顔だけが、プリキュアたちのすべてではない。自分に甘い態度をとってしまったり、人の気持ちをうまく読み取れなかったり、逆に自分の気持ちをうまく口にできなかったり……日常におけるプリキュアは、そんな平凡な悩みを抱えた、どこにでもいる女の子たちだ。けっして特別ではない女の子たちが、それぞれの勇気を振り絞って戦う姿が多くの視聴者の感動を呼んだことと同様に、この歌では、それぞれに違う女性たちが何気ない思いやりを発揮させて団結する、平凡な、しかし確かな「プリキュア」的きらめきがぐっと読者の心をつかむ。
そして、同時にこの歌は、『うたわない女はいない』という歌集の魅力を、まさに凝縮するような歌ではないかとも感じた。歌人である以前に、推しのアイドルに熱量を注いだり、修験道を踏破した経験があったり、有名な俳優と同じ生年月日であったり……。さまざまなバックグラウンドを持つ詠み手たちが、自身の生きてきた過程やその中で得た、自分を構成する、しかし自分の中でも統合されていなかったいろいろな要素を、労働短歌というかたちでまさに「プリキュア」的に昇華させるのだから。
最後に。「うたわない女はいない」というタイトルは、当初は「うたう」に、自分の置かれた厳しさを吐露するという意味合いをかけたものかなと思っていたが、たぶんそれだけではない。本当になにげない、ちょっとした日常や経験がこうして短歌になるのだから、歌を詠むことはけっして特別ではないんだよ、と読者の背中を押す意味合いもあるのではないだろうか。
あらためて、「うたわない女はいない」と口にする。当初は否定形のタイトルに少し距離を覚えていたものの、本を何周かしたいまでは、むしろ男性である私も、「さあ、いっしょにうたおう!」と勇気づけられる気持ちになっている。