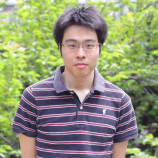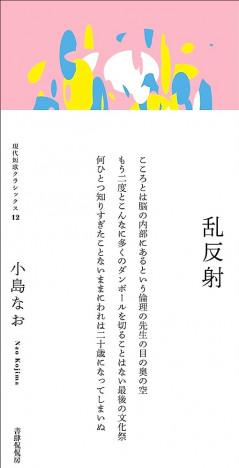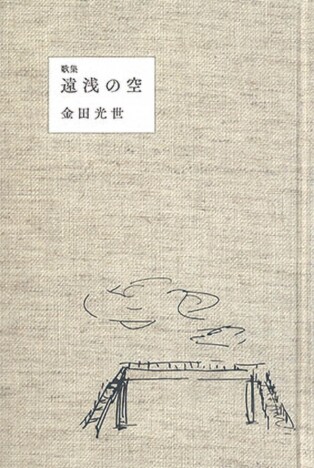菅原百合絵の初歌集『たましひの薄衣』瑞々しい言葉から浮かぶ人生の「へだたり」と誠実な「まなざし」

『たましひの薄衣』(書肆侃侃房)は、18世紀フランス文学を専門とする文学研究者であり、「東京大学本郷短歌会」「パリ短歌クラブ」などで短歌を発表してきた歌人・菅原百合絵さんのはじめての歌集である。東京で過ごした学部時代から、ジュネーヴやリヨンで過ごし、パリ・シテ大学の博士課程を修了する留学期にいたるまで、10年ほどのあいだに編まれた歌のなかから333の歌がおさめられている。
〈彼岸〉と〈此岸〉のイメージ
私は菅原さんとは、学生時代の友人であった。私自身は歌作とは縁の遠い生活を送っていたものの、ときおり共通の知人の評判などをとおして、彼女の歌に触れる機会はあった。そのなかでとくに私に強い波紋を残しているのは、「光を漁る」という連作のなかに登場する、以下の歌である。
〈彼岸が此岸になるまで舟を漕ぎゆく旅を一生と呼べり〉
はじめてこの歌に触れたとき、映画学を専攻していた私はテオ・アンゲロプロスの『霧の中の風景』『こうのとり、たちずさんで』、アンドレイ・ズビャギンツェフの『父、帰る』などの作品を思い浮かべた。
彼岸(かのきし)から此岸(このきし)にいたるまでは一生(ひとよ)に相当する時間を費やさなければならないのだから、ふたつの岸には埋めようのない大きなへだたりがあるのだろう(※)。幼い姉と弟が舟を漕いださきにたどりつく、霧に覆われた〈此岸〉――おそらくは現世と離れた場所で、希望の象徴とも思える一本の木に出逢う『霧の中の風景』や、川=国境によって新郎と新婦がへだてられた結婚式が銃声によって中断させられ、アルバニアとギリシャという、ふたつの〈岸〉をわかつ裂け目が浮かび上がる『こうのとり、たちずさんで』、小舟を介した親子の無人島への旅が、いつしか兄弟が父を喪う儀式へと変転する『父、帰る』――。いずれの作品でも、〈彼岸〉と〈此岸〉のあいだには、たんなる物理的な意味にとどまらない「へだたり」が横たわっている。
そうした「へだたり」は人々に深い悲しみをもたらすこともあれば、断絶を乗り越えようという、生きる力の源泉にもまたなりえるだろう。どこか物悲しげに、しかし確かな手つきで櫂を操る漕ぎ手のイメージが――いわば「へだたり」がもたらす影と光の両面が――、ちょうど当時の私を魅了したさまざまな映画作品のように、自身のもとに去来したように思えたのだが、全編をとおして「へだたり」、および「へだたり」をもたらす、またはそれ自体が「へだたり」の象徴となるような「水」の豊かなイメージが横溢する『たましひの薄衣』は、そのときの思いを私によみがえらせてくれた。
『たましひの薄衣』でまず目を引くのは、古語を軸とした過去へのまなざしの豊かさである。『旅芸人の記録』をはじめ、ギリシャ神話や叙事詩を作品の重要なモチーフとしてきたアンゲロプロスと同様に、菅原さんにもまた、古典文学・芸術や歴史への造詣の深さが感じられる。
〈ネロ帝の若き晩年を思ふとき孤独とは火の燃えつくす芯〉
〈丈高きチュイルリーの樹に添ひあゆむ若きリルケの孤独の象〉
といった歌から端的にそれは了解できるし、そのいっぽうで、教養として位置づけられる作品や、歴史的事象のマニアックな細部と戯れることが作品の主眼というわけではない。おそらく菅原さんの軸にあるのは、いにしえに生きた人々の――自身とは「へだたり」のある人々の想念をどのように受け継ぎ、自身の血肉としていくかという問いである。そして、そうした問いの核として機能するものが、歌集においてさまざまなかたちで変奏される「水」のモチーフである。
〈ほぐれつつ咲く水中花ゆつくりと死をひらきゆく水の手の見ゆ〉
〈魂は水の浅きをなづさへりうつし身ゆゑにゆけざるところ〉
さまざまなかたちで変奏される水のモチーフ
そもそも、「水」とはなにか。「水素と酸素の化合物で」といった物質的な説明を求めているのではない。人間にとってはどのようなものか。体の構成要素のおよそ7割を占める、生存のためにはなくてはならない卑近な存在であると同時に、さまざまな信仰の対象ともなってきた、人智のおよばない、私たちの命をも奪いうる「他者」ではないか。菅原さんはそうした水の他者性を、作品のなかで注意深く読み解いている。
〈箱舟に乗せられざりし生きものの記憶を雨の夜は運び来〉
〈目覚むれば昼の岸辺にたどりつくオフィリアよりも遠くながれて〉
残酷な神としての水は、かつてはノアの箱舟に乗る機会を逸した多くの動物たちの生を押し流し、ハムレットの最愛の人オフィリアを死の底へと引きずりおろした。これらの歌は神話や戯曲に想を得ており、日常とは少し距離を感じさせる。しかし、菅原さんの手にかかると、何気ない日常においても、水は「他者」としての顔を顕在化させる。
〈顔洗ふときにもみづは重たきにいかなる岸を彼岸とはいふ〉
〈音立てずスープのむときわがうちのみづうみふかくしづみゆくこゑ〉
上記の歌に感じられるのは、自身の体にじかに触れ、ときには自身のうちに沈んでゆきながらも、どこか自分とは「へだたり」をもった水のすがたである。
その他者性は、水に悠久、あるいは永遠といった意味合いが付与されることにもまた起因する。たとえば、下記の歌のなかにそれは読み取れるだろう。
〈残光にレマン湖のみづ燿へり異端者セルヴェを燃やしたる都市〉
〈打ち寄せて無限に返りくる水を狂人ニーチェも深く愛しき〉
神学者ミシェル・セルヴェが火刑に処された16世紀とも、哲学者フリードリヒ・ニーチェが理性を失った晩年の19世紀とも、川や湖、あるいは海の流れは変わることはない。それらはただ、静かに地球を循環し、地表を満たすだけなのだ。
水が浮かび上がらせる幸福
古来より水が地表を流れ、普遍的な運動を繰り返してきたことと比較すれば、いまに暮らす個々人の生などはあまりにちっぽけなものだろう。しかし、菅原さんは人間を突き放すような水の姿を描くいっぽうで、いわば慈父としての水のすがたもまた見逃さず、そこから自身の生の幸福もまた浮かび上がらせる。
〈寡黙なるひとと歩めば川音はかすかなり日傘透かして届く〉
〈いつしんに心を寄せて憶ふ人ありしこと春のさざめく川に〉
ここでいう「寡黙なるひと」「心を寄せて憶ふ人」とは、おそらくは菅原さんの〈エマニュエル・カントのやうなる〉と語られる恋人であり、のちに〈わたしの夫〉として歌に詠まれるひとを指すのだとは、やがて歌集を読み進めるなかで知ることができる。恋人から夫婦となったふたりの日常のなかにも、水はちょうど生を寿ぐようなかたちで、節々に姿をあらわす。
〈今しがたわれに触れゐしひとの手が川の光を指してきらめく〉
水に対して、人はさまざまな心情を仮託することができる。若き日の友人との想い出であったり、今はなき大切な人への追憶であったりするその心情は、しかし往々にして、過多な感傷にもまた陥りやすい。菅原さんは言葉をとおして豊かな情感を編むと同時に、〈キリストを石もて追ひし人々の微笑み〉〈コンコルド広場にギロチンありし日〉といった鋭利な言葉を周到に差し挟むことで、安易なセンチメンタリズムからその情感を開放してもいる。
〈「輪郭のないものばかりうつくしい」 水辺に春のひかりながれて〉
本書の序盤に登場するこの歌は、私がもっとも心を惹かれた歌である。もともと輪郭を持って生まれた人間は、ほんとうの美に触れつつも、それに到達することはできないのかもしれない。水は「輪郭のないうつくしさ」を持つがゆえに、菅原さんの重要なモチーフとなり、同時に自身が到達することのない「他者」のイメージになりえたのではないか。そして「他者」に向けたものであるからこそ、言葉はまた豊かなものとなりうる。
〈目が合ひて逸らせばやがて舟と舟ゆきかふやうにさざなみ来たる〉
誰かとの間に生まれる「さざなみ」に目を向け、言葉によってとらえること。いわば水というフレームを通して、誰かの思いに届こうとすること。『たましひの薄衣』という歌集の美しさは、そうした他者へのまなざしの誠実さにささえられている。
(※)ここでいう「彼岸」「此岸」には、仏教用語における意味合い(彼岸=ひがん、生死の海を渡って到達する悟りの世界のこと、此岸=しがん、迷いや煩悩のある現世のこと)もまた含まれているだろう。