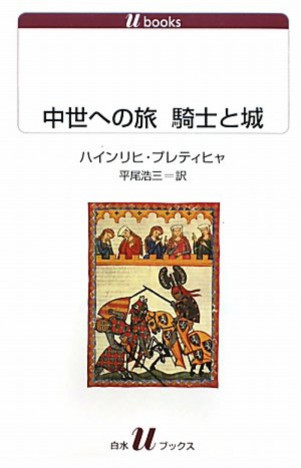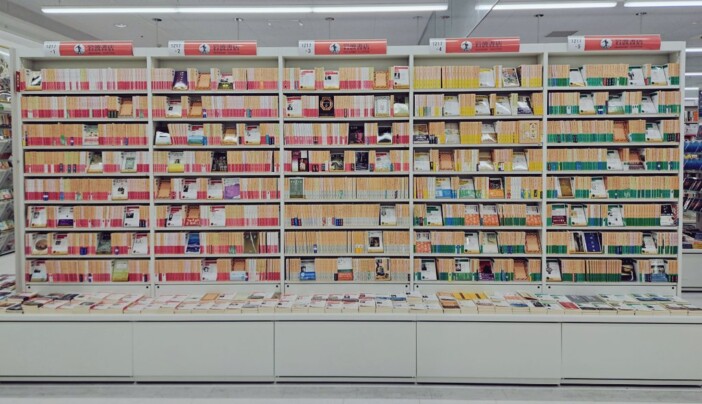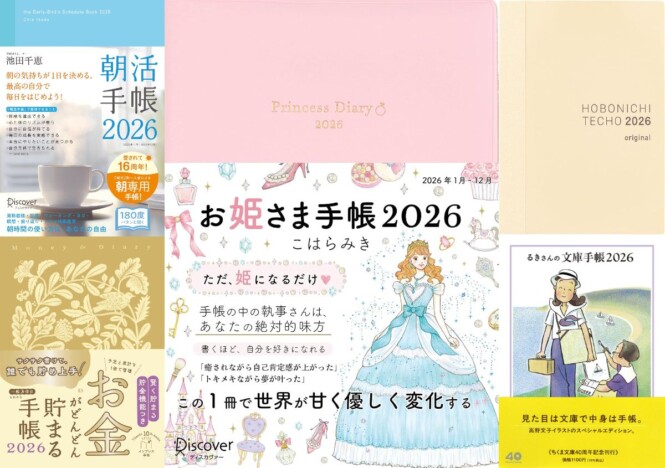書店閉店が続く地方都市で注目集まる「自治体運営の書店」や「図書館大型化」の流れ「本との出合いの場」はどう守っていく?

コロナ禍以降、書店の閉店のニュースが立て続けに報じられている。今年の7月31日は、地方都市にある書店の閉店が相次いだ。なかでも、大分市、大分駅前の中心部にある「ジュンク堂書店大分店」が、28年の歴史に幕を下ろした事は衝撃的であった。同店は1995年に開店し、約38万冊を在庫する大分県内屈指の大型書店として親しまれていた。
ジュンク堂書店大分店です!
本日は朝からたくさんのお客様にご来店いただきましてありがとうございました。常連様方のお顔、久しぶりにお見かけするお顔、皆様の温かいお言葉に感謝しています。多くの方に見守っていただきながら閉店の時を迎えました。28年のご愛顧ありがとうございました。 pic.twitter.com/1b1ykseQlm— 【閉店】ジュンク堂書店大分店 (@junkuoita) July 31, 2023
また、1961年から続いた愛知県名古屋市の老舗書店「ちくさ正文館書店」も、7月31日に閉店した。人文書や文芸書などを中心にした独自の品ぞろえで有名で、こういった店主の個性が色濃く出た書店の閉店が後を絶たない。ちなみに、名古屋市では1918年創業の「正文館書店」の「本店」が、6月30日に閉店している。
他にも、大阪府高槻市の阪急高槻市駅前にあった「ダイハン書房 高槻店」や、山梨県都留市にあった「ブックスカトー都留店」も7月31日に閉店した。どんなに地方都市といえども、大分市は人口約47万人、高槻市は人口約35万人の規模である。また、都留市は都留文科大学を有する学生街にあった書店であった。こうした都市であっても、書店が苦境に立たされている実態が浮き彫りになった。
既存の書店にダメージを与えているのは、ひとえにネット書店の台頭が大きい。また、電子書籍の普及がコロナ禍で急速に進んだことも背景にあるとされる。さらには、地方都市の人口は減少が続き、郊外化も進むため、町の中心部、とりわけ駅前を行き交う人口が減少傾向にある。さらに3年半にわたって続いたコロナ禍によって、鉄道の利用者が減少したことも痛手になっているであろう。
今後も書店に限らず、地方の駅前にある大型小売店は閉店が続く可能性が高い。ネット通販にシェアを奪われてしまっている地方の百貨店についても同じことがいえる。百貨店もおそらく、東京、大阪、名古屋、福岡などの大都市圏を除けば、10年後にはほぼ残っていない可能性が高い。駅前の大型書店は、さらなる苦境が予想される。
書店の場合、ネット通販では得難い偶然の出合いがある。また、書店は地方の文化の殿堂でもあるはずだ。こうした存在を簡単になくしていいのだろうか。電子書籍によって、特に漫画を出版している出版社は業績が伸びている。そんな今だからこそ、出版業界が一丸となって書店を守るための行動を考えることが必要だ。
書店存続の光となるか 全国初の自治体運営「八戸ブックセンター」はなぜ実現できた?「本の街をつくる」元市長の熱き想い
2016年12月に青森県八戸市に開店した「八戸ブックセンター」は、全国でも類例がほとんどない自治体が運営する書店である。書店が全…
書店が閉店する一方で、青森県八戸市にある「八戸ブックセンター」の自治体運営の書店や図書館の大型化が注目されている。高度成長期に建てられた図書館が改築される例が相次ぎ、カフェを併設するなど、読書目的だけではない人も集まれる魅力的な空間が生み出されつつある。既存の書店とこうした図書館は、いかに棲み分けを行いつつ、共存もしていくべきか。民間と行政が共存共栄の道を探っていくことが、今後の地方の文化を保つ上では必要なのではないだろうか。