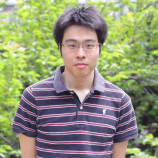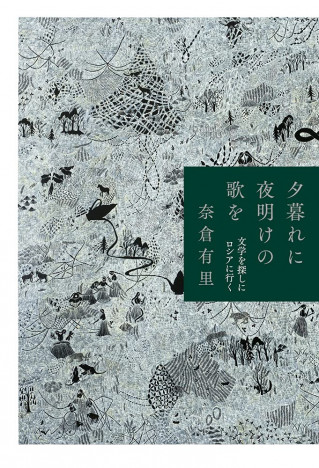コラムニスト・小田嶋隆の遺作小説『東京四次元紀行』書評 断片的なものとして「余白」を重視すること

2022年6月24日、反骨のコラムニストとして知られた小田嶋隆さんが亡くなった。享年65歳。かくして、その死の直前の6月5日に発刊された『東京四次元紀行』(イースト・プレス)は、小田嶋さんの初となる小説集になったと同時に、彼の生涯をしめくくる遺作ともなった。
私自身は、小田嶋さんと一面識もなかった一介のファンに過ぎないが、それでも、自身の揺れ動く気持ちを抑えられず、本稿は「書評」の枠を逸脱したいささか奇妙な文章になるかもしれない。その点はあらかじめお詫びしつつ、以下をお読みいただければと思う。
東京23区の物語と、〈プラスアルファ〉の物語
『東京四次元紀行』には、東京のすべての区を舞台とした23篇と、〈プラスアルファ〉の9篇、計32篇のショートストーリーが収録されている。
本作は小田嶋さんを思わせる「私」が、1983年の夏に仕事を辞めてぶらぶらしていた時、運転していた車に突然、健二というチンピラ風の男が乗り込む「残骸-新宿区」からはじまる。「私」は新宿の駅前まで健二を乗せ、軽く身の上話を聞いたくらいで彼と別れるが、その数年後、覚せい剤取締法違反で健二が逮捕されたというニュースを見かける。さらに数年後には、新宿の路地で声をかけてきた「オカマ」の街娼(※現在、「オカマ」という表現には使用を差し控えるべき側面がありますが、舞台の時代背景や小田嶋さんの意図を考慮し、使用させていただきました)に彼の面影を見る。
続く「地元―江戸川区」では健二が主人公となる。彼は事実婚(という言葉を小田嶋さんが嫌っている節はあるものの)状態にあった静子を正拳突きで気絶させ、アパートを出ていく。
その次の「傷跡―千代田区」では健二から暴行を受けた静子が、病院で全治3ヶ月の診断を受けたのち、自分のもとにやってきた健二の舎弟を名乗る男から300万円を受け取る。さらに次の「穴-墨田区」では、ふたたび健二が……というように、23のエピソードはそれぞれ独立した話でありつつも、どこかで根底でのつながりを見せる。
……はずだと、『東京四次元紀行』の途中までは思っていた。思っていただけではなく、早合点して上記のようなことを書いた。しかし、さらに読み進めてみると、案外そうでもないことに気づかされた。
健二からはじまる物語の系譜は、健二と静子の娘・彩美を主人公とする「サキソフォン―杉並区」でいったんはひと段落する。それ以降では、「八百屋お七-文京区」からはじまる3つの物語で大楠道代似の気概ある女性・七子と、配偶者となる篠田との出会いから破局までが描かれ、また、「猫―足立区」からはじまる3つの物語は秋山遼太郎という男の〈猫〉を軸にした足取りが描かれるものの、そのほかの物語には、これといった連続性はない。「プラ粘土」からはじまる、〈プラスアルファ〉の9篇も同様である。
また、エピソードの一つひとつに、明確なストーリーラインが見られるわけでもない。たとえば「継母の不倫-江東区」は、看護師の涼音が、いまは別居している継母が自身の職場の医師と不倫していることを知るが、それが昼ドラのような決定的な修羅場につながるということはない。涼音は継母の事情を話すため、医師を職場で呼び止めるが、説明の過程で彼に好意を持ち始めていることに気づく。それは涼音が、継母から医師を奪うという新たな展開の伏線であることを匂わせつつも、しかし、そのようにはっきりと描かれるわけでもない。いささか宙ぶらりんな感触を残したまま、この物語は幕を閉じる。
加えて、ものごとの真偽についても、語り口はあいまいである。
「ダイヤモンドー港区」でいえば、はたして母の遺した結婚指輪は、娘である由布子の指摘する通り〈子供でもわかるようなデカいガラス玉のおもちゃ〉であったのかどうか。「鳩」でいえば、神奈川県から転校してきた中学生・太田原純一が飼い、帰還訓練を施していた6羽の鳩は、やがて純一が語るように、すべて焼かれて食べられたのかどうか。情報は断片的で、はっきりと白黒をつけることはできない。
どうもねちねちと揚げ足ばかりをとるような書き方を重ねてきたが、しかし、誤解するなかれ。それらは決して、本作の欠点などではない。
そもそも、「序文」に小田嶋さんの宣言はあったではないか。「視点が定まらず、論理の一貫しない、曖昧な」、あるいは、「起承転結や序破急のカタチにおさまらない」文章を書くのだ、と。
そして、これは奇をてらった書き方というよりも、むしろ現実の肌触りを小説という形で保持するうえでの小田嶋さんの戦略と言うべきだろう。「街の中に置かれている人間は、もともと断片的なのだから」――そう小田嶋さんが語るように、私たちは日常の中ですれ違う人々について、「全体」を知ることはできない。本作にもほのめかしがあるように、ちょうどいま、街の路上で私を追い抜いた小指のない男性は、やくざではなく単に指を「焼いて食った」のかもしれないし、反対方向を歩いてくる赤子を連れた女性は、自身の子ではなく、配偶者の不倫相手が産んだ子供を育てているのかもしれない。想像するといささか恐ろしくもなるものの、日常においてはそのような「余白」があるからこそ、目の前の人をより主体的に知ろうとする気持ちは生まれ、人間関係はより芳醇なものへと変化していく。
『東京四次元紀行』は情報の抑制に加え、登場人物の心情描写も抑制的だ。重大な決断、もしくは事件に際しての心の揺れ動きもさらっとした形で流しており、そのこともまた、「余白」の顕在化に奏功している。はじめはやや面食らいながらも、読み進めるうちに、想像を刺激する小田嶋スタイルが、いつしか自分の中でやみつきになっていることに気づかされていく。
「余白」に目を向けること
小田嶋さんは短い文章のなかに本質的な提言を詰め込むことで、Twitter上でも人気を博した。ただ、人の営みは簡単に白か黒かで割り切れるものではない。小田嶋さん自身も140字の制限のなかでさまざまな表現を、ときには露悪的なかたちで駆使しながらも、同時にSNSでの言説がしばしば陥りがちな、安易な価値判断や類推、また他者への否定に対しては、つねに懐疑的な視点を持ちつづけた。
いまの社会では、明快で、強く、わかりやすい情報が尊重されるいっぽうで、その範疇におさまらない、あいまいで、弱く、わかりにくいものについては、ほぼそぎ落とされてしまう。しかし、人間の感情はそもそも軸が容易に定まらない、あいまいでもろい「余白」を残したものではあるし、それらに目を向けることこそが、本来であれば人間理解の上でも重要な軸となるはずだ。人が生きるということ、その複雑さに迫ることを『東京四次元紀行』は私たちにうながす。
『東京四次元紀行』の登場人物たちは、「強さ」に満ちているとは言えない。ささいな過去の傷――あの時に行動できなかったこと、逆に極端な行動に身を任せてしまったこと、約束を守れなかったことなどに頭を悩ませ続け、あてもなく躊躇や逡巡を続ける。小田嶋さんはそんな彼らの声を丹念に掬い上げつつ、同時に、いたずらに鳥瞰的な視点で彼らを描こうともしていない。いわば本作での小田嶋さんは、断片的なものとして、「余白」を重視するスタイルを貫くことで、それぞれの人間の生を尊重しているのである。
この場で告白すると、冒頭に述べたように私自身は小田嶋さんと一面識もないものの、この『東京四次元紀行』では小田嶋さんに著者インタビューができないかと、いくつかの媒体にかけあっていた。
結果的に、それは小田嶋さんの死によって実現はできなかった。そのため、ここにも「余白」は残った。しかし、結果的に「余白」のすべては埋まらないにしても、同時に、埋めようとする努力は放棄するべきではない。「わかる」というには努力が足りなすぎるし、「わからない」とあきらめるには時期尚早すぎる。……ううん、まとまらんし、感傷的な言葉はさらにいろいろと出てきそうだ。しかし、『東京四次元紀行』における「余白」の流儀にならい、このあたりで切り上げよう。ハンカチで顔を拭き、少し休憩したあとは、小田嶋さんの遺した色とりどりのテクストをふたたび読み返しつつ、またゆっくりと考えていきたいと思う。