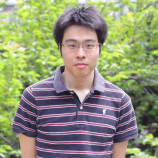ロシアの分断に抗う文学「心の故郷」のあたたかさを 奈倉有里『夕暮れに夜明けの歌を』書評
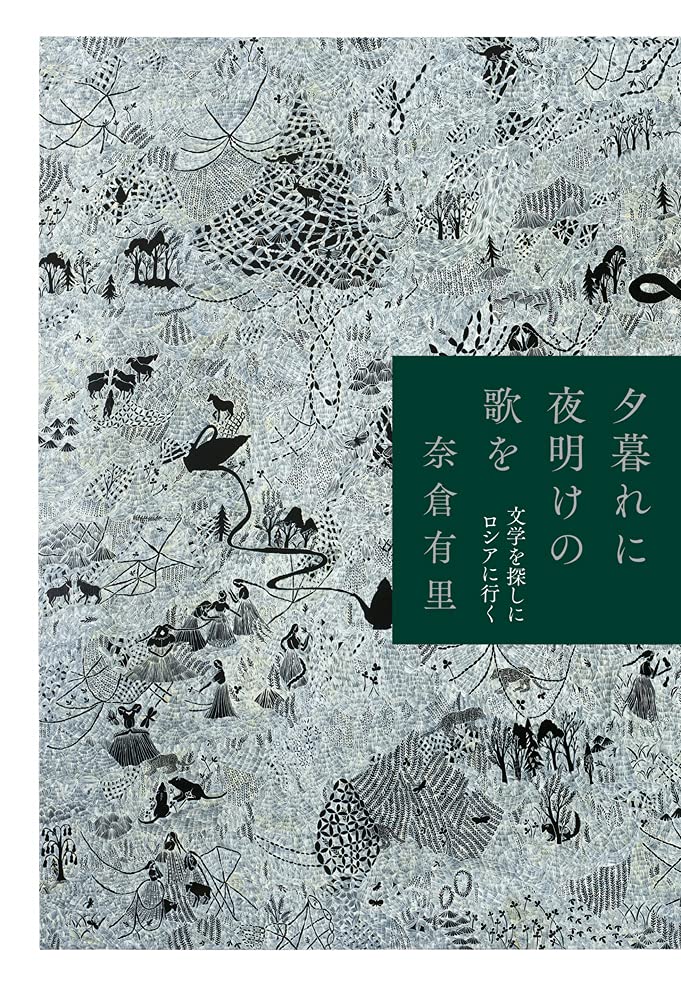
『夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く』(イースト・プレス)は、高校卒業後に単身ロシアにわたり、日本人としてはじめてロシア国立ゴーリキー文学大学を卒業した文学研究者・奈倉有里さんによる随筆集だ。2002年から2008年のロシア滞在で交流を得た教師と学友たちとの思い出や、その後しだいに分断と言論統制が進んでいくロシアの姿を、かつて抑圧に立ち向かった作家たちの言葉を引きながら綴っていく。
その語り口は穏やかでありつつものびやかで、誠実につむがれた一語一句は、ページをめくるたびに読者の心へじんわりと染みわたってくる。そして、本書は言葉の尊さをたしかなかたちで感じさせると同時に、人の奥底にある「心の故郷」とも呼ぶべき存在について、多くの示唆を与えてくれる一冊でもある。
「心の故郷」の感覚
筆者自身は残念ながら、これまでロシアを訪れたことはない。しかし不思議と、本書を読むとちょうど自身にも覚えがある、「心の故郷」が生みだすあたたかみのような感情が訪れた。
それははじめてロシアを訪れるまでの奈倉さんの「ロシア」のイメージが、「ほぼ新潟」、ひいては「ほぼ故郷」であったことが、重要なヒントになるかもしれない。当時、未成年だった奈倉さんは、文学や語学を通して19世紀のロシアの姿に触れていた。テクストの中に登場する冬の自然や人々の苦悩は、より身近な場所にあるもののように思えていたという。ちょうど母方の祖父が住む地であり、母の故郷である雪国・新潟で自身が体験したものであるかのように記憶のなかに刻まれていた。
そうしたこともあってか、やがてロシアに向かう飛行機の中で、これからの生活で生まれるであろう苦労や不安もすべてが「故郷の味」であるように思えてきた奈倉さんは、留学生活の中で「故郷」としてのロシア像を、心のうちにふたたびかたちづくってきた。
文学翻訳家のレーヴィチ先生の翻訳指導を受けたとき、彼の旧友と同じ名前であったことから「あなたがユリという名前でよかった」という言葉を繰り返しもらったこと。寮友のマーシャと夜通し語り合うなかでふと『千と千尋の神隠し』の話題が出て、主題歌の『いつも何度でも』を一緒に口ずさんだこと。酒飲みで有名なアントーノフ先生の姿を歴史図書館で見かけ、のびのびと好きな研究をしているその姿に励みをもらったこと……。情愛に満ちた筆致とともに語られるこうしたエピソードの一つひとつは、もちろん奈倉さんに固有のものではある。ただ、そのような学生時代の思い出は少なくない読者が持つものであろうし、同時に、一人ひとりの心のよすがとも親和性のあるものだろう。奈倉さんは日々を重ねるなかで、「住んだところがふるさとになる」ことをしだいに実感していく。
分断が進むロシアの現在
そのようにして生まれた「故郷」のあたたかみはしかし、ロシアの分断が深まるなかで、しだいに危機にさらされていく。本書では2004年に起きた、350人以上の死者を出したベスラン学校占拠事件や、ウクライナ侵攻の前史となる、2014年のロシアによるクリミア半島の編入宣言、およびドンバス地方の紛争に触れられる。
そのなかで奈倉さんは、人の個別の生に目を向けることを重視する。たとえば、ニュース番組でウクライナの反戦運動が凶悪な暴動のようにとらえられること、ウクライナ人に「狡くて欲張りで少し頭が足りない」といった画一的なイメージを付与することへの怒りを見せる。
また、地方自治体が機能せず、電気も病院も満足にない暮らしを強いられる、いわば「グレーゾーン」に暮らすドンバスの人々に思いをはせ、それぞれの人にどのような思いや背景があるのかに注意深く想像を向けること、つまり「それぞれの灰色に目を凝らすこと」がなければ、対立は終わらないはずだと述べる。
そうした個々人の生を尊重する姿勢は、両国の紛争について「マルーシャやシーシキンや、そのほか数えきれないほどのウクライナとロシアの両方に出自を持った人々にとって、身体を引き裂かれるような痛みだった」と語る一節からも読み取れる。シーシキンはモスクワ出身の名の知られた作家だが、マルーシャはウクライナ東部に祖父母を持つ奈倉さんの学友である。つまり、奈倉さんのなかでは、高名な作家も、日常的に話すクラスメートも、その存在の大切さに変わりはなく、何らかの基準によってそこに優劣をつける姿勢とは、はっきりと距離を置いている。言いかえれば奈倉さんは、高尚なものとそうでないものをわけるような、容易に人と人との分断にも変化しうる境界線の芽を、文章の上で注意深く摘み取ることを一貫して意識している。
同時に、故郷とはそもそも、そのような境界線が存在しないものなのだと思う。思い出のなかでは、友情を育んだ同級生や恋人、親しんできたスポーツ、行きつけの喫茶店、一押しの芸能人、話題の政治的トピックまで、自分の糧になってきたさまざまな要素が区別なくシームレスに重なり合い、やがて自分の原風景として――「故郷」としてかたちづくられていく。
「橋」はどこにかけられるのか
では、私たちは「故郷」をどのようにつなげることができるか。奈倉さんがその鍵として提示するのは、言葉の存在である。
奈倉さんはウクライナ侵攻が起きたのち、「無数の橋をかけなおす――ロシアから届く反戦の声」(「新潮」2022年5月号)と題された随筆を発表している。文学者や音楽家をはじめ、さまざまな立場の人たちが、ロシアに対して各々の方法であげた「声」について綴ったこの随筆においては、言葉を守ること、言葉によって生み出される「人の内面世界を救うこと」こそが、戦争を含む、人間の心のうちにある残虐さに対峙する方法であることが示唆される。
それは『夕暮れに夜明けの歌を』の後半で奈倉さんが語る、「人は言葉に実態を見出し、喜び、言葉に傷つき、言葉によって生かされている」という一節とも、あるいはあとがきで示される、さまざまな世界の矛盾に対して奈倉さんが無力でなかった唯一の時間が「学友たちと歌をうたい詩を読み、小説の引用や文体模倣をして、笑ったり泣いたりしていたその瞬間」であったこととも、根底の部分で響き合いを見せるだろう。
人を生かし、人をつなぐ存在となる言葉。「無数の橋をかけなおす」においては、言葉を通して「橋」をかけつづけることの意義が強調されるが、では「橋」は最後には、どこにかけられるのだろうか。
それは個々人の生が踏みにじられる、現在の土地に対してではない。また、かつて存在した過去の土地に、憧憬のようなかたちでかけられるものでもないだろう。人と人がお互いに敬意を持ち、ともに言葉によって歩もうとする未来の――これからつくられるまだ見ぬ土地へと、その橋はかけられるはずだ。なぜなら、奈倉さんがそうであったように、故郷は振り返るものではなく、自らの手で作り出すものであるからだ。
本書で引用される、アンドレイ・マカレーヴィチ『空虚な約束を』の歌詞にある「この世界の光は闇より少しだけ多い」という言葉を、無条件に肯定することは今はできない。それでも、言葉によって心のよすがとなる「故郷」の光は生まれ、それは未来にかけられる橋への羅針盤ともなりえるはずだと信じたい。なによりも、言葉によって生まれる光の尊さをたしかなかたちで示した『夕暮れに夜明けの歌を』という本の存在こそが、私が抱いたような希望の、けっして脆弱ではない礎の役割を果たしてくれるのである。