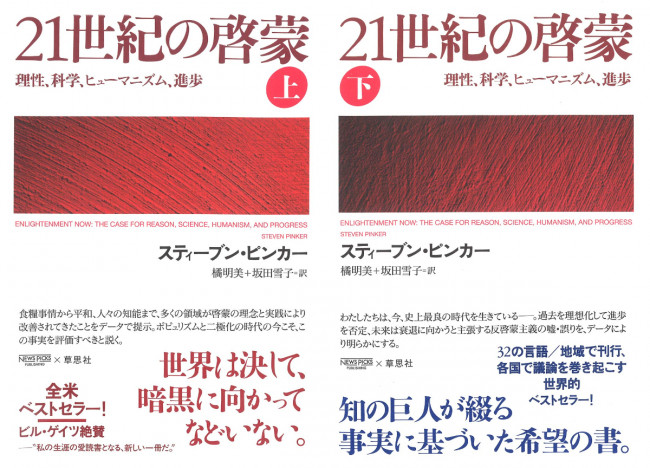フローの時代の似顔絵――多和田葉子『地球にちりばめられて』+村田沙耶香『信仰』評

書物という名のウイルス 第13回
多和田葉子の試み
思えば、多和田葉子の1990年代半ばの代表作『ゴットハルト鉄道』(講談社)の語り手は「ゴットハルト」という一つの単語にバチッと感電して、そこからとめどなく妄想を膨らませてゆく。執拗にからみつく言葉に惑溺するなか「外に出なさい」というささやき声をも響かせたところに、この小説の独創性があった。言語中毒者を言葉によって解毒する――この悪循環的な迷宮性には、平成文学の重要な特徴が濃縮されてもいる。
逆に、そのおよそ20年後の『地球にちりばめられて』では、一つ一つの言葉の電力はかなり控えめである。一つの単語に執念深くまといつくことを、今の著者はむしろ避けている――というより、「ゴットハルト」のような特別な電源はもはやあてにできないのだ。ゆえに《日本列島に後見されない日本語》を、ありあわせでもいいから何とかひねり出し、小さな火力を備えた言葉の薪に仕立ててゆくことが、『地球にちりばめられて』およびその続編『星に仄めかされて』(2020年)のモチーフになったと言えるだろう。
とはいえ、その試みも簡単ではない。多和田はデリート・キーを押すように日本を抹消したが、それは文体的な代償を伴っている。少なくとも、『日本語が亡びるとき』(2008年/筑摩書房)や『本格小説』(2005年/新潮社)を書いた水村美苗ならば、本書のようなあっさりした処理で「日本」をキャンセルすることはないだろう。水村は日本語についてのイデアリスティックな像を抱いており、それが彼女の端正にしてきめの細かい文体を支えている。たとえアナクロニズムであったとしても、丹念に彫琢されてきた文学の言葉の伝統がなければ、思想や感情の繊細なディテールは写像できないという「信」が水村にはあった。
逆に、本書のピジン語(らしきもの)はありあわせであり、任意性にさらされている。そもそも、Hirukoお手製の即興言語〈パンスカ〉(汎スカンジナビア言語)がどういうものか、具体的な説明は乏しい――これは本書の難点だろう。「言葉が記憶の細かい襞に沿って流れ、小さな光るものを一つも見落とさずに拾いながら、とんでもない遠くまで連れて行ってくれる」パンスカは「母語よりもずっと優れた乗り物だ」と書かれてはいるけれども、仮にこの即興言語にそれほどの性能があるならば、母語を探す旅はますます必然性を失うのではないか。
多和田のファンの読み方とは違うだろうが、私は本書にうっすらとしたニヒリズムを感じた。そこでは、言葉も含めて何ものも「信」の核にならず、国を喪失した痛みも生じない(不在の日本を懐かしんだり、復興したりすることは、本書では保守反動として扱われる)。だが、多和田は虚無を軽やかに生き抜くスタイリストでもない。北欧を横滑りしながら、小説の電源となる言葉に出会おうとするパトス(情熱=受苦)は、物語の奥に染み込んでいる。ただし、そのパトスは火柱となって燃え上がることなく(あるいは初期の多和田好みのモチーフで言えば、主人公を「転落」させることもなく)、地球というサーキットに「ちりばめられて」ゆくのである。