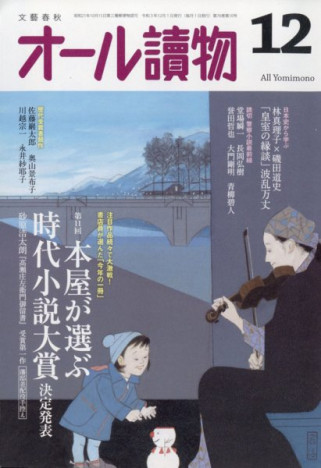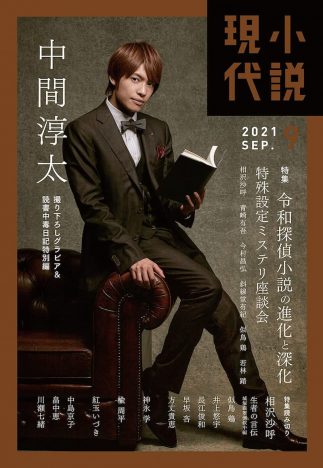鈴木涼美が語る、女性ファッション誌「JJ」が与えてくれたもの 「20歳前後の女性にとって強烈な光となっていた」

作家・鈴木涼美による新書『JJとその時代 女のコは雑誌に何を夢見たのか』(光文社新書)は、数々の人気モデルを輩出し、女子大生を夢中にさせ、部数80万を誇った雑誌「JJ」を軸に、女性ファッション誌が女性たちにどんな価値や思想を提供してきたのかを論じた一冊だ。女性ファッション誌が次々と廃刊されていく中で、何が失われたのかを見つめ直すその眼差しは、これからのメディアの行き先を考える上でも示唆に富んだものだろう。鈴木涼美に、同書に込めた想いを聞いた。(編集部)
雑誌は20歳前後の女性にとって強烈な光となっていた

――『JJとその時代 女のコは雑誌に何を夢見たのか』は、女性誌が次々と廃刊されていく近年において、改めてそれらがどんな役割を担っていたのかを振り返った一冊です。執筆の動機を教えてください。
鈴木:女性誌については以前からどこかで書きたいと思っていて、特に「JJ」「CanCam」「egg」など、多くの人がイメージを共有している雑誌を取り上げたいと考えていました。おっしゃるように近年は女性誌がどんどんなくなってしまっていて、ギャル雑誌「egg」などがWebで復活したりはしているものの、雑誌の時代はもう終わってしまうのかなと感じていて、小さい頃から雑誌に親しんできた人間として、どういう文化があったのかをまとめておきたかったんです。そんな折にもともと「JJ」編集部にいた光文社の編集者から、女性誌についての本を書かないかとお声がけいただいて。私自身「JJ」はすごく憧れの雑誌だったので、ぜひ書きたいと応えたんです。当時はまだ「JJ」が刊行されていたんですけれど、ゆっくり書いていたら2021年2月号で事実上の休刊となってしまいました。結果的に、ひとつの時代の終わりを示す本になったと思います。
――本書を読むと、それぞれの雑誌がいかに明快なコンセプトを提示してきたかがわかります。Webの場合は一本一本の記事単位で読まれるために、一つのサイトの中にいろんなタイプの記事を入れることができる面白さがありますが、雑誌の方がよりコンセプトが強固で、その分、紙面全体で強いメッセージを発信していたように思います。
鈴木:そうですね。音楽雑誌にしても、好きなミュージシャンによって読者がそれぞれ違う雑誌を読むのが普通でした。雑誌というパッケージで買うからこそ、一緒に載っているほかの記事を読んで新たに得る情報もありました。一方でWebは書き手も想定していないような読者に届く面白さはあるけれど、「CUTiE」系や「egg」派といった大きな括りでのグループは生まれにくくなっている感じがしますね。

――女性誌が提示した思想や価値観が、どんな風に女性たちを勇気付けていたのかに焦点を当てているところが本書の特色だと思います。女性誌が提示してきた価値観は、呪縛のように日本の女性たちに取り憑き、先入観や誤解や偏見を生んだところもあるけれど、一方で「女の人生は生きるに値するものである、と活力を与えたに違いない」と書かれているのが印象的でした。
鈴木:90年代の「JJ」などを改めて読むと、現在のポリティカル・コレクトネスの観点から見て問題のある表現もあります。有名商社勤務の男性が「愛嬌があってオフィスで女性としての役割を果たしている人に惹かれます」という意見を言っていたり、「社会人2年目のOLがこれを持っていなくちゃアウト」みたいに価値観を押し付けるようなところもありました。自分の個性は自分で決めるのが理想とされる現在の価値観からはかけ離れているし、性差による役割をステレオタイプ化していた部分はあるでしょう。「JJ」は“幸せな結婚”を頂点として、女性に望まれるステレオタイプな役割を自ら引き受けつつ、それを楽しむような雑誌でした。ただ、その価値観は当時の20歳前後の女性にとって強烈な光となっていたことも確かだと思います。
実際のところ、10代から20代で自分にとって本当に必要なものがなにかとか、どんな風に生きていくべきかを明確に見定められている人なんてほとんどいないはずです。少なくとも私は全然固まっていなかったから、雑誌の提示する価値観に寄りかかって、自分は〇〇系だからこういう服を着ている、という感じでした。ファッションに強いこだわりがあったわけでもないから、このブランドのほうが私の好みに合っているとかもわからなくて、漠然と「今年はヴィトンのヴェルニが流行っているから欲しい」と思っていました。そういう意味で、宙ぶらりんの若者にとっては拠り所にもなっていたんです。
ーー当時は雑誌の影響力が大きく、若者がアイデンティティを形成する上での助けにもなっていた、と。
鈴木:そうですね。ただ、雑誌がかつての勢いを失ったからといって、若者にとって指針となるような価値観が必要なくなったかというと、必ずしもそういうわけではないと思います。人間がたかだか20年くらいで高度な生き物になるわけがないですし、いつの時代だって若者は自我がふわふわしているものでしょう。たとえば、Instagramとかに投稿されている写真を見ると、若い女性はファッションもメイクもすごく似通っていますよね。それぞれに自分らしい多様なファッションをしているわけではなく、むしろジャンルの垣根がなくなったことで無個性的になっている。ヨーロッパでもアメリカでも女子大生はカジュアルな格好をしているものなので、90年代の日本の女子大生の方が変だったのかもしれないけれど、雑誌とともに花ひらいた日本独自の文化はずいぶん減退したように思います。赤文字系だったら身の丈に合わない高級ブランドを身につけていたり、青文字系だったら不思議なセンスを発揮していたり、ギャルはギャルですごく変なファッションをしていたりしたけれど、雑誌がなくなってみんなが同じようなファッションになったということは、やはりそこで発信されていたメッセージには強い魅力があったのだと思います。