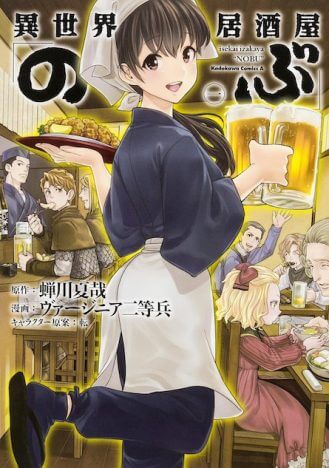本の続きが読めないなら生きている意味がないーー『死にたがりの君に贈る物語』が描き出す、深い小説愛

生活必需品、という言葉をコロナ禍になってから頻繁に耳にするようになり、緊急事態宣言が発令されるたびその定義に紛糾している。最近では、それに当たらない豪奢(ごうしゃ)品の販売を控えるようにというお達しに、高級かどうかの判断は客によって異なると声明をだした百貨店もあった。
他人からみれば取るに足らない何かに生かされる
ここでいう生活必需品とはライフライン、つまり供給が途絶えると確実に死ぬものという意味だろうが、「人はパンのみにて生くるものにあらず」と聖書にも書かれているように、人の生命を維持するものは水と食糧だけではない。「これがあるからどうにか明日も生きようと思える」と人がすがりつくものは、むしろ、他人から見ればどうということのない些末なものじゃないかと思う。
推しのアイドルによって生かされ、その炎上と引退によって背骨を失うに等しい傷を受けた主人公を描いた宇佐見りん『推し、燃ゆ』が、芥川賞受賞から3カ月たった今も売れ続け、50万部を突破したのはおそらく、主人公と同じように他人からみれば取るに足らない何かに生かされていると感じる人たちが多いからじゃないだろうか。
本も、同じだ。作家がシリーズ完結の前に急逝したことで生きる希望を失い自殺をはかった16歳の少女。『死にたがりの君に贈る物語』(綾崎隼/ポプラ社)で描かれる彼女、純恋(すみれ)を両親は「なんて馬鹿なことを」と叱る。売れているからといって素晴らしい内容とは限らない、くだらない本のために命を捨てようとするなんて許さない、と。けれどそんな両親に彼女は言うのだ。「本の続きが読めないなら生きている意味がない」。
亡くなった作家の名前はミマサカリオリ。デビュー三年目にして、10代20代に熱狂的なファンをもつ年齢も性別も非公表の覆面作家だ。デビュー作であり代表作の『Swallowtail Waltz』シリーズは既刊5巻で累計発行部数400万部を突破。実写映画化とドラマ化、そしてアニメ化も果たした大ヒット作の著者が作品を完結させる前に亡くなったとなれば、打ちひしがれる人の数も相当なものだろう。
でも死ぬほどじゃなくない?と思う人も、もちろんいるだろう。たかが小説でしょ?と。純恋の両親のように。けれど純恋にとっては「たかが」じゃなかった。勉強もできない。特技もない。友達もいない。高校をやめたときには母親に「あんたみたいな子、産まなきゃよかった」と言われ、「どうして私みたいな屑が生まれてきたんだろう」と思い続けてきた彼女は、『Swallowtail Waltz』を読んで初めて、「こんなに面白い本があるんだったら、生きていよう」「この本を読み終わるまでは、生きていたい」と思えた。文字どおり生命維持装置だった作品が、未完のまま永遠に閉じたとなれば、死を選ぶのは彼女にとって当然のことだったのだ。その切実さを、誰に笑うことができるだろう。