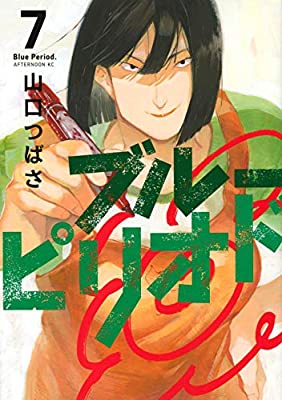美術マンガ『ブルーピリオド』が描く“青の時代”とは? 絵を描くこと、表現することへの葛藤

※本稿は『ブルーピリオド』第10巻のネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。
「青」といっても色々ある。鮮やかなウルトラマリンに濃いプルシアン。爽やかな群青に深い紺青。それらの「青」から浮かぶイメージも、晴れ晴れとしていたり沈んでいたりと様々だ。
マンガ大賞2020を受賞し、5月21日に最新の第10巻が出た山口つばさ『ブルーピリオド』(講談社)にも、多彩な「青」がちりばめられていて、新緑のようにわき出る興味を誘ったり、憂鬱に沈む気持ちに寄り添ったりしてくれる。
同級生たちと出歩き、飲んでサッカーを見て騒ぐだけの日々を送っていたマイルドヤンキーの高校生、矢口八虎が美術に興味をひかれ、美術部で絵を描き始める。自分で何かを作る喜びを知った八虎は、倍率が最高という東京藝術大学美術学部絵画科の油画専攻に進みたいと考え、美大予備校に通って本格的に絵に取り組み始める。
以上が『ブルーピリオド』のイントロダクション。タイトルには元ネタがあって、不世出の大画家、パブロ・ピカソの生涯で20歳あたりから数年間続いた「青の時代」からとられている。この頃のピカソの絵は、青い背景に沈み込むように、裕福には見えない人たちが不健康そうな顔色で描かれ、見る人を陰々滅々とした気分へと引きずり込む。
芸術に行き詰まっていたというよりは、当時のピカソが陥っていた精神状態が反映されたもののようだが、情熱的で奔放なイメージのピカソにあって「青の時代」の作品は、若さ故の苦悩が反映されたものとも捉えられそう。『ブルーピリオド』で八虎や美大を目指す他の予備校生たちが、技術に苦しみモチーフに悩む姿はまさに「青の時代」といったところだ。
そんな谷底のような陰鬱とした青に、八虎が明け方の渋谷で感じた爽やかな青を差すような感じで、藝大合格という大目標を突破し澄み切った蒼天に駆け上る展開で、『ブルーピリオド』という作品が大団円を迎えても変ではなかった。ところが、山口つばさはその先に、より混沌とした「ブルーピリオド」を用意していた。
八虎は、美大予備校で知り合った絵の天才、高橋世田介といっしょに藝大の油画専攻に合格し、新たな第一歩を踏み出す。藝大なり美大に合格するためのテクニックを知れるハウツーコミックとしても楽しめたストーリーは、ここから美術の本質へと迫る泥濘へとハマり込んでいく。
入学前に描いた作品を藝大の教授たちに見せた八虎に、教授は「コレから先どういう作品を作っていきたいの?」と尋ね、最初の課題の「自画像」のコンセプトに「これ絵画でやる意味ある?」と問う。美術とは絵を描くことで、藝大とは絵を学ぶ学科で、だから絵を描いて当たり前と思っていたら否定された。絵を描くとは何か。そもそも表現するとはどういうことかといった疑問にぶち当たり、八虎は迷い始める。
「藝大に入って1年生の時に、何を描いたら良いか分からなくなってしまったんです。そこで、自分が好きだったものの原点に戻ろうと思い、マンガを描き始めました」。マンガ大賞2020の贈賞式での山口つばさのコメントに、藝大進学を果たした第7巻から描かれる内容が、示唆されていたように今なら思える。『ブルーピリオド』というタイトルに込めて描こうとしていたものが立ち現れたのだとも。