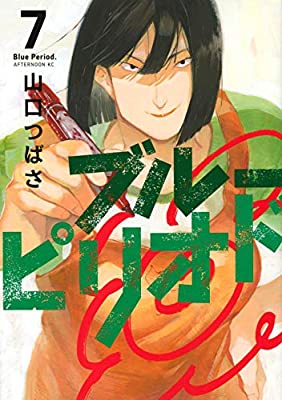美術マンガ『ブルーピリオド』が描く“青の時代”とは? 絵を描くこと、表現することへの葛藤


絵のド素人からスタートした八虎が悩むのは当然だが、第10巻ではさらに、天才的な画力を持っていて、描くことに一切の迷いも悩みもないように見えた世田介をも、混沌とした青色が包み込む。
冒頭、「絵を描くの好き?」と聞いた八虎に世田介は、「絵を描くのが好きだと思ったこと、一度もない」と答え、「それって何か意味あるの?」と聞き返す。好きでなければ描いてはいけないのか。巧いから描くだけではいけないのか。子供の頃に巧いと褒められ、そのまま描き続けてきた延長線上で藝大まで来た世田介にとって、描くことはただ描くことで、それ以上でも以下でもなかった。そんな世田介を初めて襲った葛藤が、覚醒へと至る「青の時代」が、第10巻を通して描かれていく。
こう言うと、憂鬱と例えられるダークな青色ばかりが目立つ作品だが、新入生たちが力を合わせて神輿を作り、おそろいの法被を着て踊り、模擬店を出して盛り上がる様はまさしく青春。新緑が芽吹き、生命感があふれ出すライトな青色に彩られていて目が眩む。新型コロナウイルス感染症の影響で大学に通えず、友達作りもままならない状況が終わり、悩みもあれば喜びもある青色のグラデーションに、早く包まれるようになって欲しいものだ。

コミックでは他に、第1回のマンガ大賞を『岳 みんなの山』で受賞した石塚真一による、『BLUE GIANT』というシリーズがある。仙台で育った宮本大が世界一のジャズプレイヤーになると決め、テナーサックスを吹き始めて幕を開けた物語は、日本を出て欧州に渡った大が癖のある仲間たちちと出会い、ジャズプレイヤーとして名前を知られていく『BLUE GIANTGIANT SUPREME』を経て、ジャズの本場アメリカでの旅を描く『BLUE GIANT EXPROLER』へと続く。
天文用語で激しく燃える星を青色巨星=ブルージャイアントと呼び、転じてジャズプレイヤーの中でひときわ明るい輝きを放つ存在をそう呼ぶようになったという。大が目指すのもそんな巨星。だから『BLUE GIANT』というタイトルになった。
自分のやることに迷いを持たず、雲ひとつない蒼天を突き進むイメージの大は、美術とは何かに迷う「青の時代」を生きる八虎や世田介たちは正反対だ。そんな3人が青春の旅を経てたどり着くのはどんな場所かを見たくてたまらないどちらも紆余曲折はあるだろうが、歩みだけは止めないで欲しい。人間至る所青山あり、なのだから。
■タニグチリウイチ
愛知県生まれ、書評家・ライター。ライトノベルを中心に『SFマガジン』『ミステリマガジン』で書評を執筆、本の雑誌社『おすすめ文庫王国』でもライトノベルのベスト10を紹介。文庫解説では越谷オサム『いとみち』3部作をすべて担当。小学館の『漫画家本』シリーズに細野不二彦、一ノ関圭、小山ゆうらの作品評を執筆。2019年3月まで勤務していた新聞社ではアニメやゲームの記事を良く手がけ、退職後もアニメや映画の監督インタビュー、エンタメ系イベントのリポートなどを各所に執筆。
■書誌情報
『ブルーピリオド』1〜10巻発売中(アフタヌーンKC)
著者:山口つばさ
出版社:講談社