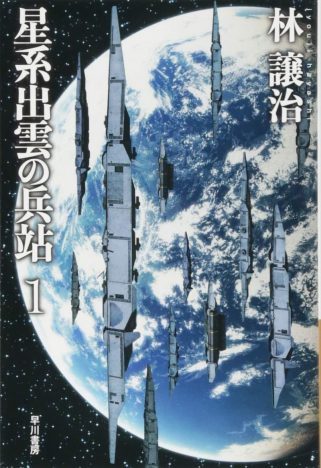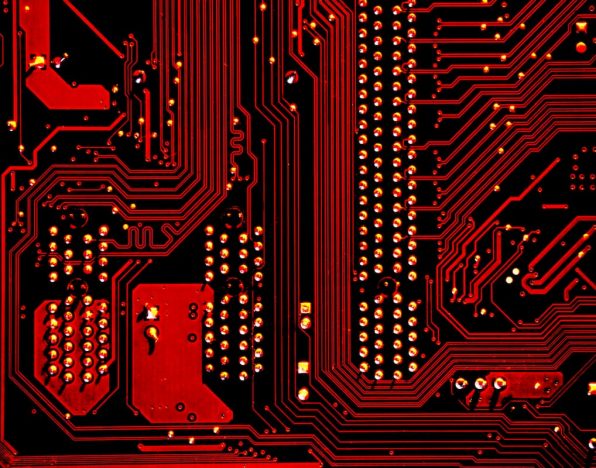完璧な贋作に価値はあるか? SF大賞受賞作『歓喜の歌 博物館惑星III』が問う、芸術とテクノロジーの未来

地球を挟んで月とは反対側の衛星軌道上に浮かぶ〈アフロディーテ〉には、全世界のありとあらゆる美術品や芸術品、動植物が集められていて、所属する学芸員たちが収蔵や鑑定、保存のために働いている。そんな〈アフロディーテ〉を舞台に起こる事件を連作で綴った最初の単行本『永遠の森 博物館惑星』が2000年に刊行され、第21回日本SF大賞にノミネートされた。
受賞は逃したが、ミステリーとして評価されて日本推理作家協会賞の長編及び連作短編部門を受賞。ライトノベルやSFの分野では既に知られていた菅浩江が、さらに広く知られるきっかけとなった。それから実に19年を経て2019年に刊行された待望の続編が『不見の月 博物館惑星II』だった。
第1作の登場人物たちが年齢を重ね、幹部として働く〈アフロディーテ〉に、警察に相当する自警団員の兵藤健が新人として赴任し、同じ新人で3部門を管轄する〈アポロン〉に配属された尚美・シャハムとともに、美術とテクノロジーが絡んだ様々な案件に挑んでいくエピソードが連作で綴られていく。
〈アフロディーテ〉ができた当時に地球から移ってきた老人が、演奏し続けた手回しオルガンが〈アフロディーテ〉の50周年を記念する品として注目されたものの、貴重な工芸品として劣化を防ぐ処理を施すべきか、修理を続けながら楽器として演奏できる状態を保つべきかで、学芸員たちの意見が分かれる「手回しオルガン」。画家が傑作とされる自分の絵に何かを塗り込めた理由に迫る「不見の月」。どちらも、美が持つ意味を問う展開がある。そして、「不見の月」だったら絵を損壊せず塗り込められた何かを分析して、焼いた場合に起こる変化をシミュレートする未来的なテクノロジーが提示される。
その『不見の月 博物館惑星II』から、登場人物もストーリーも引き継いだ連作短編が収録されたのが『歓喜の歌 博物館惑星III』だ。最高峰の人材がそろった〈アフロディーテ〉が本物と認めたものと寸分違わぬ壺が出てきて、学芸員たちを戸惑わせる「にせもの」というエピソード。スキャニングによって形をまねるだけでなく、割れ方まで同じにできる技術が現実のものとなったら、世界は大混乱に陥りそうだ。
ここで健が、「見分けがつかないなら、どっちも本物だってことにすれば」と口を滑らせ、学芸員たちがそろって目をむく描写に、見た目が同等に美しいならどちらも価値があるとは言い切れない美術品の奥深さが浮かぶ。「笑顔の写真」と「笑顔のゆくえ(承前)」というエピソードでは、満面の笑顔が感動を呼んだ子供たちの写真には、撮った写真家によってトリミングされた部分があって、評価を喜ぶ一方で、作為への罪悪感を写真家に抱かせている。たとえ事実を切り取っていても、それが全てではない写真という表現の難しさを感じ取れる。
美をテーマにして連なるこれらの短編群は、SFとしては、ネットを漂う〈はぐれAI〉を追い詰める展開や、貴重な薬効を持った花を蘇らせる可能性を追い求める展開から、テクノロジーがもたらす未来のビジョンが見て取れる。一方で、贋作組織との戦いがあり、暗躍する謎の人物の正体に迫るサスペンスとしての要素も、『不見の月』と『歓喜の歌』の2冊を貫いている。健が引きずっている過去のできごとと深く関わるクライマックスでの大どんでん返しに、これはやられたと拍手を送りたくなるだろう。
ベートーベンの〈歓喜の歌〉に包まれ迎える、大団円としかいいようがない終幕を経てもなお残る美の価値とは、そしてテクノロジーの可能性とは何かといった疑問が、もっと読みたいと気持ちを煽る。それならと菅浩江には応えて欲しいところだが、可能性はどれくらいあるのだろう。
■タニグチリウイチ
愛知県生まれ、書評家・ライター。ライトノベルを中心に『SFマガジン』『ミステリマガジン』で書評を執筆、本の雑誌社『おすすめ文庫王国』でもライトノベルのベスト10を紹介。文庫解説では越谷オサム『いとみち』3部作をすべて担当。小学館の『漫画家本』シリーズに細野不二彦、一ノ関圭、小山ゆうらの作品評を執筆。2019年3月まで勤務していた新聞社ではアニメやゲームの記事を良く手がけ、退職後もアニメや映画の監督インタビュー、エンタメ系イベントのリポートなどを各所に執筆。
■書籍情報
『歓喜の歌 博物館惑星III』
著者:菅浩江
イラスト:十日町たけひろ
出版社:早川書房
価格:本体2,000円+税
Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4152099607