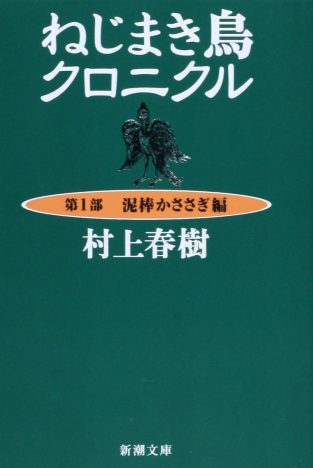村上春樹『一人称単数』はフェミニズム的な観点からの自己批判だ 「僕/ぼく」や「私」を強く意識することの意味

村上春樹の新作『一人称単数』には、8つの短編が並んでいる。短歌をつくる「彼女」との些細な思い出を描いた「石のまくら」、かつてチャーリー・パーカーの架空のレコードについての音楽評論を書いた「僕」がニューヨークでそのレコードを発見してしまう「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」、小説家の「僕」によるヤクルト・スワローズをめぐる回想の「ヤクルト・スワローズ詩集」、人の言葉を話す猿とのやりとりを描いた「品川猿の告白」(『東京奇譚集』に収録された「品川猿」のスピンオフ的な作品と言える)などである。
結論をさきに言うと、『一人称単数』は、村上春樹によるフェミニズム的な観点からの村上春樹批判である。
本短編集の特徴は、書き下ろしの「一人称単数」がそのまま短編集のタイトルになっていることにも示されるように、すべての短編が「僕/ぼく」や「私」といった「一人称単数」の語り手であることだ。もっとも、村上作品において一人称の語り手であることは珍しくないので、厳密に言えば、「本短編集の特徴は一人称単数の語り手であることを強く意識させること」となろう。加えて、村上自身の体験が織り込まれているように読めることを特徴と挙げる向きもある。
一人称であることを強く意識させることとは、「私」が「私」であることを、「僕」が「僕」であることを、強く意識させることだ。もう少し言えば、「私」や「僕」は、他の誰でもなく、「私」であり「僕」である、ということ。
では、「私」とはなにか。さしあたり、「私」とは記憶や経験の連続性だと言っておこう。昨日の「私」と今日の「私」の同一だと思えるのは、これまでの記憶や経験が連続していると思えるからだ。この記憶の連続性が「私」である。ここまで考えたとき、『一人称単数』のとくに前半部、やけに「思い出せない」ことが多いことに気づく。
ここで語ろうとしているのは、一人の女性のことだ。とはいえ、彼女についての知識を、僕はまったくと言っていいくらい持ち合わせていない。名前だって顔だって思い出せない。(「石のまくら」)
十八歳のときに経験した奇妙な出来事について、ぼくはある年下の友人に語っている。どうしてそんな話をすることになったのか、経緯はよく思い出せない。(「クリーム」)
学生時代に自分がそんな文章を書いたことなんて、長いあいだすっかり忘れてしまった。(「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」)
一人の女の子のことを――かつて少女であった一人の女性のことを――今でもよく覚えている。でも彼女の名前は知らない。もちろん今どこで何をしているかも知らない。(「ウィズ・ザ・ビートルズ With The Beatles」)
本短編集の語り手は、とても都合よく記憶を語る。本短編集の語り手は、覚えたいことは覚え、忘れたいことは忘れる。作中人物たちは語り手によって、都合よく覚えられ都合よく忘れてられていく。例えば、「石のまくらに」の「僕」は、女性の「無防備で柔らかな肉体」は覚えているくせに、名前や顔はろくに覚えちゃいない。
そうやって都合のよい人物像が「私」によって好き勝手に作られ、「私」の同一性を保証するためであるかのように語られていく。しかもそれは、男性の語り手によって男性中心的におこなわれていくので、必然、女性蔑視的な色合いがにじむ(実際、女性蔑視的な危うい表現がなかば意図的に登場する)。本短編集に限らず、村上春樹作品が長年指摘されているジェンダーの問題だ。