村上春樹の小説は『ねじまき鳥クロニクル』以降に様相を変えたーーキャリア最重要作を再読する
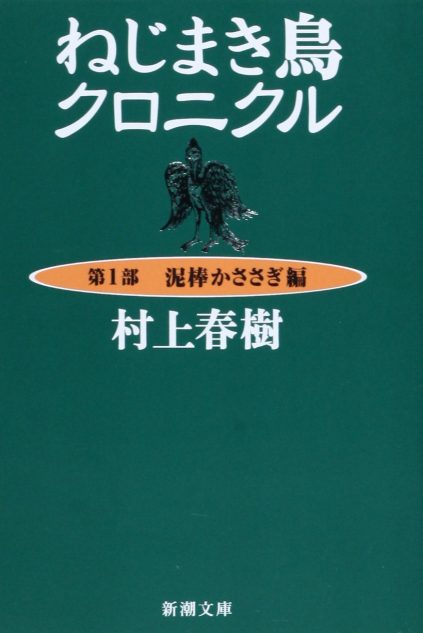
村上春樹の代表作の一つであり、朝日新聞が実施した「識者が選ぶ平成時代に刊行された本のベスト30位」で10位となった小説を原作にした舞台『ねじまき鳥クロニクル』の東京公演(東京芸術劇場プレイハウス)が2月11日からはじまった。重層的な物語構造を持つ原作をどのように舞台化するのか、もっとわかりやすく言うと、あんなに長くてやややこしい話をどうまとめるのか?という興味を持って観劇したが、結論から言うと、とてつもなく素晴らしかった。『ねじまき鳥クロニクル』のエッセンス(本質)を上手く抽出し、象徴的なフレーズを効果的にちりばめながら、コンテンポラリーダンス、音楽、そして、多様な肉体性をたたえた役者陣のパフォーマンスによって再構築したステージは、舞台芸術における最良の表現と言っていいだろう。
特に印象的だったのは、全編に漂っていた不穏な雰囲気、そして、まるで優れた絵画を見たときのような、圧倒的な構築美だ。
演出・振付・美術を手がけるのは、イスラエル出身のインバル・ピント。日本では2013年に上演されたミュージカル『100万回生きたねこ』(2013年は森山未來、満島ひかり)がよく知られている。さらに上演台本・演出として、「マームとジプシー」の藤田貴大が参加。解釈や答えを安易に導くのではなく、難解さ、不気味さ、恐ろしさを美しく洗練された言葉で綴った日本語のセリフは、藤田の技量がなければあり得なかった。音楽はNHK大河ドラマ『いだてん』の劇伴も記憶に新しい大友良英。アジア、日本を中心にした民族性を色濃く反映した楽曲を大友、イトケン、江川良子が生演奏し、人間の暗部、歴史の深みを投影した脚本の言葉、あまりにも豊かな役者の身体性をしっかりと際立たせていた。
主人公の岡田トオルを演じた渡辺大知、成河をはじめ、残酷なまでのピュアネスを感じさせた門脇麦(笠原メイ役)、本作における暴力性を象徴する大貫勇(綿谷ノボル役)、驚異的な長台詞を高い身体能力とともに描き出した吹越満(間宮中尉役)など役者陣のパフォーマンスも見どころたっぷり。劇場に足を運ぶ方は大いに期待してほしい。
ここでは改めて小説『ねじまき鳥クロニクル』について考察したいと思う。『ねじまき鳥クロニクル』は、1992年から1993年かけて『新潮』に掲載され、1995年に刊行された村上春樹の8作目の長編小説。昭和の終わりごろに発表された『ノルウェイの森』(1987年)が上下巻合わせて400万部を超えるベストセラーとなり、一躍時の人となった村上は、ブリンストン大学の客員教授として招かれたことを契機に、狂騒から逃れるように渡米した。日本から遠く離れ、集中して取り組んだのが、それまでの作品のなかで最も長い『ねじまき鳥クロニクル』だったのだ。
『ねじまき鳥クロニクル』は、仕事を辞め、主夫としての日常を送っている“僕”(岡田亨)、雑誌編集者の妻“クミコ”(岡田久美子)の関係を中心にはじまる。どこにでもあるような小さな問題を抱えながらも、無事に日々を過ごしていた二人だが、飼い猫がいなくなってことで、少しずつ亀裂が生まれる。猫を探していた僕はある日、クミコが突然いなくなったことに気づく。やがて、クミコの失踪には、彼女の兄である綿谷ノボルが関与していることがわかるーーというのが、この作品のあらすじだ。
村上春樹が結末を決めずに長編を書き始めてるのは良く知られた話だが、物語自体が自由意志を持って動いているような独特のダイナミズムは、この作品から始まったと言っていいだろう。
『ねじまき鳥クロニクル』の豊かな物語性を象徴しているのが、“井戸の底に降りる”というモチーフだ。主人公の“僕”は、妻の失踪により、それまで当たり前に存在していた日常を突如として失う。今日の幸せが明日も続くことは限らないという、当たり前の事実であり、途轍もない不条理を体験した“僕”は、近所に住む女子高校生・笠谷メイに教わった井戸の底に降り、自分自身の深い自我の底に潜り込んでいく。それはやがて別の世界につながり、出口を見つける大きなきっかけになるのだ。村上自身は“壁抜け”という言葉を使っているが、井戸をモチーフにしたブレイクスルーが、彼の小説の世界、物語の構造を大きく広げたことはまちがいない。
主人公が非現実と現実を行き来するような構図は、この後、村上春樹作品の大きな特徴となる。このことについて彼自身は、「非現実的な世界と現実的な世界との境目がはっきりしているようには、僕自身思えない。だから、いろいろな状況で、ふたつの世界は渾然となるのです。異界というものは、現実の世界の間近にある、と日本では捉えられているのではないでしょうか。向こう側へ行こうと決めたら、行動に移すのはさほど難しいことではない」(雑誌『WIRED』日本版VOL.33/『ニューヨーカー』の文芸編集者デボラ・トゥリースマンのインタビューより)と語っている。このコメントからは、異世界と現実の境界線が曖昧な日本の文化的な風土からの影響が感じられる。レイモンド・カーヴァー、スコット・フィッツジェラルドなどのアメリカ文学に強く影響されていた村上だが、90年代半ばからは日本的な物語への興味が増したのではないだろうか。その最大の要因はおそらく、日本を離れ、この国の在り方を俯瞰したことだろう。























