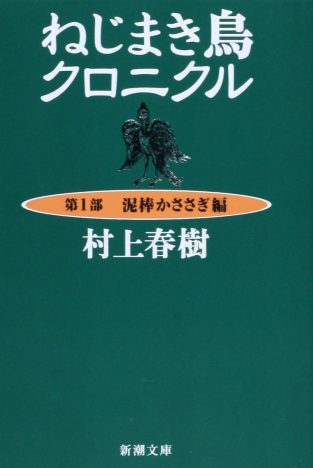村上春樹は“父親の存在”とどう向き合ってきたのか? 新刊エッセイ『猫を棄てる』を読んで

村上春樹が初めて父親の戦争体験、自身のルーツについて書いた『猫を棄てる 父親について語るとき』が大きな話題を集めている。昨年、月刊『文藝春秋』6月号で発表された本作。書籍化に際し、台湾のイラストレーターによる13点の叙情豊かな挿絵が添えられている。本稿では、村上春樹作品における“父親の存在”について考察する。
村上春樹は本作『猫を棄てる 父親について語るとき』のあとがきに次のような言葉を寄せている。/p>
亡くなった父親のことはいつか、まとまったかたちで文章にしなくてはならないと、前々から思ってはいたのだが、なかなか取りかかれないまま歳月が過ぎていった。身内のことを書くというのは(少なくとも僕にとっては)けっこう気が重いことだったし、どんなところからどんな風に書き始めれば良いのか、それがうまくつかめなかったからだ。
村上の父親が90歳で亡くなったのは、2008年のこと。その翌年のエルサレム賞の受賞スピーチ「壁と卵」で彼は、父親のことを話した。毎朝、朝食の前に仏壇の前で長い祈りを捧げているのを見て、村上が「なぜそんなことをするのか」と尋ねる。すると父親は「あの戦争で亡くなった人のために祈っているのだ」と教えてくれた……というのが、その内容だ。このエピソードは、彼の小説の読者に強いインパクトを与えた。それまで村上は、ほとんどと言っていいほど、父親について語ってこなかったからだ。
デビュー作『風の歌を聴け』(1979年)から『国境の南、太陽の西』(1992年)までの村上春樹の作品の特徴の一つが“父親の不在”であることは、疑う余地がないだろう。ギリシャ悲劇の『オイディプス王』などに起原を持つ父と息子の物語(その中心は、子が父を超えようとする“父殺し”のストーリーだ)はーー『スターウォーズ』から『鬼滅の刃』までーー今に至るまで、延々と繰り返されている。それは小説、映画、マンガをはじめ、物語作りのもっとも根本的な構造なのだ。
しかし村上は、特に初期の作品において、父親的な存在を完全に消し去っていた。その代わりに採用されていたのが、「“邪悪なもの”の侵入を、社会的な役割から離れ、個として生きようとする人間が防ぐ」という話型だ。『羊をめぐる冒険』(1982年)『ダンス・ダンス・ダンス』(1988年)『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985年)『ノルウェイの森』(1987年)といった初期の代表作の主人公は家族を持たず、大きな企業に属することもなく、個人的な生業で日々を過ごしている。そこに”邪悪なもの“が突如として現れ、主人公は(”やれやれ“と呟きながら)不可避的に物事に引き込まれていくというのが、その定型だ。
この話法を取り入れることによって村上春樹の小説は、それまでの日本文学とはまったく異なる文脈を作り上げた。父親の不在、地縁的な描写の欠如は当時、賛否両論を巻き起こしたが、その作風は若い世代を中心に大きな共感を集めた。彼の作品が世界的な評価を獲得していることは、その物語の“型”に時代や地域を超える普遍性が含まれていたことを証明している。
村上作品における“父親の不在”に変化が現れたのは、『ねじまき鳥クロニクル』(1994年)だった。この作品が小説家の分岐点であったことは以前にも書いたが(村上春樹の小説は『ねじまき鳥クロニクル』以降に様相を変えたーーキャリア最重要作を再読する)、その根拠の一つが、実際に起きた悲惨な出来事である“ノモンハン事件”についての描写。作中では主要な登場人物である間宮中尉の独白として語られるが、このエピソードが村上の父親の実体験に裏打ちされているのは間違いないだろう。
『ねじまき鳥クロニクル』は“飼っていた猫が失踪する”という話から物語が展開されるが、『猫を棄てる』もまた、父親と一緒に猫を棄てる場面から始まる。「父と一緒に海岸に猫を棄てに行ったときのことをふと思い出して、そこから書き出したら、文章は思いのほかすらすらと自然に出てきた。」という村上自身の記述の通り、この思い出は彼の記憶に強く刻まれていたようだ。