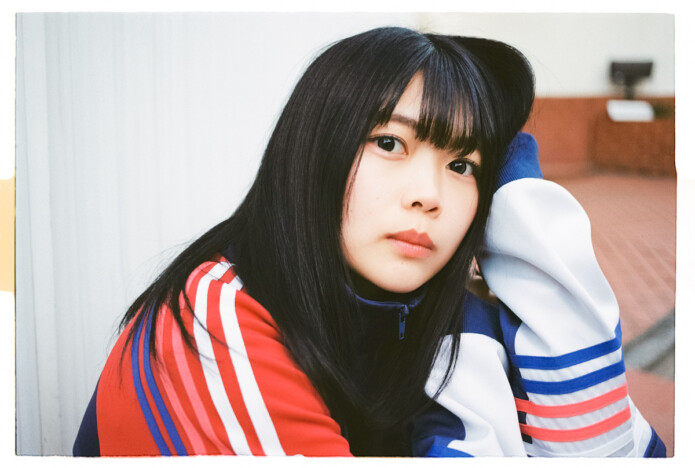Mr.Children『miss you』評:自問自答の末に表出した“自己への嫌悪” 桜井和寿と鏡のメタファーを考える
桜井和寿は特に、藤原基央と五十嵐隆と共有している終わりなき自問自答への傾向を、「鏡」「反映」というモチーフで表出してきた。〈窓に反射する(うつる)哀れな自分(おとこ)〉へ〈Mr.Myself〉と呼びかける「innocent world」、〈甘えていた鏡の中の男〉に復讐を誓う「優しい歌」、破局寸前の恋人の〈力のない瞳〉に〈僕という過去〉の反映を見る「渇いたkiss」。「優しい歌」には、そのまま〈出口の無い自問自答〉というリリックも登場する。「Mirror」(1996年)という楽曲名、『REFLECTION』(2015年)というアルバム名はもちろん「鏡」「反映」を意味している。
特筆すべきは「Mirror」で、この曲は〈あなたが誰で何の為に生きてるか〉の謎が解けるよう「鏡」となりたいと願う歌になっていて、「あなた」という他者も自問自答を繰り返す主体として想定されている。アンプラグド風のアレンジと、シンプルなシャッフルリズムの上で〈ヒットの兆しもない〉ラブソングと自己言及する「Mirror」において、「鏡」は身近な他者を救うものとして肯定的に描かれるのだ。桜井和寿の歌世界では、自分も他者も自問自答を反復する主体であり、自分と他者の関係は「鏡」の機能を有している。ただ、自分自身が覗く「鏡」は信用ならないが、他者(=あなた、きみ)という「鏡」は自分の本当の姿を映してくれる。その差異によって、他者は貴重なものとなる。
上記で素描した「鏡」の構造は、スターのイメージをオーディエンスも作家自身も仮構してしまう文化産業のアナロジーになっている。鏡の前で自問自答を繰り返す作家は、他者の視線に晒されることで、自己のイメージを確保できる。あなたの鏡になりたいと歌う作家に、オーディエンスは安心して自己の鏡を投影する。作家は鏡としてのオーディエンスを欲し、オーディエンスは鏡としての作家を欲する。こうしてMr.Childrenとオーディエンスは、それぞれが鏡を向け合う、自問自答の共同体となる(※3)。
作家と鑑賞者の共犯による鏡像の乱反射、同質的に自問自答する主体の氾濫が、Mr.Childrenの周囲には付きまとう。作家自身とオーディエンスそれぞれに浮かび上がる「自らの姿」への執着を描いてきた桜井和寿の表現を鑑みれば、鏡像的な共同体の構造は必然だったであろう。
そんな桜井が、ここにきて「鏡」に映る自分への嫌悪を歌うようになったのはどういうわけだろう。2020年発表の「君と重ねたモノローグ」では、ドラムが消えて歌が強調される場面で〈鏡に映った自分の嫌なとこばかりが見えるよ〉と語りかけていた。さらに、今作収録の「LOST」。ディストーションエフェクトのかけられた桜井の声が告げる。〈鏡なんて無くて良いや/こんな自分を もう見たくない〉。ここでも、アコースティックギターとシンセベースとパーカッションが消えて、ボーカルの存在が前に出ている。「鏡」の前に立つ自分への嫌悪は、アレンジによって強調されている。
『miss you』における表現主体は、「鏡」の嫌悪者として仮構される。嫌悪者の姿は、例えば「Party is over」に反映される。コーラスの二周目、一周目のコード進行に対して微妙な変化をつけながら、〈もう席を立って帰ろう/でも何処へ向かえばいい?〉とファルセット混じりに歌うパート。「鏡」としてのスターから離れるにももはや行き場所はないという呟きは、「Fifty's map ~おとなの地図」において、〈どこにも逃げれない/そう過去にも未来にも〉と、6/8拍子のドラムだけを頼りに歌い上げる場面と呼応する。そして、アシッドジャズ風の演奏に乗せてMummy-Dにも似たフロウで畳みかける「アート=神の見えざる手」。社会風刺のリリックはMr.Childrenのディスコグラフィにもたびたび登場したが、この曲の特異性は、自らとオーディエンスとの関係の批判を表す点にある。性器に傷をつけることが契約の代わりになる、殴ったり蹴ったりすることが愛の代わりになる。共依存の描写が、作家とオーディエンスの関係の似姿になる。
大衆を安い刺激で釣って
国家権力に歯向かってみせて
半端もんの代弁者になる時
僕のアートは完成致します
〈半端もんの代弁者〉が、作家の自己規定となり、鏡像関係への諧謔を表す。鏡への嫌悪は、自問自答の鏡だけなく、他者という「鏡」にも向けられている。
「アート=神の見えざる手」において桜井は、いわゆる脚韻を明確には踏まない。だが、韻律を全く感じさせないわけではない。語尾で「て」を連射するところとか、「とか」を三度繰り返す箇所とか、同じ音の連続がリズムの小気味よさを形成している。「代弁」と「完成」は母音がそれぞれ「a/i/e/n」と「a/n/e/i」で構成要素が同じだ。はっきりとした韻踏みとは異なる、ほのかな韻律の感触が生まれている。
彼女もトラウマを抱えていました
面倒くさいから割愛しますが
どこか常識で測れない
僕達のこの恋をご理解下さい
上記のパートでは、「面倒くさい」「割愛」「測れない」「ご理解」「下さい」の「ai」が韻律を為している。素早く心地よい発話の応酬の中で、〈面倒くさいから割愛しますが〉と、「彼女」という他者への蔑視を発露させる。Mr.Childrenが自らのシグネチャーであるコード進行とボーカルメロディの妙を封印したとき、リズム要素の活用は、他者への無関心と敵意を滑り込ませる手段となるのだ。
後半の「黄昏と積み木」「deja-vu」「おはよう」という三曲の穏やかなラブソングは、鏡像関係を周到に避けている。〈金曜日の仕事が思いがけず早く済〉んだときに〈君はまだ仕事してる〉(「黄昏と積み木」)し、〈僕と君の生活〉は〈少しずつ重なる〉(「おはよう」)が、一致はしない。〈君の生真面目さとそれ故の危うさ〉は〈悟られないようにしてた僕の一面みたい〉(「deja-vu」)だが、全面的ではない。鏡像ではない他者との関係を肯定的に描くことで、本作は閉じられる。
しかし。そんな「鏡」の物語が、なんだというのだろう? 鏡への執着と憎悪など、よくある俗流精神分析に過ぎないのではないか? 鏡に対する嫌悪表現自体が、ソーシャルメディアの鏡像関係に疲弊した時代の映し鏡ではないのか? そもそも、今読まれてきた文章が、『miss you』という作品の忠実な「鏡」になっていないか? それをどう説明すればいい? こうした疑問は、本論では一切解消されていないし、「鏡」を求める心性が鑑賞者から消えるわけでもない。『miss you』に対して、長らくのファンは「鏡」への嫌悪を受けいれず、Mr.Childrenと関係ない生活を送ってきた者は一切興味を示さないかもしれない。彼らの鏡像性に微妙な愛憎を抱き続けてきた(私を含む)少数のリスナーだけが愛着を持つという意味では、商業的には失敗かもしれない。
私にできるのは、本作の密室的な響きと、出口なしのリリックから感受したものを、できる限り詳細に語ることだけだ。鏡から逃げられない状況を歌うのに、アンサンブルと音響作用への注力を高めるMr.Childrenは、とても魅力的だ。お気に入りのシャツにコーヒーをこぼした。眠れない。やり直す時間はない。未来に何も残せない。失望を能うかぎり丁寧に掬い上げる時にだけ、降りてくる恩寵がある。救いのなさが、そのまま救いとなる。そのとき、別の形式に変換された徒労感と閉塞感の似姿を、「鏡」とは誰にも呼ばせない。
※1 BUMP OF CHICKENとsyrup16gとの間にも親交があり、syrup16gの「水色の風」(2002年)には藤原基央がコーラスで参加している。
※2 ふぢのやまい「「しるし」を「かぞえる」」2021,『痙攣 vol.2 もう一度ユートピアを 国内音楽特集』収録
※3 宇野惟正とレジーの共著『日本代表とMr.Children』(ソル・メディア,2018)は、サッカー日本代表とMr.Childrenがそれぞれの「鏡」となっていく様を、時系列順に詳細に描いている。