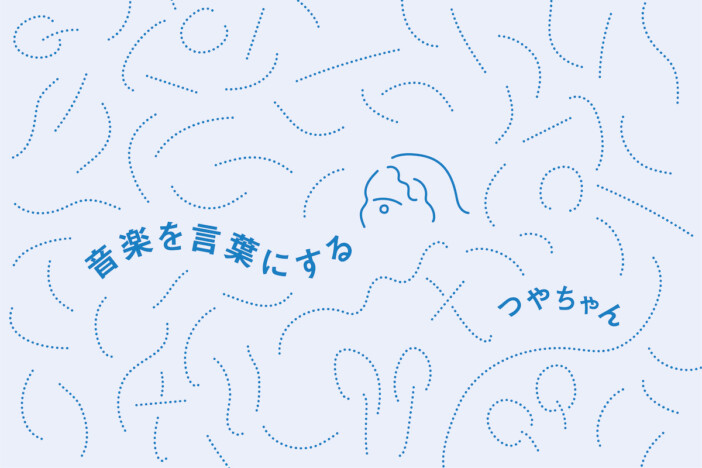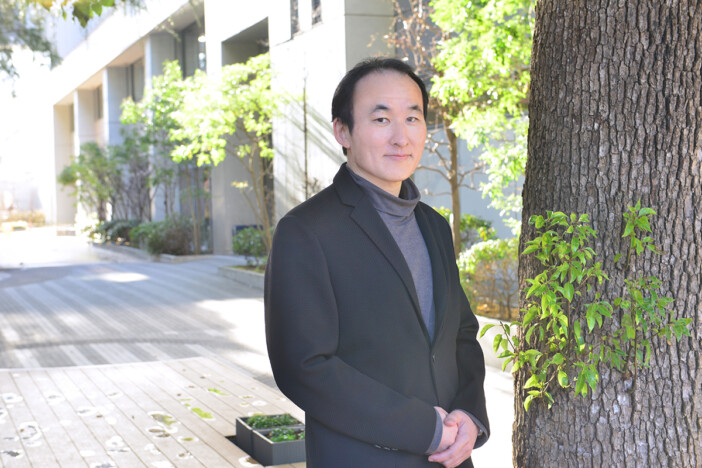【連載】つやちゃん「音楽を言葉にする」 第2回:誰に、どのような問いを投げかけるか
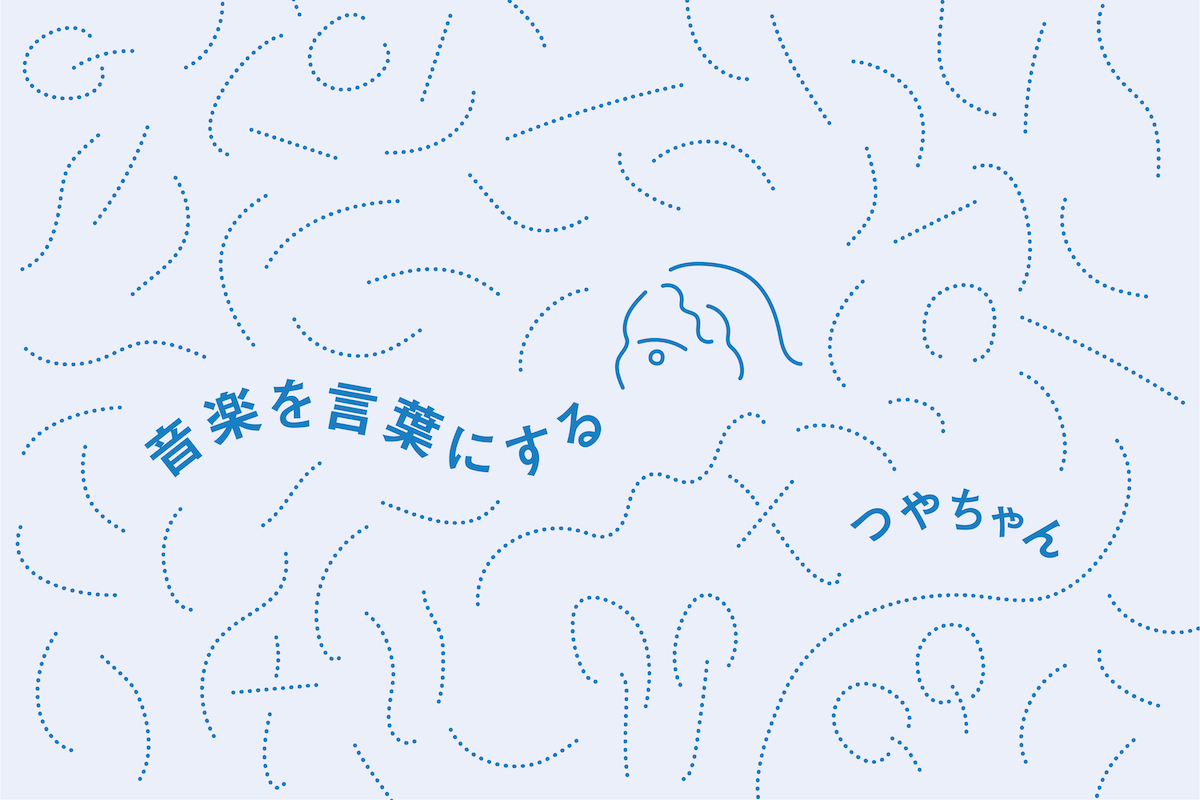
文筆家・つやちゃんが、インターネットやAIが発展してますます複雑化する現代の情報空間において、音楽を中心としたカルチャーについて「書くこと」「語ること」の意義やその技法を伝える新連載「音楽を言葉にする」。
第2回は、音楽を語りはじめる前に必要となる準備と作業について。(編集部)
感情を伝えるためにこそ、構造が必要
前回は、批評的な強度を備えた文章や語りは専門的なスキルによって編み出されるものであり、その内部には思考と感受の痕跡が必ず刻まれている、と述べました。今回は、その痕跡をいかに言葉として立ち上げていくか――つまり、語りはじめる前に必要となる準備と作業について考えていきます。
まず押さえておきたいのは、ここで言う「思考と感受の痕跡」とは、ただ闇雲に唸ったり悩んだりしている気配を残す文章ではない、ということです。現代の読者は、かつてよりもずっと複雑な情報環境の中にいます。SNSやメディア、サブスク、無数のアルゴリズムに囲まれ、日々あらゆる言葉にさらされている。そうした中で、もはや私たちには、「言いたいことが何かよく分からないけれど、とにかく悩みながら書いているような語り」に付き合っている余裕は、あまり残されていません。正確に言えば、そのような蛇行した語りも戦略や技法のひとつとしてあるのですが、アプローチとしては変化球に類するので一旦ここでは置いておきます。むしろ、そういった時代における思考と感受の痕跡とは、思考や感受を丁寧に通過したことが構造として、あるいは文体として静かに滲み出ているような文章や語りのことです。つまり、迷ったり悩んだりしたプロセスそのものではなく、そのプロセスを通して何を見出したか――その結果として選ばれた言葉や順序、比喩や距離感の中に、考えと感受の跡が刻まれている状態を指しています。
それは一見すると、シンプルな語りに見えるかもしれません。けれども読み手には、「この人はこれを語るまでにきちんと見て、調べて、感じて、考えてきたんだな」という気配が残る。批評的な強度とは、そういった文章や語りから立ち上がってくるのではないでしょうか。これは、単に文章の技巧の話ではありません。信用や信頼が目に見えにくくなっている時代において、何を信じるかの根拠が語り手の誠実な経験に委ねられているからこそ、そうした痕跡がより強く求められているのでしょう。
たとえば、あるアーティストについて、あるいは作品について書くとします。書きたい/語りたいと思っているあなたの中には、すでに言いたいことがいくつか沸いてきているはずです。「このアーティストは、今の時代の空気を体現している! 社会的閉塞感や孤独をありありと描き出していて、鳥肌が立つくらいに凄い!」「懐かしさと新しさを同時に感じるサウンドだ。なんだか胸がしめつけられるような気持ちになる」「本人の幼少期の体験という個人的なエピソードがモチーフになっているけれど、多くの人に届く普遍性を感じる」等々。もう、今すぐにでもそれを書き殴っていきたい——すばらしい表現に触れた時、そういうエネルギーに駆られることは多々あると思います。前回述べた通り、そのモチベーション自体はとてもすばらしく、何にも代えがたいものです。ただ、そこで一度立ち止まる必要があります。冷静に見て、上の記述は、感想のレベルを出ていません。対象のアーティストや作品を変えても当てはまるような内容ですし、何より、陳腐です。あなた自身も、音楽メディアやSNSなどで今まで散々目にしてきたような記述でしょう。
ただ、ここでいきなり「単なる感想を脱して強度高いことを言うためにはどんな言葉を選べばいいのか……」などと考えるのは、手順をショートカットしすぎです。ここで必要になるのは、まず、他者との接続をいかに作るかという工夫だからです。日常のコミュニケーションにおいても、知らない人が自分のことだけを饒舌に語りはじめても、誰も聞く耳を持たないでしょう。それと同様です。オタク的語りが閉じているのは、そこに他者との接続点が見つけづらいためです。
重要なのは、「共有地がないと人は感情の橋を架けられない」ということではないでしょうか。共感とは、文字どおり「共に感じること」ですが、それは同じ地面に立てたときに初めて可能になる体験です。主観的な語りだけで書きはじめると、それがどれほど切実であっても、読者はどの地面に立てばその感情を理解できるのかが分かりません。つまり、語り手の内面に読者がジャンプインするための導線がない。それに、逆説的ですが、主観は後に出すからこそ強くなるという現実もあります。主観とは、構造を渡したあとの贈り物になった時、もっとも読者の心に残るものなのです。
これは、感情を捨てろという話ではありません。むしろ逆で、感情を伝えるためにこそ、構造が必要なのです。強度高い語りや文章を綴っていくためには、感情がより豊かに伝わる設計をまず工夫する必要があります。そう考えると、「まずは主観の外へ」というアプローチは、あなたの語りをより遠くまで運ぶための、設計図を描くような行為とも言えるでしょう。
まずはリサーチ、とにかくリサーチ
さて、ではどのようにして、他者との共有地を築いていけばいいのでしょうか。世の中を見渡してみると、その問いに最も近いヒントを持っているのは、いわゆる「マーケティング理論」と呼ばれるフレームワークです。と書いた時点で、なんだか難しい話が始まりそうだと身構える人が多いかもしれません。心配いりません、ここでは専門用語を使わずに説明するので、ひとまずついてきてください。
たとえば、飲料メーカーで、とある飲料水を多くの人に届けたいという状況があったとしましょう。最近売り上げに陰りが見えはじめていますが、あなたは自分でも毎日飲んでいる、大好きなドリンクです。これは、あなたが好きなアーティストや作品に対して抱く「これは本当にすごい! もっと多くの人にこの感動を伝えたい!」という気持ちと、まったく同じです。そんなとき、あなたはこう考えるかもしれません。「このドリンクのサッパリしたのどごしがとても好きだ。だから、汗をかいた後のリフレッシュにぴったりだ、という切り口で宣伝しよう」と。けれども、ここで主観だけを頼りにマーケットへコミュニケーションしていっても、多くの場合はうまくいきません。それは、あなたの個人的な感動が、他者との共有地になっていないからです。
では、どうすれば他者との接続点を見つけられるのでしょうか。まず大切なのは、世の中でその飲料水がどのように受け入れられているのかを知ることです。たとえば、「外でスポーツをしている若者」がよく買っているのか? 「美容意識の高い30代の女性」に支持されているのか? 「コンビニでサッと買っていく忙しいビジネスパーソン」が多いのか? このように、現状の支持されている文脈を探ることで、商品の価値の輪郭が少しずつ明確になっていきます。そして、たとえば自分では「サッパリしたのどごし」が魅力だと思っていたけれど、リサーチを進めていくと、実際に多くの人が評価していたのは「微炭酸のちょうどいい刺激と、飲み終えた後のスーッと抜けるような余韻」というポイントだった——そんな発見があるかもしれません。さらに言えば、近年はこの「余韻の心地よさ」に類似した商品が多く登場していて、競合環境も変化している。だからこそ、今後は単に「余韻」だけではなく、その飲料のみが持つ別の強みをどう打ち出していくかが鍵だ、といった発見も出てくるかもしれません。
このように、主観から出発しつつも、それをいったん棚に上げて、「どのように受け取られているか」という世の中の視点に立ち戻ると、色々なことが見えてきます。これは、飲料水の宣伝だけでなく、音楽や文化について語ること/書くことにおいても同じプロセスです。つまり、そのアーティストや作品が、世の中においてどのように受容され評価されているかを、できるだけ鮮明に捉えられるようリサーチするということです。いきなり書きはじめる前に、まずはリサーチ、とにかくリサーチです。他者との共有地を築き、接続点を持つためには、そこから始めなくては話になりません。ちなみに、世の中での受容や評価が鮮明になった後、書く段階でやることは基本的には二種類しかありません。現状の評価を発展させていくか、ズラすかです。ただ、これについてはまた次回詳しく論じます。今回はまず、リサーチについて考えていきましょう。
リサーチにおいて重要な観点は、シンプルです。できるだけ客観的に調べていくということしかありません。もちろん、語りたいこと/書きたいことのテーマを念頭に置きながら情報を追っていくことになりますが、そこでは、対象が世の中でどのように認知されているかという観点でひたすら捉えていきます。そして、何より大切なのは、情報は山のようにあるけれど、最終的に一言化できるくらいまで圧縮していくということです。どういうことか。これは概念的に論じるよりも、まずは具体例を挙げながら作業していった方が分かりやすいと思うので、実際にやってみましょう。
例として、シンガポール出身でロンドンを拠点に活動するアーティスト・yeule(ユール)がレーベル〈Ninja Tune〉からリリースした4作目のアルバム『Evangelic Girl is a Gun』を挙げます。事例は何でも良いのですが、わたしが過去に執筆した作品評で、今回論じるテーマを説明する題材として分かりやすいからという理由で選びました。yeuleは現行の音楽シーンを考えるうえで重要なアーティストなので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。ただ、ここでは例として挙げているだけなので、知らなくてもかまいません。どういったリサーチをするか、という観点で捉えてください。
考えるべきなのは、yeuleがこれまでの三作のアルバム、ライブやMVなどを含めた表現活動によって、どのように受け止められているか、という世の中の評判・評価です。まずは日本語で書かれたインタビューやレビューをチェックするのは必須でしょう。SNSやリアルの場での口コミもできるだけ見ておく必要があります。さらに、ロンドンを拠点にしている海外アーティストなので、少なくとも英語圏でのインタビューやレビューも押さえておくべきです。最近は翻訳サイトの精度も飛躍的に向上しているので、語学ができなくともニュアンスはつかめるはずです。アーティストによっては情報収集の量が膨大になってしまうため、その全てに目に通すのはなかなか難しいかもしれませんが、できるだけ多く確認しておいた方がよいです。
常に届ける先のペルソナ=人格を描いておく
さて、作品を聴きながらそうやってリサーチを進めていくと、少しずつyeuleというアーティストの輪郭がはっきりしてくるはずです。まず、アルバムによって作風が徐々に変化し、グリッチなエレクトロニックサウンドから、近作ではロックサウンドへと傾倒していること。過去作から一貫して、自傷、依存、喪失といったパーソナルな傷を美学に昇華してきたこと。とりわけ、2022年にリリースした『Glitch Princess』では、自傷行為とテクノロジーを接続させ、「人間とは何か」という問いに向き合っていたこと。また、ジェンダーや身体に対する違和を乗り越え、あえて性別を感じさせない声や、はっきりした身体のかたちを見せないビジュアルを通して、自分自身のあり方を新たに作り直そうとしていること。そして、yeule自身が「ポストヒューマン」「デジタル幽霊」として、現代社会の喪失感をまといながら存在していること——。こういったことは、作品を聴きつつさまざまな記事を読んでいたら、ある程度つかめる情報です。このくらいであれば、すでに前提知識として知っている、という方も多いかもしれません。しかし、これはまだ単なる「情報」でしかありません。誰でも調べれば得られる知識なので、それ自体はあまり大きな価値を持っていません。
ただ、そういった情報を収集していく中で、世の中の人が、yeuleの作品に対してどのようなイメージや感情を抱いているかがなんとなく見えてきます。たとえばライト層は「怖い/分からない」という感想で止まりやすい一方、コア層は「痛みがどう美学として編み直されているか」に反応している——といった具合に、受け取られ方が層によって明確にズレていることも見えてきます。
わたしがリサーチしていくと、具体的には、次のような状況が見えてきました。特に海外では、yeuleの悲しみや依存、孤独といった負の感情が独自のテクスチャでパッケージされ表現として届けられることにより、主に若年層が深い共感を抱いています。また、そういった「自身の身体の解体」や、それを特異なテクスチャで表現するという手法自体が、SOPHIE(ソフィー)以降のハイパーポップ文脈において注目されてきたアプローチであり、yeuleはそういった流れにおいても無視できない存在と認識されていることも分かってきます。(SOPHIEやハイパーポップという語彙が自分には分からない、という声が出てきそうですが、これも心配いりません。インタビューを読んでいると本人の口から、レビューを読んでいるとリスナーが、様々な影響源や類似するアーティスト・作品を語ってくれます。それをまた調べていくことで、輪郭はつかめていけるでしょう。)
また、yeuleのオリジナル性の高いビジュアルは、熱心なファンだけでなく、もう少しライトなリスナーや、存在は知っているがちゃんと作品を聴いたことがないという層にまで支持されていることも分かってきます。どこか可愛さとダークさが共存する美意識は、いまのヴィジュアル・トレンドとも重なり、若いファンの心をつかんでもいるでしょう。さらにもっと層を広げていくと、yeuleのそういった表現に対して「若い層に支持されているのは知っているが、それがなぜかはよく分かっていない」「そもそもちょっとビジュアルが怖い、何がしたいのかよく分からない」と感じている層がいることも分かってきます。
今わたしは、「yeuleのコアなファン」から「なんとなくyeuleも聴いている音楽好きのリスナー」、さらに「楽曲は深く知らないがビジュアル面に関心を抱いている人たち」、そして「多く支持されているのは知っているがよく分かっていない層」といった形で、複層的なターゲットでyeuleの認知イメージを並べていきました。リサーチ作業においては、情報を収集していく中で、そういった形でyeuleのアーティスト像を立体的に捉えていく必要があります。なぜなら、アルバム評を書いていくにあたって、どういった問いを立て、どの層に向けて届けていくかが最初の重要なポイントになってくるからです。アーティスト論にしろ作品論にしろ、「誰に向けてどんな問いを投げるか」は最初の関門であり、最も肝となるところです。
先ほどの飲料水の例になぞらえると、それは、ターゲットをどこに設定するか——外でスポーツをしている若者なのか、美容意識の高い30代の女性なのか、コンビニでサッと買っていく忙しいビジネスパーソンなのか——その層に向けてどんな一言目を投げるのか、という部分にあたります。話すこと/書くことにおいて、これほど大事なポイントはありません。ビジネスにおけるプレゼンでも、研究論文でも、何においても同じです。とにかく「誰に向けてどんな問いを立てるのか」という観点が弱いと、論がスケールしていかず、説得力を欠いてしまいます。
実際、ターゲットと問いをどのように設定するかは、さまざまな条件によって左右されます。先のyeuleの作品評の場合、音楽専門メディア〈TURN〉から執筆依頼があり、メールには「新作リリースにあたってyeuleを大きくフィーチャーしたい」という一文が添えられていました。さらに、前作までの流れを受けて本人を取り巻く熱狂がいっそう高まりつつあることを踏まえ、これはアーティストにとっても、これまで以上に広い層へと届くべき局面にあると感じました。同時に、音楽ジャーナリストとして最新作を聴いたとき、この表現はより多くの人と分かち合うべき作品だという確信もありました。というのも、本作は、現在の社会に横たわるさまざまな問題について思考するうえでも、十分に意義ある題材になり得ると感じたからです。
この時点でわたしは、「コアなリスナー」や「なんとなく知っている音楽好き」も視野に入れながら、主な読者としては「気になっているが、まだよく分かっていない層」に届けたいと設定しています。つまり、yeuleに興味はあるけれど入口が見つからない人たちに向けて、橋を架けるような文章にしたい、というのが狙いです。さらに、せっかく書くなら、短期的な紹介にとどまらず、長いスパンで読み返されるものにしたいとも思いました。音楽の話でありながら、読者がそこから社会や時代についても考え直せるような射程を持たせたい。というのも、yeuleの作品には、そのような論の展開に耐えうる強度が確かに備わっているからです。現実的に言えば、優れたアーティストや優れた作品ほど、音楽論であると同時に社会論としても成立します。音楽は単なる音ではなく、その時代の身体感覚や欲望、不安を映し出すものでもある。だからこそ、優れた音楽作品はまた、優れた批評を呼び起こします。ゆえに、「これは重要だ」「これは後に残る」と直感が働いた作品ほど、言葉にして記録しておくべきです。批評の強度を押し上げる最大の燃料は、ほかでもない作品そのものの力にあるからです。
ただ、基本的には、外的要因による制約がない限り、ターゲットの設定は自由です。そこにひとつの正解はありません。ブレイクの兆しが見えてきたタイミングほど、逆にコアなリスナーに向けて粒度の細かいマニアックな論を出した方がよい、というケースも多々あります。視聴者や読者をどこに置くかというのは、どちらかというと、論をきちんと届けて意義あるものにするために必要なステップと捉えた方がよいかもしれません。また、書き手によっては常に同じターゲットに向けて書き続けるという信念を持っている人もいるでしょう。特定の音楽ジャンルの愛好家に向けてジャンルを固定して専門誌で語り、執筆を続けている一部のライターは、そういった想いのもと活動している方もいます。しかし、そうだとしても、メディアによって多少ターゲットは変化しますし、基本的には常に届ける先のペルソナ=人格を描いておくべきです。
問いとは他者との共有地を築くためのもの
さて、視聴者や読者のイメージが定まったなら、次に考えるべきは、その人たちに向けてどのような問いを置くかです。再び、先ほどの飲料水の例に立ち戻ってみましょう。たとえばターゲットとして、「コンビニでサッと買っていく忙しいビジネスパーソン」を設定したとします。そこでさまざまな声を拾い、ヒアリングを重ねながらリサーチしていくと、「微炭酸のちょうどいい刺激と、飲み終えた後のスーッと抜けるような余韻」を人々がなぜ求めているのか、その背景が少しずつ見えてくるはずです。
つまり彼らが欲していたのは、単なる爽快感ではなく、「エナジードリンクほど強すぎず、コーヒーほど胃に負担がかからない。それでもボーッとはしたくない」という、ちょうどよい軽い覚醒感だったのかもしれない。「カフェインより軽い刺激が、いまの気分にぴたりと合っていた」という隠れた本音が浮かび上がってくるのです。そのとき、コミュニケーションとして「わたしたちはなぜ、強すぎない覚醒を求めているのか?」という問いを据えてみる。そうすることで、プロダクトやプロモーションは単なる特徴の提示を超え、読み手や消費者の思考を促すものへと変わっていきます。重要なのは、ターゲットの行動の背後にある、本人さえまだ言葉にできていない無意識の本音に向き合うことです。そこまで掘り下げてはじめて、「他者との共有地を築く」ことが可能になります。
同様に、yeuleについても考えてみましょう。「若い層に支持されているのは知っているが、それがなぜなのかよく分かっていない」「そもそもちょっとビジュアルが怖い、何がしたいのかよく分からない」と感じている広い層に対して、どのような問いを投げかけることで、意義あるコミュニケーションを生成していけるのでしょうか。これにはさまざまなアプローチが考えられますし、書き手としての感性が問われるところです。なかなか抽象化しノウハウとして伝えることは難しいですが、大切なのは、まずあなた自身がそのターゲットになりきることではないでしょうか。わたしはもう、すでに作品も多く聴いてたくさんのリサーチをしてyeuleのことを知ってしまっています。けれども、そこですべての情報を一旦忘れ、今から届けたいと思っている人をイメージして語りかけてみる。そういった想像力が、問いの設定には欠かせません。
そうした結果、yeuleという固有名詞から入るよりも、このアーティストがテーマとして据えてきた「ポストヒューマン」という概念がいまどのように変化し、それにyeuleがどのように対処しようとしているのか——といった観点で間口を設けるのが良いのではないかと考えました。せっかくなので、ここで「問いの設定」が実際にどのように文章の入口として機能するのか、私が書いた原稿の冒頭部分を抜粋してみます。ここでは、いきなり結論を語るのではなく、まず読者と共有できる地面をつくるために、どのような問いが置かれているのかを意識しながら読んでください。
〈そして身体が残った――ユールのセクシーさをめぐる記録〉
2025年の現在、「ポストヒューマン的」とは、もはやある種のテンプレートである。身体の変容、アイデンティティの可塑性、テクノロジーとの共生――言うまでもなくその先駆は故ソフィーであり、機械音と声を同化させ肉体を仮想的にデザインし直すことで、アイデンティティの枠組みを解体した。アルカはさらにその先へ進み、身体の変容可能性そのものをテーマに、多重人格的なサウンドスケープを展開してきた。先人たちが切り拓いたのは、「変わることでしか生きられない身体」の物語だ。
時は経ち2025年、Z世代のアーティストたちは、このポストヒューマン的感覚をそれぞれの方法で引き継いでいる。ジェーン・リムーバーは壊れた記憶や曖昧な感情の断片を、刺激的で不安定な音のなかにアーカイヴしていく。2hollisは、リズムの歪みや拍のズレ、破壊されたままのメロディのループなど、構造それ自体を「途中で壊れる」ことを前提に設計する。lilbesh ramkoは、つながりたい欲望と届かない困難の間でひたすら声を枯らす。「変われること」への欲望よりも、「変われないまま、世界の不確かさに耐えている」わたし。ポストヒューマン的身体性を受けつつも、世界のシステムの側が崩れているという感覚を表現している若手アーティストたち。音楽は今、現代の不安定なリアリティにおける存在の方法として私たちを救っている。
10年前、私たちは「身体は変えられる/性別も存在の枠組みも再設計可能である」という解放の夢に魅了されていた。それは、バイオテクノロジーや機械との共生であり、SNSやゲームを通じた自己の再構成・再編集であり、何よりクィアな存在の肯定として輝いていたはずだ。けれども2025年の今、私たちはその夢が必ずしも自由や幸福を保証してくれないことに気づいている。変われるという幻想の過剰消費によって、自由な変身は「変わらなければ居場所がない」というプレッシャーに変質してしまった。どれだけテクノロジーが進んでも、この世から差別や暴力はなくならないことが分かった。それにAIの進化は、私たちの創造性や人間らしさを写し取るようになってしまった。画像、音楽、声、言葉……それらはもう人間でなくても作れてしまうがゆえに、人間らしさへの再接続の欲望が改めて高まっている。結果的に、「変わる」ことではなく、「変われない」ことをどう生きるかという問いがリアリティを帯びてきたのだ。言い換えるなら、ポストヒューマン的な夢をくぐり抜けたあとに、それでも“この身体”で生き続けるという選択が、今もっとも切実なテーマになったのである。
原稿は、この導入のあと、「そういった文脈のなかで、ユールの4作目となるアルバム『Evangelic Girl is a Gun』もまた、新たな境地へと足を踏み入れている」という一文を経て、作品評へと入っていきます。前述の引用は少し硬い文体に感じられるかもしれませんが、これは掲載メディアのトーンに合わせた結果でもあり、こうした書き方が唯一の正解というわけではありません。大切なのは、難しい言葉を使うことではなく、「読者と共有できる問いをどこに置くか」という設計です。また、短いレビューにおいては、そもそもこんなにも問いを長々と語ることは不可能です。問いを短くした、あるいは省略した書き方については、連載が進むにつれてまた別の機会に紹介するので、ここではまずベーシックな書き方を説明しています。
ここで設定されている問いは、「いま、ポストヒューマンという概念は音楽においてどのように解釈され、どのように表現されているのか」というものです。ポストヒューマン的な想像力は、2010年代半ば以降の芸術表現においてひとつの熱を帯び、さらに近年は生成AIの進化によってあらためて切実さを増しつつあります。そのあいだyeuleは一貫して、この主題を抱えながら作品を更新してきました。だからこそ、このテーマを入口に据えることで、yeuleをすでに知っている人だけでなく、「気になっているがまだよく分からない」という層もまた、思考に参加できる共有地が生まれると考えました。
繰り返しますが、問いとは他者との共有地を築くためのものです。本稿ではそのために「ポストヒューマンの現在」という大きな問いを選びました。しかし、ターゲットが変われば、置くべき問いも当然変わっていくでしょう。それは「インターネット以後の自分はどこにいるのか」という問いかもしれないし、「かわいさと痛みはなぜ共存するのか」という問いかもしれない。反対に、コアなリスナーを主たるターゲットに設定するなら、「音像がプロデューサーによってどのように変化してきたか」といった、よりニッチで専門的な問いが成立するかもしれません。いずれにせよ重要なのは、視聴者や読者を見定め、その人にとって「これは気になる」「読んでみたい」と思える問いを投げかけることです。
そして、論においては、設定したターゲットに親和する言葉づかい、文体、間合い——そういったものを丁寧にチューニングしながら、問いに対する答えを導き出していく必要があります。たとえば先のyeuleの作品評では、読者層を広く設定したため、導入では音楽評論の専門用語をできるだけ避けています。エクスペリメンタル、エディット、コード感、サウンドスケープ、ハイパーポップ、シューゲイズ、ポスト・インターネット……そうした語彙は、入口に立つ人を遠ざけてしまうからです。本来であれば固有名詞も控えるべきですが、ここではあえてSOPHIE(ソフィー)やArca(アルカ)といった名を記しました。「ポストヒューマン」というテーマからyeuleに惹かれた読者が、その先に広がる音楽の地平にも触れてほしいと思ったからです。
問いが立った瞬間、批評がはじまる
前回、「批評とは未来を信じる態度を前提にして成り立っている」と書きました。もっと具体的に言えば、音楽評論やジャーナリズムは、未来の音楽文化の発展と啓蒙という大きな役割を担っている。書き手として「これを伝えたい」という想いを持ちながら、同時に、文化の未来へと接続する視点を忍び込ませていくこともまた大切だと思います。ただし、今回の本丸はまず「誰に、どのような問いを投げかけるか」という一点にありました。まずはその核心を、しっかり押さえてください。
さて、問いは立ちました。改めてこうやって順を追って説明していくと、とてつもなく大掛かりな作業のように感じるかもしれません。しかし、普段からある程度アンテナを張っておけば、こういった作業自体は1、2時間程度集中して取り組むことで大まかな輪郭は見えてきます。もちろん時間をかければかけるほど、聴けば聴くほど情報は蓄積されるので、それに越したことはありません。ただ、時間をかける際も、ターゲットと問いの設定を意識しながら収集していくという観点を忘れないようにすることが大切です。
共感性の高い、かつ鋭い問いが立てば、視聴者や読者は「確かに、それは気になる」と——おそらく無意識のうちにでも——感じながら、とりあえず聞いてみよう/読んでみようという態勢に入ります。しかし、ここからが本番です。問いは入口にすぎません。重要なのは、その問いを手放さずに、どのように言葉を運び、どのように受け手とともに思考を深めていくかです。問いが立った瞬間、批評ははじまります。けれども批評が成立するのは、その先で、読む者が「なるほど」と足場を得たり、「そういう見え方があったのか」と視界を更新したりするからでしょう。では、このあとの論はどのように展開されていくべきなのでしょうか。どのように意見を立て、どのように言葉を組み、問いに対する答えへとたどり着くのか。次回は、立てた問いに対して意見をどう立ち上げ、論をどう運んでいくか——その方法について考えていきます。