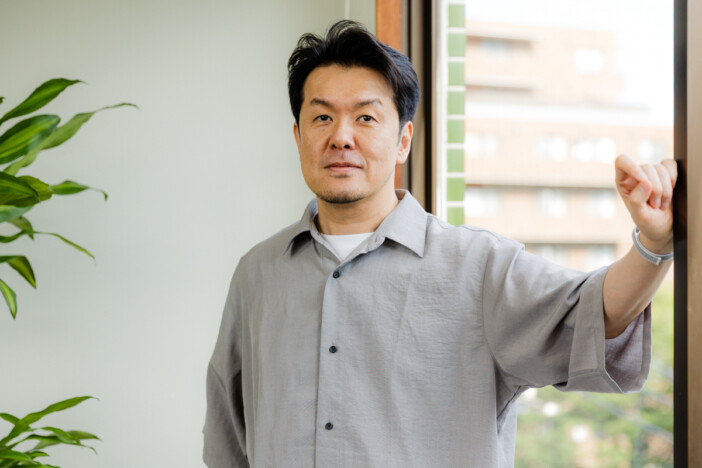作家・染井為人×SUPER BEAVER・渋谷龍太『歌舞伎町ララバイ』対談 「歌舞伎町に戻ると"帰ってきた"って安心します」

『悪い夏』『正体』など、手がけた小説が次々と映像化。“生活保護”“冤罪”などの社会的イシューを織り込んだダークで生々しい作風で支持を集めている作家・染井為人が『歌舞伎町ララバイ』(双葉社)を刊行した。
舞台は新宿・歌舞伎町。トー横キッズたちを取り巻く状況、大人たちの思惑が絡み合うなか、後半では壮絶な復讐劇へと突入する『歌舞伎町ララバイ』は、リアルな社会問題とエンタメ性を共存させた極上のノワール群像劇と言えるだろう。
今回、染井とロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太(Vo)の対談が実現。歌舞伎町で生まれ育った渋谷は『歌舞伎町ララバイ』をどう読んだのか? 本作の執筆プロセス、歌舞伎町に対する思いを含めて、歌舞伎町のど真ん中で語り合ってもらった。
SUPER BEAVERも染井為人も稀有な道を辿ってきた
——渋谷さんは以前から染井さんの作品を読んでいたそうですが。

渋谷龍太(以下、渋谷):はい。よく本屋に行くんですけど、染井さんの小説も平置きされていた文庫本を手に取ったのがきっかけで。確か『悪い夏』だったと思います。最初から「面白い!」と思って、それからずっと拝読させていただいています。上手く説明できないんですけど、純粋に面白かったのと、人間っぽい生々しさも僕が惹かれた要因の一つだったかもしれないです。
染井:ありがたいです。僕も渋谷さんの本、『都会のラクダ』(KADOKAWA)も読ませていただきました。
渋谷:ホントですか?!
染井:すごく面白かったです。連作短編みたいな構成で、エンタメ性もあり、純文学的でもあり、もちろん自伝でもあり。1章読むたびにSUPER BEAVERの曲を聴いてたんですけど、すごく贅沢な時間だったし、勝手に詳しくなった気持ちになってます。
渋谷:染井さんにそんなことを言ってもらえるとは……。
染井:最後あたりで初・武道館のシーンが出てきますけど、ちょっとウルッときたし、鳥肌が立ちました。そこまでの過程も読んでるし、「いろんなことがあって、ついに武道館にたどり着いたんだな」と思って。『都会のラクダ』を読んだことで、渋谷さんに対する印象も少し変わりましたね。メジャーデビューして、インディーズに戻って、渋谷さん自身にも心が持たない時期があって。こういう経験をしてきたからこそ、歌に説得力があるんだろうなと。
渋谷:うれしいです。ただ、僕自身は「作品において、作った人間の背景はどれくらい重要なんだろう?」と思うことがあって。バックグランド込みじゃないと響かない音楽なんて意味ないよなと思ったりもするんですよ。なので「自分たちのこれまでの歴史をどこまで出すべきなのか?」は迷っている部分でもあるんです。
染井:確かにSUPER BEAVERはすごく稀な道を辿ってきたバンドですからね。
渋谷:染井さんご自身も、以前は違う仕事をされていたじゃないですか。
染井:芸能の仕事をしてましたからね。

渋谷:そこからどうして小説家に舵を切ったのか、すごく興味があります。
染井:「芸能の世界に疲れてしまった」というのが一つありますね。20代後半ぐらいから思っていたのですが、その頃はもう「自分が離れたら迷惑がかかる」という状況で。
渋谷:穴をあけられない、と。
染井:そうです。バンドのメンバーではないけど、自分も部下がいて、一緒に仕事をしてきた人たちもいたので。それでも30代になったときに「これ以上は無理だ」と思い、仕事を辞めました。今でこそだいぶクリーンになりましたけど、僕がいた頃の芸能界は無礼講というか、ちょっと治外法権みたいなところがありましたからね。で、ずっと騒がしい場所にいたので、1人で静かにやれる仕事はなんだろう? と考えて、小説だなと。
渋谷:でも、選んでなれるものではないですよね?
染井:そうなんですけど、そのときは小説家に「なろう」ではなく、「なれる」と思ったんです。一生で1回きりですけどね、そんなことは。
渋谷:つまり何の根拠もなく、小説家に舵を切ったんですか?
染井:はい(笑)。結局2年くらいかかりましたけど、『悪い夏』を書き上げて、文学賞に応募して、ありがたいことに拾ってもらって。奇跡みたいな話だなって自分でも思います。
渋谷:すごいですね……。
歌舞伎町への愛は語れるものではない
染井:渋谷さんも小説を書いてみたらどうですか?

渋谷:じつは「小説を書いてみませんか?」とお話をいただいたことがあって。ただ自分のなかでテーマが決まらないんですよね。書けるかどうかという以前に、どこにフォーカスを当てるか?で悩んでしまって。それが見つかればやってみたいなという気持ちはあります。
染井:これもバックグランドの話になってしまうけど、歌舞伎町で生まれ育った人って、なかなかいないじゃないですか。そういう人が書いた小説ってどんなもになるんだろう? と。
渋谷:確かに人数は少ないですからね。子供の頃のクラスメイトも大人になって結婚すると、新宿を出て行く人がほとんどなんですよ。「ここで子育てはできないよな」と思うけど、自分はこの街が好きだし、ずっとここにいたいと思っていて。それもかなり特殊な感性かもしれないですね。
染井:渋谷さんの歌舞伎町への愛はどこから来てるんですか?
渋谷:僕、歌舞伎町のプレゼンができないんですよ。何がいいのかよくわかってないというか(笑)、「地元だから」以外の理由がなくて。実家がすぐ近くだし、見慣れた風景なので。バンドマンなのでよく地方に行くんですけど、歌舞伎町に戻ると「帰ってきた」って安心します。
染井:安心できる場所なんですね、歌舞伎町が。
渋谷:はい(笑)。僕が生まれた病院もホテル街のなかにあったんですけど、ずっと歌舞伎町の景色を見て育ったから、もうしょうがないというか。上京してきた方が地元に帰ったとき、ホッとするって言うじゃないですか。それと同じだと思ってます。
染井:なるほど。僕はけっこう田舎の出身なんですよ。千葉県なんですけど、市川で生まれて、印西というところで育って。高校のときに初めて友達と歌舞伎町に来たんですけど、もう怖くて怖くて。

渋谷:わかります。僕も高校のとき、初めて新宿区以外の友達ができて。ウチに遊びに来ることになって、ホテル街を突っ切ろうとしたら、「え、どこ行くんだよ?」って言われましたから。
染井:ですよね(笑)。僕が初めてここに来たのは25年くらい前なんですけど、すごく覚えていることがあって。たぶん風俗の店だと思うんでけど、プラカードを持ったお姉さんが、気だるそうに煙草を吸いながら「おっぱいモミモミいかがですか~」って言ってたんです。それがカルチャーショックすぎて、「え、何て言った?」って。
渋谷:「聞き違いじゃないよね?」みたいな(笑)。
染井:自分の地元にはキャバクラとかもなかったんで、ビックリしちゃって。渋谷さんはたぶん見慣れていたと思うんですけど。
渋谷:そうですね。小学校、中学校には海外の方も多かったんですけど、「親が水商売をやるために日本に来た」という子もけっこういて。それが当たり前だったので。
——25年前と現在では、歌舞伎町の雰囲気は大きく違いますよね。

渋谷:ぜんぜん違います。今の歌舞伎町のほうが怖いですね、僕は。
染井:僕も芸能の仕事をしているときによく歌舞伎町に来てましたけど、その頃ともまったく違っていて。『歌舞伎町ララバイ』を書くときに編集者と一緒に久々に回ってみたんですけど、「これは自分の知ってる歌舞伎町じゃないな」と。
渋谷:2000年代の初めに歌舞伎町をキレイにしようという計画がはじまって、2008年の終わりにコマ劇場が閉館して。その辺りからガラッと変わったんですよね。それまでは大人が怖いだったんですよ。「子供がいきがってるとやばいぞ」という感じがあったし、そこに良くも悪くも秩序があった。今はそうじゃなくて、「何でもありなことになっちゃいそうだな」という空気をはらんでるんですよね。
作家・染井為人が作品に取り入れた “歌舞伎町の空気感”
——染井さんの新作『歌舞伎町ララバイ』の主人公は、トー横キッズの少女・七瀬。今の歌舞伎町の雰囲気が生々しく描かれています。
渋谷:めちゃくちゃ面白かったです! 僕、トー横キッズたちがどういう人たちなのかわかってなくて。僕が知らない歌舞伎町に触れられた感じがあって、すごく新鮮でした。
染井:ありがとうございます。作品としてはエンタメに振ってはいるんですが、歌舞伎町にいる若い人たちの空気感みたいなものも取り入れたくて。実家や地元にいられなかった子たちにとっては、“歌舞伎町がユートピア”ではないけれど、居心地のいい場所なんですよね。そこに独特のコミュニティが出来ているわけですが、椅子取りゲームというか、ポジション争いみたいなものも少なからずあるみたいで。それが歪な形で表出することもあるし、事件につながることもあるのかなと。
渋谷:なるほど。『歌舞伎町ララバイ』を執筆するにあたって、実際に取材もされたんですか?
染井:歌舞伎町にいる人たちに直接話を聞いたことはないんですが、歌舞伎町にまつわる資料、トー横キッズの生態をテーマにした動画などもいっぱいあるんですよ。社会勉強と称して、あえてトー横キッズをやっている若い人のレポートもあるし、そういう資料を参考にしている部分もあって。そのときも「自分が知ってる歌舞伎町と違うな」という印象を持ちました。

渋谷:昨日、久々に新宿をグルッと歩いてみたんですよ。西口の思い出横丁も行ってみたんですけど、観光客の方がすごく多くて、英語のメニューもあって。あのあたりもだいぶ雰囲気が変わってましたね。
——『歌舞伎町ララバイ』の後半は、主人公・七瀬の壮絶な復讐劇へと展開します。
染井:七瀬には「愛する歌舞伎町に偽物がはびこっている。これは駆除しなきゃ」という使命感があったんんじゃないかなと。地元に居場所がなくて、歌舞伎町に来て、初めて人の優しさに触れて。歌舞伎町にほれ込んだからこそ、そこにいる偽物たちを許せなかったと思うんですよ。
渋谷:その展開は最初から決めていたんですか?
染井:いや、決めてないです。僕は最初からストーリーを決めて書くことが出来ないんです。プロットも作らないタイプで、『歌舞伎町ララバイ』も頭から書き始めたんですけど、1ページくらい書いたところで、七瀬というキャラクターに対して「これはいけるな」と感じて。

渋谷:そうなんですね! じゃあ、七瀬のバックグランドみたいなものも書きながら決めていくんですか?
染井:そうです。書いているなかで「こういう子なのかな」というイメージがなんとなく見えててきて。そこから「どういう生い立ちなんだろう?」「どんな背景がある子なんだろう?」という。
渋谷:面白い! そういうことって読んでるだけではまったくわからないし、人物像もストーリーもしっかり決めてから書いてるんだろうなって勝手に思ってました。
染井:普通はそうするんでしょうけどね。
渋谷:それで失敗することもあるんですか?
染井:ありますあります。書いていて「この後、どうするの?」「物語、動かないよ」とか(笑)。それで完成しなかった作品もありますし。バンドでもないですか? 曲を作ってる途中で「これは違うかも」というか。
渋谷:ウチのバンドは主にギター(柳沢亮太)が詞曲を作っていて。道筋を描ける人間がいて、そこにみんなで乗っかっていくので、途中で「これはダメだね」という経験はあまりないかもしれないですね。あと「僕が発するから、この言葉を使う」みたいなことも多くて。俺が歌うことを考えて言葉を積んだり、MCで俺が喋ってることが歌詞になることもあるんですよ。バンドのなかでインプットとアウトプットが出来ているのも強みなのかもなと。
染井:そうなんですね。
渋谷:僕らの歩みがすごく遅くて、ゆっくり進んできたのもよかったと思ってます。ちょっとずつ見える景色が変わっているし、そこで感じることも変化していて。なので「何を歌おうか?」と迷うこともないし、それが自分たちのクリエイティブの大事な要素になっている気がしますね。
染井:バンドのメンバーがいるって、いいですね。心強い。
渋谷:もちろん「めんどくせえな」ってこともありますけど(笑)、4人いれば4人の視点があるし、得手・不得手もある。ウチはそれぞれの役割分担がハッキリしているバンドなんですけど、そこもいいところだなと思ってます。

プロになると小説・音楽を嫌いになってしまうのか
——小説家は基本的に一人で執筆するわけですけど、インプットとアウトプットについてはどう感じていますか?
染井:そこまで意識的に「インプットしなきゃ」という感じはなくて。普段の生活のなかで気になることがあったり、「これってどういうことだろう?」という興味がもとになることが多いです。
渋谷:何がいちばん多いですか? 本を読むとか映画を見るとか、方法はたくさんあると思うんですが。
染井:人と話することかな。たとえばこうやって渋谷さんとお話させてもらうのもそうで。歌舞伎町がホームで、いちばんホッとする人が、田舎で暮らさなきゃいけなくなったらどうなるのかな? とか。
渋谷:うわー、怖い怖い(笑)。
染井:(笑)「そこでどうやって生きがいを見つけるんだろう?」ということにも興味があるし、そこに今の社会問題を組み合わせたり。たとえば地域復興だったり、町おこしだったりを掛け合わせることで、物語が動かくかもしれないなと。
渋谷:そうやって着想を得るんですね!
染井:『正体』もそういう感じでした。2018年に大阪の警察署から脱走して、50日くらい自転車で逃げてた人がいるんですよ。日本一周を目指している人を装って、いろんな場所で記念撮影とかしていて(笑)。そのニュースと“日本の法律では18歳でも死刑判決を受ける可能性がある”ということを組み合わせたのがきっかけなので。“社会派”と言われることもあるんですが、自分ではそう思ってなくて、そのときに興味がある事柄を掛け合わせている感覚なんですよね。

渋谷:めちゃくちゃ興味深いです。僕、もう一つ聞きたいことがあって。芸能の仕事をされていて、あるときから小説家になったわけじゃないですか。そのことで“本が好きだった自分”は変わりましたか?
染井:だいぶ変わりましたね。前はただの本好きで、純粋な気持ちでページをめくってましたけど、自分で小説を書くようになってからは作者の意図が見えるようになって。「ここはちょっと逃げたな」みたいなことがわかるようになった。
渋谷:やっぱりそうなんですね! そういうスイッチで自分で切れるんですか?
染井:切れないですね。ただ、本が嫌いになったかといえば、そんなことはなくて。なぜダメなのか、どうして好きなのかという理由がハッキリしてきたんですよ。好きな小説は自分で書くようになっても好きだし、そういう意味では変わらないです。映画やドラマも同じですよね。芸能の世界で仕事をするようになると、「このロケ地はあそこだな」とか「主人公の役者がこの事務所だから、脇役のこの人はバーターだな」とかわかるようになって(笑)。昔みたいに純粋に楽しめなくなりつつ、それでもいい作品はやっぱりいいので。音楽も同じじゃないですか?
渋谷:そうですね。自分でバンドをはじめて、10代前半の頃の目線とは明らかに変わって。今の染井さんの話とつながるんですけど、なぜ好きなのか、なぜいいと思うのか、その裏付けみたいなものに気が付いたんですよね。好きじゃないもの、「あんまりよくないな」と思うものについては、さらに粗が見えるようになって。そのことで一時期は「音楽が嫌いになってきたかも」と思ったこともあったんですけど、じつはそうじゃなくて、明瞭になったんですよね。
染井:そうですね。僕も同じです。
渋谷:モノを作る人間として、そのことをぜひ聞いてみたくて。染井さんのお話はすごく腹オチしたし、聞けてよかったです!