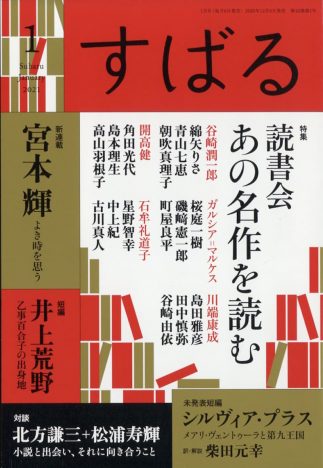小川洋子が示した飽和する現代コミュニケーションの解 6年ぶりの長編『サイレントシンガー』の”匿名性"を読み解く

小川洋子の6年ぶりの長編小説となる『サイレントシンガー』(文藝春秋)は、とある山の片隅、「アカシアの野辺」で育った少女リリカの一生に寄り添うような静かな時間の流れを読む物語と言えるだろう。
「アカシアの野辺」の人々は無言であることを愛する。内気で言葉を交わすことを避けて生活する人々が集まる小さな集落の中で必要なコミュニケーションは多くない。決して宗教施設ではないが、市井に暮らす人々との関わりを最小限に避け、金網に囲まれた敷地の中で生活をしている。コミュニケーションは指文字で行われるが、手話のように多くを語ることはできない。羊、火、暦、鍬……。必要な単語を表すいくつかのサインがあるだけで人々が暮らしていくには十分なのだ。
リカは「アカシアの野辺」で育った。共に暮らすおばあさんと、村の人々がつくる無言の小さなコミュニティ。けれど、休養室の老介護人が口ずさむ子守唄を耳にしたリリカは、歌を知るようになった。
やがて彼女は、野辺に「無言の声」を響かせる存在となる。リリカは言葉を持たぬ者たちに向けて歌うことはできても、誰か一人のために歌うことはできない。毎日夕方5時、町役場から流れる「家路」は確かに彼女の声でありながら、誰の声でもない。それでも、その匿名の声を必要とする人々が確かにいる。
リリカには外とのつながりがある。ボイスレッスンをしてくれる先生、仮歌の仕事を依頼をする人々、リリカを気にかけている料金係さん。
野辺の人々とのつながりは、外の人々とのつながりと違って“絡まり”が喪失している。声と共に失ったのは、複雑に絡み合う人間関係の結び目であり、そこには直接的な繋がりしか残らなかった。その単純さは安らかさをもたらす一方で、野辺はどこか喪失感が広がる不完全な共同体となっているのだ。
著者・小川洋子はこれまでも、『博士の愛した数式』や『密やかな結晶』など、外界から切り離された閉鎖的な空間を舞台に、欠落や喪失を抱える人々を描いてきた。本作はその系譜に位置づけられるが、欠落の対象を「声」に据え、沈黙と響きのあわいに物語を展開させている。その舞台は著者自身の経験から生まれた独特の宗教観によって生まれたものだ。「アカシアの野辺」は宗教施設ではないと明言されるが、外部との関わりを排し、沈黙を美徳とする生活は一種の宗教性を帯びる。
リリカの歌は、外の世界では匿名の声として響き、野辺の中では存在を希釈された声として受け入れられる。リリカは野辺の中で声を持つことを許された存在だった。人々はどれだけ無言でいることを愛していても、全く会話をせずに暮らしていくことはできない。「アカシアの野辺」の人々は生まれた時からそのコミュニティの中にいたわけではない。外の世界を知っている人々であるからこそ、声の存在が必要になる。リリカは媒介者として、沈黙と外界、無声と有声の境界をまたぎ、その存在によって共同体を維持する役割を果たす。無言の共同体は、声を持たぬことで完成するのではなく、むしろ声の存在によってのみ維持されている。
幼い頃から「アカシアの野辺」で育ったリリカは声を持ちながらも沈黙を体現する完全な存在であったのかもしれない。彼女の歌声は、森を渡る風のように、ただそこに在り続ける。誰のものでもない声が、静かに人々を包み込み、真っ直ぐ森を抜けてゆく。
小川洋子が繰り返し描いてきた「欠落」は、“匿名の声”というかたちを取り、声を失いかけた現代の世界を支えるものとなる。情報と音声が溢れ記号的なコミュニケーションが繰り返される時代に、必要とされるのは完全な無言ではなくむしろ、誰のものともわからぬ穏やかな声なのではないか。リリカはまさに「サイレントシンガー」として、沈黙を望む人々をつなぎとめる存在であったのだ。