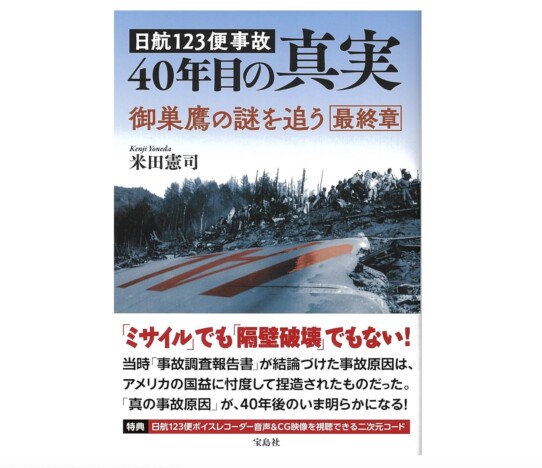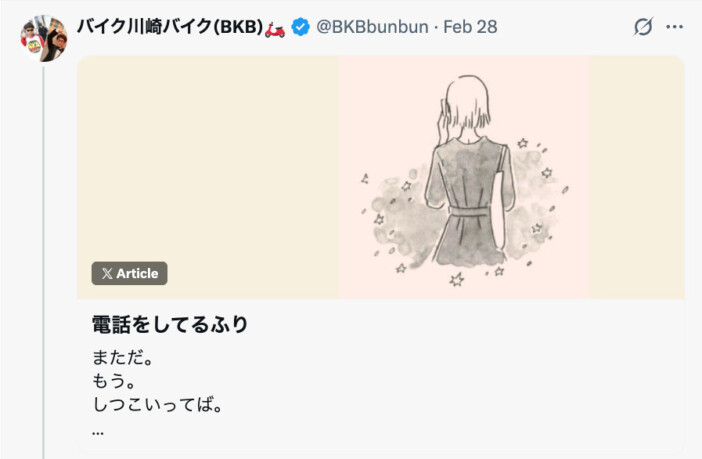書評家・千街晶之が読む『七つの大罪』 7に因んだ7人の作家が織り成すオリジナル・アンソロジーの愉悦

傲慢・怠惰・憤怒・嫉妬・強欲・色欲・暴食……と並べれば、カトリックにおける「七つの大罪」であることはご存じだろう(正確には、人間を罪へと導く欲望や感情のことを指すらしい)。といっても聖書の中でこの7つが制定されているわけではなく、後世の聖職者・神学者が定めたものである。
■7人の実力派作家の顔ぶれ
現実世界では罪の源とされるような忌まわしい欲望や感情でも、フィクションの世界においては物語のネタとして恰好の題材となる。漫画やアニメのモチーフとしてもポピュラーだし、ミステリの世界では、デヴィッド・フィンチャー監督の映画『セブン』が「七つの大罪」を扱った作品として有名だ。そして新たに、宝島社から『七つの大罪』と題されたオリジナル・アンソロジーが刊行された。「七つの大罪」それぞれに因んだ短篇を7人の作家に執筆させるという競作企画だが、参加作家がいずれも数字の7に縁がある顔ぶれなのだから実に凝っている。中山七里、川瀬七緒、七尾与史、カモシダせぶん、若竹七海はわかるし、三上幸四郎も3+4=7だというのは容易に見当がつくとして、岡崎琢磨はどこに7があるのだろうと不思議に思うが、なんと7月7日生まれなのだそうだ。
巻頭を飾るのは「傲慢」担当の中山七里の「罪の名は傲慢(プライド)」。リベラル文化人を気取る裏ではパワハラ・セクハラを常としている男と、彼に性的暴行を受けたと告発した女性ジャーナリストの対立がやがて殺人事件に発展する……という社会諷刺色の濃い作品で、中山作品ではお馴染みの刑事コンビも登場する。「怠惰」担当の岡崎琢磨の「手の中の果実」では、小学生の次男が不登校になった理由の見当がつかない父親が、妻の実家の葡萄農家に息子と滞在することになる。本書で最も心温まる後味の作品であり、「七つの大罪」といってもおどろおどろしく罪で彩られた作品ばかりではないことがここで判明する。不登校をめぐる真実に気づくのが誰かという点でも意外性がある。
「憤怒」担当の川瀬七緒の「移住クライシス」では、幼い息子を失ったばかりで悲嘆に暮れている夫婦が住む家を、鎌を持ち、憎悪の表情を浮かべた老女が脅かす。表面的に見えているものがくるりと裏返る、ミステリのお手本のような好短篇だ。「嫉妬」担当の七尾与史の「オセロシンドローム」の主人公は、嫉妬深さが原因で交際相手から別れを告げられた女性。相手を諦められない彼女は心療内科に通うようになるが……。先が読めない展開に翻弄される作品であり、夏目漱石の『こころ』の絡め方にも工夫が見られる。「強欲」担当の三上幸四郎の「十五分」は、3人の男女の交通事故死を意図的に引き起こしたという容疑で逮捕された動画配信者と、拘置所に面会に訪れた週刊誌記者の対話の形式で進行する。「十五分」というタイトルは拘置所の面会時間であることが冒頭に記されているが、それだけではなく、複数の意味がこのタイトルに籠められていることが最後に判明する技巧的な作品だ。
■白眉なのはカモシダせぶんの「色欲」
本書の中でも特にユニークなのが、「色欲」担当のカモシダせぶんの「父親は持ってるエロ本を子どもに見つからないようにしろ」。タイトルからして何事かと思うが、まさにこのタイトル通り父親が、自分が隠していた18禁のエロ漫画雑誌を息子が読んでいることを知る。ところが息子は悪びれるどころか、開き直って自分の性癖を滔々と語るのだ。ここからどうやってミステリになるのかと思うが、ある種の安楽椅子探偵ものとも言うべき展開となるので目が点になる。リズミカルな語り口も素晴らしく、本書の白眉と言えるだろう。
トリを飾るのは「暴食」担当の若竹七海の「最初で最高のひとくち」。冒頭から、わがまま放題の息子と異様に献身的なママという、何やら不健全な印象の親子関係が描かれている。しかも彼らは、何らかの犯罪に関わっているらしい……。「暴食」テーマを若竹七海が書いたら猛毒たっぷりの作品になることは予想できたが、まさかここまでとは……と背筋が凍る一大怪作だ。若竹作品ではお馴染みの「あの人」、別の作品の舞台である「あの場所」も登場し、ファンサーヴィスも抜かりはない。
同じ1行から始まる小説を複数の作家が競作する『黒猫を飼い始めた』『嘘をついたのは、初めてだった』『これが最後の仕事になる』『だから捨ててと言ったのに』『新しい法律ができた』(いずれも講談社)、一時期ネットミームとなった「祠破壊」をモチーフにした作品で揃えた『祠破壊ホラー小説アンソロジー』(星海社)、北海道圏を中心としたミステリ作家たちの小説・漫画・評論から成る『北海道ミステリークロスマッチ』(行舟文化)等々、このところユニークなオリジナル・アンソロジーの企画が相次いでいる。本書『七つの大罪』もそれらに連なる企画であり、収録作の水準も高い。これからもこういう楽しいオリジナル・アンソロジーが続々と出ることを期待したい。