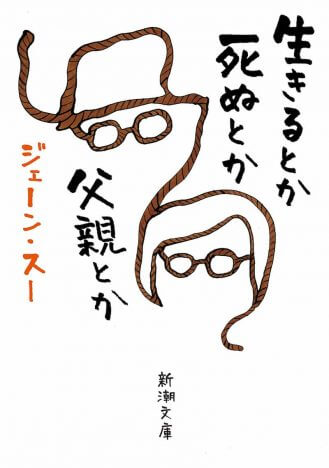ジェーン・スー、50代で見えてきた人間関係の築き方 「人を変えるより自分がそこから動くことに注力した方が良い」

人間の本質は変わっていない。可視化されているだけ。
――スーさんはラジオなどでも相談を受けることが多いと思いますが、最近多い相談事はどんなものですか。
スー:1カ月に1回、インスタのストーリーズで質問を受付けているんです。毎回1000 件から2000件くらいの質問がきて、ざっと目を通した印象で言うと、変えられない過去にとらわれて悩んでいる人、まだなにも起こっていない未来に不安を感じている人が半分くらい。過去は変えられないし、未来のことはわからないので、そこに時間を使うのはもったいないなと思います。とらわれてしまう気持ちはよくわかるけれども、それは自分自身の可能性を狭めたり、自ら自尊感情を削ったりする行為だと自覚した方がいいかも。
――コロナ禍の中で書かれた項目では、理屈や知性より情緒が先走りすぎていることも指摘されています。そうした傾向は加速している感じがありますか。
スー:加速はしていないと思うんです。SNSの影響で、ファクトよりエモーションが尊ばれる場面が、より可視化されるようになっただけではないかと。昔の方がひどかったかもしれませんよ。
――ファクトよりも情緒というのは日本人の特徴なんでしょうか。
スー:それはどこの国も同じかもしれません。よくも悪くも情報の拡散が加速しやすくなっているとは思うんですけど、人間の本質として、エモい方向にコロッと騙されちゃうみたいなところは変わっていないと思います。加速しやすくなっているとしたら、人間側ではなく、システムの問題ですね。
パートナーシップにおける無意識の不均衡
――パートナーシップや結婚観についても書かれていますが、お母さんが結婚を機に仕事を辞めてサポート側に回ったことに対して静かな怒りを感じていらっしゃることに激しく共感しました。実は身内が同業の彼氏と一緒に暮らし始めたんですが、収入や立場などあくまで対等な関係なので、絶対になし崩しでサポート側に回るなと言っているんですね。
スー:女性は、よく気がつくとか優しいといった性質をもっていると、女らしいと褒められがちです。そういう性質をもっていたほうが、価値が高い・優れているという評価を世間からまだされがちなんですね。だから、真面目な女性ほどやりたくなってしまう。いい子でいたほうが褒められてきたんだもの。当然です。でも、そういう仕組みのせいで女の人が社会に出づらくなった歴史を理解していれば、気を付けられると思います。
それと、極端な収入格差がないのであれば、家賃を均等に負担すれば、力の均衡はだいぶ保てる気がします。土台がイーブンだから、そこから話を始められる。外貨を稼いでくるほうと、家のことをやるほうというふうに、お互いが納得の上で役割分担するのは良いと思うんですけど、それによって発言力や決定権の不均衡が生まれるのはマズい。そうならないようにするには、細心の注意が必要ですよね。

スー:残念ながら、私にはわからないですね。立て直し能力があるなら、私、結婚していたかもしれないし。まあそれはないか(笑)。ただ、立て直したいうちは努力しますけど、できることをぜんぶやって、それでも無理だと思ったら別れてきちゃったので。長く年月を経た関係の立て直しは正直難しいですよね。だからこそ、スタートで間違えるなよ、良かれと思ってサポートに回るなよと言い続けているんです。関係性が固定するまでが勝負だと。