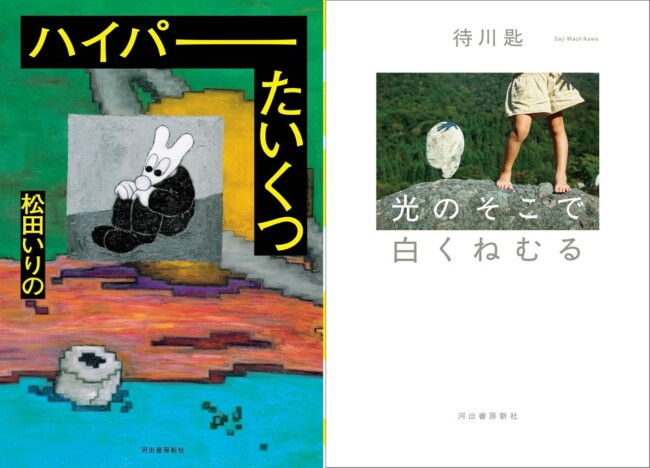人間椅子・和嶋慎治、怪奇と幻想に彩られた文芸路線を貫く理由を聞く 歌詞集『無情のスキャット』について

■「無情のスキャット」にした理由
――人間椅子は初期から怪奇や幻想の猟奇的イメージ、文芸路線といった方向性で一貫していますが、路線変更を考えるとか、外部から方向性を変えるようにうながされることはなかったですか。
和嶋:『見知らぬ世界』でわりと普通のポップスみたいな曲をいっぱい作ったら「そういうのはやめてくれ」とレコード会社にいわれました(笑)。それはもう人間椅子のスタイルがある程度決まってからのことですけど。初期には「ギタリストやベーシストの兼任でなくボーカリストを入れた方がいい」とか、「気持ち悪い歌じゃなくて普通の曲をやった方がいい」とかいわれました。
でも、売れ線の曲を書いたら僕らはもっと売れなくなると気づいていましたし、ボーカリストを入れるのも違うと思って断りました。なんだかんだいって、文芸ロック的なモノを貫いていますね。
――人間椅子のもう一つの特徴として、和嶋さんと鈴木さんの出身地である青森の方言があります。
和嶋:我々の一つのスタイルなので詩集にもいくつか入れました。西洋の音楽におけるキリスト教の基盤が僕らにはないから文芸ロックを書いたわけですけど、その延長線上でなにかしら説得力を持たせるルーツを使うのもいいと思いました。例えばイギリスのシン・リジィは、アイルランド民謡をとり入れている。見事に成功していますが、とはいえ日本人がアイルランド民謡をやってもしょうがない。それで、津軽弁の歌詞を書いた。自分ら地方出身者が田舎者だと恥じることなく、隠すのではなく、逆にコンプレックスを積極的にとり入れる方がロック的というか、表現としていい。過去にフォークの三上寛もやっていてカッコよかったですけど、それをロックでやった。津軽弁の特徴は、激しさです。相手をディスる言葉が多くて、褒めることはあまりないかも(笑)。で、相手に対して否定的なことをいう場合、関西は回りくどくいうのに津軽は言葉少なく、ぶっきらぼうにズバッという。メタルに向いてると思っております。
――初期の詩を読み返してみると、「針の山」はメタリカもカバーしたバッジー「Breadfan」に日本語詞をつけたものですけど、英語詞とはまるで違う抑揚になっていて、カバー曲なのに人間椅子のオリジナリティを象徴する1曲になっていますね。
和嶋:英語を知らなかったのがよかった。そこを調べたり読みこんだりするとオリジナルに寄っちゃうし、ただ曲から受けるイメージだけで書いた詩だったので、それが後の文芸ロックのやり方につながったんだと思います。
――方言を使っていない曲でも、ボーカルになまりを感じさせる節回しがけっこう出てきますよね。あれは自然とそうなっているのか、意識的にやられているのか。
和嶋:鈴木君の方が顕著になまって聴こえますね。「意識してない」と彼はいっていますが、ちょっと意識していると思います(笑)。土着的に聴こえるようにメロディを作ったら、歌い方も自然とそうなったところがありますね。
――2年前、バンドの曲へのトリビュート・アンソロジー『夜の夢こそまこと 人間椅子小説集』に関する取材の時、猟奇的な歌が書きにくくなったと話されていました。
和嶋:幻想ではない現実の猟奇というものがあるわけじゃないですか。そのイメージと直接的に結びつくのは避けたいと思うようになりました。今回の本でも書きましたけど、40代前半で自分の意識が変わり、救いがないものは作りたくないと考え始めた。表現って本来は、救いだと思うんです。宮沢賢治もゴッホも宗教と芸術は同じだといっていて、僕は同感です。そう気づいたから、はずれたものはもうやれない。
――「夜」や「死」など世界のネガティブな部分を歌うバンドというイメージは一貫していますけど、詩集を読むと後半になるにつれ「光」、「人間」など前向きなことがらを歌うものが増えた印象がありました。
和嶋:最初から現在までずっと根底にある核は、たぶん「死」です。生まれて死ぬ、特に「死」の側を歌うのが僕らだと思います。ただ次第に「生」を全うして「死」を迎える方がいいと、前以上にいうようになってきた。最近の詩にも「死」という言葉は出てきますし、身近で誰もが経験することでしょう。なのに、YouTubeなどでは「死」というワードが規制されている。「自殺」は使えないし。そういうものを見ないようにする文化が形成されるのは、おかしい。だから、これからもいっそうやっていこうと思います。
――収録作のなかから「無情のスキャット」を書名にしたのは、ご自身の選択ですか。
和嶋:そうです。冒頭に収録した最初期の「鉄格子黙示録」は、僕の詩の方向性が決まったものだし、それにしたかったんですけど、編集者に相談したら「イメージが暗すぎる。そのタイトルでは売れないんじゃないか」となった。「無情のスキャット」は人間椅子が認知される第二のきっかけとなった曲だし、「生」を全うして「死」を迎えることに意味があると気づいた後の詩なので書名にふさわしいと思いました。
■小説を書くことは一番難しい
――詩集の後半では「世界」という言葉も多くなっています。
和嶋:個人の印象だけに頼るのではなく、俯瞰して書くようになりました。世界をどうとらえるかを書きたくなった面もある。ただ、我々が今いる地点で見えるものを時代そのままに書いちゃ駄目なんです。すぐ色あせて次の年には世界もどんどん変わるから。もうちょっと普遍的に、といってもここ2000年くらいの普遍で書ければと考えています。
――題材とする文芸作品も、最近のものは使わないですよね。
和嶋:ある時期から(作家の)文章がライトになって、日常を切りとるものが多くなったし、共感できない。するとどうしても三島由紀夫以前というか……。
――わりと新しめの題材だと「人間の証明」(森村誠一)がありますけど、これにしても1970年代ですものね。
和嶋:「人間の証明」はタイトルがカッコよすぎる。例によって僕の詩は小説と全然違いますけど。小説のタイトルって文章の才能がある人がつけたものだから、タイトルだけですでになにかを語っている。自分はなかなかその域にいけません。
――『夜の夢こそまこと』に短編を書かれていましたけど、小説を書くことについては。
和嶋:自分のなかで一番難しい。詩は原稿用紙1、2枚で言葉を削る作業ですよ。小説は言葉を増やす作業だし、短編でも原稿用紙何十枚、その中で膨大な言葉に矛盾があったらダメでしょう。KADOKAWAで小説を書いたら、矛盾点に校正の赤字がものすごく入りました。小説だと1回伏線を張ったら回収しないとダメ。その伏線をいくつもだなんて、ミニアルバム1枚作るくらいのエネルギーと構成力が必要です。詩だと構成が破綻していてもOKなんです。1番と3番で違うことをいっても、なんかよく聴こえる。詩を読む人のイメージにゆだねられる部分があるんです。イメージをすべてこちらで提供しなければいけない散文は、表現の角度があまりに違うので難しい。
――俯瞰で詩を書けるようになったという変化の理由はなんでしょうか。
和嶋:自分の主観のみでやっていくことに行き詰まりを感じたんでしょうね。完全に概念先行になっちゃった時期があったんです。なにをいいたいかより猟奇的なもの、気持ち悪いもの、B級映画的なものでただ怖くすればいいみたいな感じでしか書けない時期があって行き詰まった。その後、貧乏生活でアルバイトをする中真剣に読書をしたりと、日常でもいろいろ試練があったので、それで変わることができました。
自分がなにをいいたいかがわかったから、詩も俯瞰で書くということに気づけた。ピカソだって、そうだったんじゃないですかね。彼も世界平和や愛を描いていると思うんです。子どもの絵のような純粋なものを描くべきだとなったから、ああいうスタイルに変わったわけでしょ。死ぬまで表現し続けている人って、やっぱり1回はそういう変化があってやれるようになるんじゃないかな。