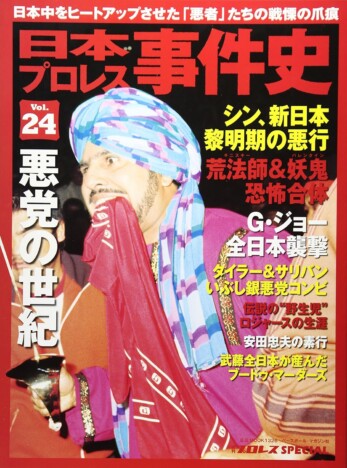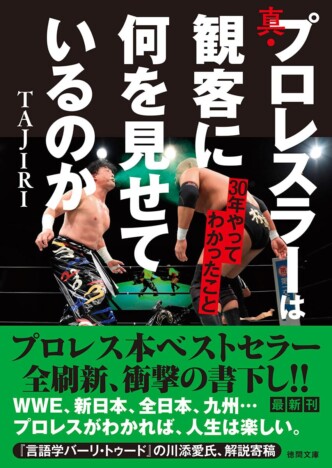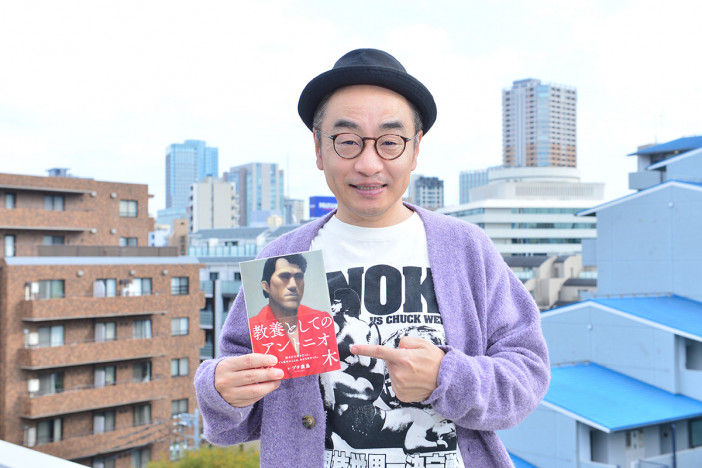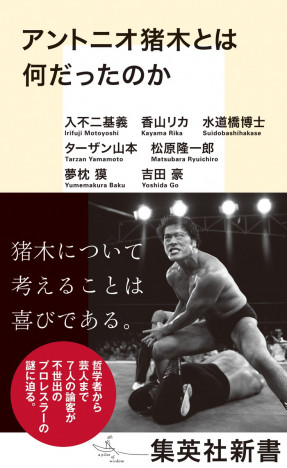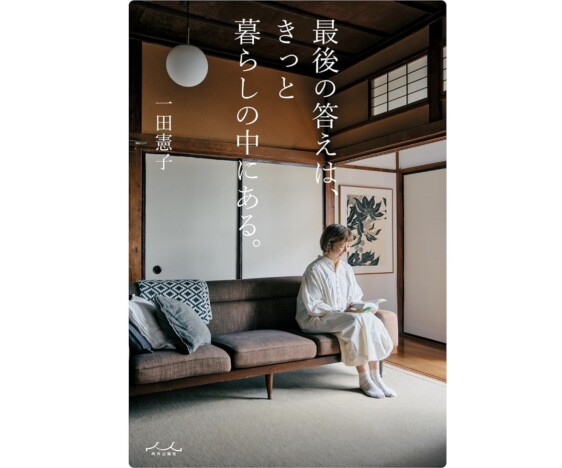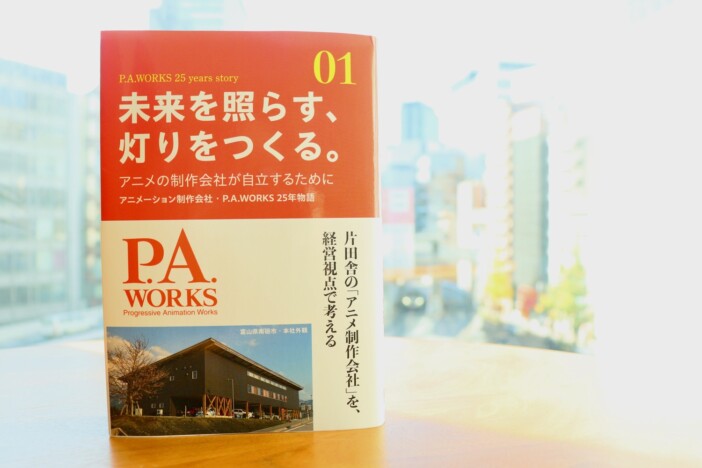力道山が遺した負債は30億円ーー22歳の未亡人はどのような半生を送ったのか? 知られざる昭和のプロレス史

1963年12月8日の夜、当時の日本を代表するプロレスラーだった力道山は、ナイトクラブ「ニューラテンクォーター」の店内でヤクザに刺され、12月15日に死亡した。力道山の誕生年には諸説があるので、正確な享年はわからない。
その力道山は、死の半年ほど前に生涯四度目の結婚をしていた。相手は日本航空国際線のスチュワーデスだった田中敬子。力道山死亡時、まだ22歳だった。世紀のスーパースターの妻という立場から一転、日本一有名な未亡人という立場に置かれてしまった彼女は、力道山の死後どのような半生を生きてきたのか。膨大なリサーチと執念深い裏取りによって敬子の歩んだ人生を描いた一冊が、細田昌志の『力道山未亡人』(小学館)である。
戦後日本を代表する超有名レスラーとして知られる力道山だが、実業家としての顔も持つ。彼が1963年に経営していた会社は、リキエンタープライズ株式会社、日本プロレス興業株式会社、リキスポーツ株式会社、株式会社リキボクシングクラブ、リキ観光開発株式会社の5つである。
5つの会社の業務内容はそれぞれ異なる。プロレスの興行を行う日本プロレスを筆頭に、レストラン・ボウリング場・トルコ風呂(サウナ)などの経営を行うリキスポーツ、ボクシングジム経営とボクシング興業を行うリキボクシングクラブ、相模湖畔のレジャーランド計画のために1962年に新設されたリキ観光開発といった役割分担があり、主に不動産業を行うリキエンタープライズが親会社となっていた。
力道山の死により、これら5つの会社の社長に就任することになってしまったのが、未亡人である敬子だった。本書では、これまでほぼ語られることがなかった「力道山の未亡人はどのようにしてこれらの会社を切り盛りしようとしたのか」そして「田中敬子は、一体どのような女性だったのか」が詳細に語られている。
大戦中に中国戦線で戦った警察官の父を持ち、健康優良児として表彰までされた少女時代から、紆余曲折を経て採用された日本航空のスチュワーデスとしての活躍、そして力道山との馴れ初めから結婚に至るまで、前半生だけで波乱万丈の濃厚さだ。特にスチュワーデス時代のエピソードは眩しいばかり。そもそも海外渡航自由化前の国際線は、限られたエスタブリッシュメントや社会的エリートだけのものだった。そこにアクセスして世界中を飛び回る敬子の生活は、力道山との結婚前からすでに常人離れして華やかだったことが詳細に綴られる。
力道山との結婚に至るまでの経緯、そして未亡人社長として力道山の遺した多額の負債を返済するべく戦うくだりは、本書の中盤から後半にかけてまとめられている。基本的には敬子の証言を元にしており、この人しか知らなかったであろうエピソードが続出するのは、本書の大きな見どころの一つだろう。特に、力道山の連れ子と一緒に力道山の前妻である小沢ふみ子を訪ねるくだりは、なんともビターな味わい。まさに「昭和の大人」の雰囲気を感じる部分である。
社長就任後、「力道山」の看板とプロレス事業の収益を狙い、敬子の周囲には様々な人々が出現する。経営者やレスラー、裏社会の住人や政治家といった男たちに翻弄されながら、世間を知らず年若い敬子は必死に自らの夫が残した会社を守ろうとする。このあたりのエピソードには、昭和の興行史・プロレス史を知る上でも重要なポイントが数多い。特に力道山の死からBI砲の大ブームを経て日本プロレスが崩壊し、新日本プロレスと全日本プロレスの二団体時代へ移行するまでの間の出来事を力道山の未亡人の視点からまとめている点は、プロレス関連書籍の中でも珍しいポイントだろう。
圧巻なのが、これらのエピソードを浮き彫りにするために重ねられた入念なリサーチだ。書かれている物事には裏付けとなる具体的な証言やデータ、過去のインタビューでの発言などが併記されており、執念すら感じる裏取りには舌を巻くしかない。前作『沢村忠に真空を飛ばせた男: 昭和のプロモーター・野口修 評伝』でも「そりゃ執筆に10年かかりますわ……」と納得した、微に入り細に入った細田のリサーチは、本書でも健在である。
この証言とリサーチの説得力で読ませるのが、本書後半の見どころである「全日本プロレスの"力道山十三回忌追善特別大試合"と、新日本プロレスの"アントニオ猪木VSビル・ロビンソンのNWF世界ヘビー級タイトルマッチ"の興行戦争」の真相に迫るパートである。これはファンの注目を集めるふたつのビッグマッチが1975年の12月11日に同日開催された事件で、力道山という金看板を掲げたジャイアント馬場が、猪木の興行をつぶすためにわざと同日程の興行を仕掛けた……という説が語られていた。
先に12月11日にタイトルマッチを行う予定を決めていたのは、猪木の新日本プロレスだとされている。そこに馬場率いる全日本プロレスと国際プロレス、そして当時全日本に救済合併された形になっていた日本プロレスが、合同興行という形で「追善特別大試合」を立ち上げた。そして、馬場は熾烈な興行戦争の相手である猪木に「師匠の追悼興行に、お前は出場できないのか」と迫ったのである。この経緯を見れば、この事件は確かに全日本と新日本の興行戦争の一環とも考えられるし、馬場が猪木に対してリング外での攻撃を仕掛けたという説にも説得力はある。
すでにビル・ロビンソンとのタイトルマッチの予定を組んでしまっている猪木は、当然ながら追善特別大試合に出場することはできない。そんな猪木に対し、11月11日の東京スポーツに百田敬子名義で「波紋状」といえる過激な内容の声明文が掲載され、最終的に説得に応じた猪木が頭を下げて謝罪。12月11日には当初の予定通り、ビッグマッチがふたつ開催されることになった。
この時の猪木対ビル・ロビンソン戦が「プロレスの教科書」とも言われるほどの名勝負となったこともあり、この事件は昭和プロレスのファンにはよく知られている。さらに、馬場による猪木への攻撃だったという説が「定説」とされている事件でもある。しかし、細田は追善特別大試合の会場である日本武道館の興行開催のシステムや、当時の東スポの立場、敬子への入念なインタビューを通して、この大事件の真相に迫ろうとする。リサーチの果てに推測された真相はかなりの説得力があり、「そうだったのかもしれない……」と唸らされた。全体的に「へえ〜!」となるエピソードの多い本書だが、この12月11日の興行戦争をめぐる推測は特に面白かった。