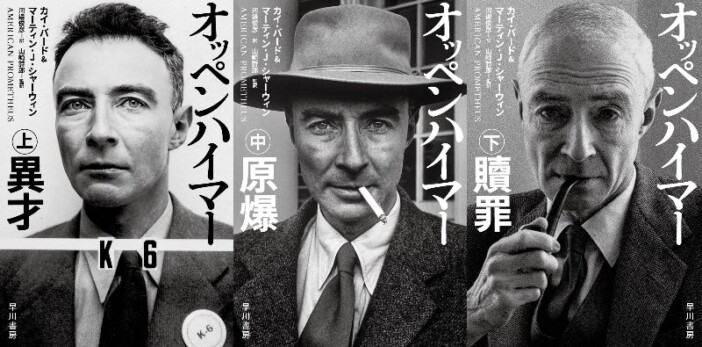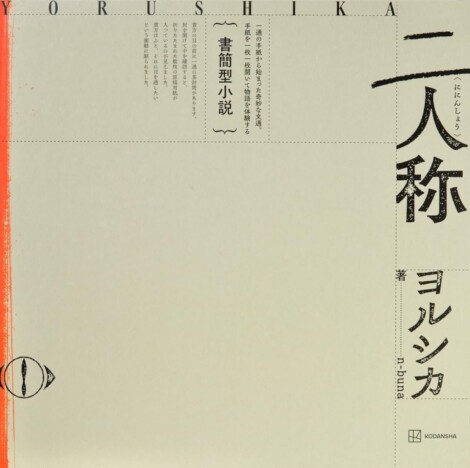【連載】速水健朗のこれはニュースではない:学生運動時代から20年後が描かれた『ぼくらの七日間戦争』

ライター・編集者の速水健朗が時事ネタ、本、映画、音楽について語る人気ポッドキャスト番組『速水健朗のこれはニュースではない』との連動企画として最新回の話題をコラムとしてお届け。
第8回は、宗田治『ぼくらの七日間戦争』と1980年代の管理教育について。
『ぼくらの七日間戦争』が刊行された時代

10代のことをティーンと呼ぶが、13~15歳が「ローティーン」で16歳から19歳はハイティーンである。11、12歳は、ティーンには含まれない。近年のドラマでは『ストレンジャーシングス』がローティーンものとして圧倒的におもしろかったけど、男女を描くにも恋愛一色にならない時期というのがいい。青春期のちょっと前の時期。関心事は多岐に向かい、まだ恋愛以外一色にはなっていない。
先日、小説家の宗田治が亡くなった。95歳。彼の代表作である『ぼくらの七日間戦争』が刊行されたのは1985年。僕がこの作品に出会ったのは、それが映画化された1988年。映画に引き込まれて原作に触れた。正確を期せば、宮沢りえの写真が帯に付いていたから、いわば映画のグッズとして購入した文庫版が触れるきっかけだ。
映画は、15歳の宮沢りえが主演で僕もまさに15歳のときに見た。ゆえに特別な作品である。ただ小説では、主人公たちは中学1年生で、それはそれなりに重要な設定ではあった。日本の公立では、小学校まではとても自由。服装も私服だし、締め付けなんかもない。それが中学になるととたんにダークカラーの制服を着せられ、前髪の長さから持ってくる鞄のメーカーまで指定される。途端に自由が奪われる。それに嫌気がさした生徒たちが反乱を起こすという話。

ただ、ローティーンを描くドラマという意味では小説も映画も同じである。小説に出てこない戦車が映画では登場するが明らかに蛇足だったと思う。
主人公たちが立てこもった廃工場の周りには親や先生たちが集まってくる。両者の間には温度差がある。子どもたちを過剰に心配しているのが親たち。教師たちは、力尽くでも止めさせなければならないと思っている。
教師は、親たちの方針の甘さが子どもをつけあがらせたのだと釘を刺す。映画ではそんな理不尽な教師を大地康雄が演じていた。親たちよりも10歳ほど上の50歳前後という設定ではないだろうか。ただ大地康雄は映画の当時30代後半。とてもそう見えない。原作者の宗田理は、これを書いた85年の時点で50代後半(1928年生まれ)だった。世代的には、学生運動世代(全共闘、60年安保に分かれるが)よりもまだ上の世代。彼は、自分の子ども世代の団塊世代と孫世代に当たる団塊ジュニア世代を、引いた距離から見て本作を書いたのだろう。
この物語に登場する親世代は、戦後の民主主義教育育ち。小説版には、こんなやりとりがある。立てこもった中学生の1人が皆が秘密基地と呼ぶ廃工場を「サンクチュアリ」と名付ける。彼は、学生運動の用語だと仲間に説明する。ただ子どもたちは皆、親世代が全共闘世代とも呼ばれた学生運動の世代だということすら知らない。この生徒の両親は、学習塾の経営者という設定。運動に夢中になり、就職できずに起業を選んだのだ。元学生運動家が学習塾や独立系出版社を立ち上げるという話は、よく耳にする話である。
15歳の僕が映画を見たときにも、理不尽で横暴な教師たちから自由を求める少年少女の話だとは受けとめられたが、学生運動の子ども世代が親世代と同じことを追体験する物語だとは、すぐに気が付かなかった。なるほど親世代も自由を求めて戦っていたのか。『ぼくらの七日間戦争』は、子どもたちが横暴教師と機動隊を撃破して、花火を打ち上げて終わる。では親の世代の戦いはどのように終わったのか。
現実の運動は、いろいろな理由から下火になっていった。ただ成果もあった。多くの学校(主に進学校だ)で校則の自由化の流れが生まれていったという。だが学校が自由になったのか。むしろ逆。管理教育の時代が訪れる。ぼくらの世代は、その最後の方を経験した世代でもある。