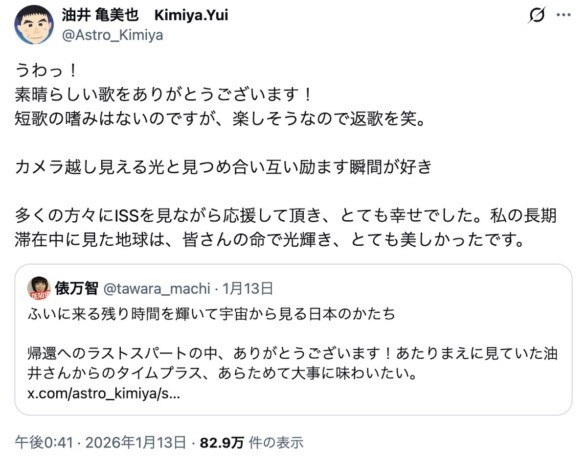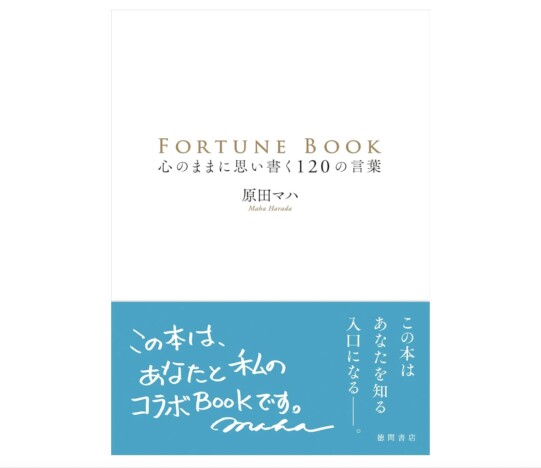「センスが良い」とはどういうことなのか? 哲学者・千葉雅也が提唱する、AI時代のセンスの磨き方

〈さて、実は、この本は「センスが良くなる本」です〉。そんな大胆不敵な謳い文句から、哲学者・作家の千葉雅也が、芸術を自由に楽しむセンスの身につけ方を論じた芸術入門。それが本書『センスの哲学』(文藝春秋)である。
芸術に限らず、さまざまなジャンルや場所で「センス」という言葉は使われている。だが、そもそもセンスとは何を指しているのか?センスの良し悪しとはどういうことか?という所から、センスを良くするための話は始まる。
辞書的な意味を総合すると、センスは「直感的にわかること」と定義できる。著者はその定義の裏にある価値観を疑ってみる。「センスがいい」で世間がイメージするのは、たとえば絵画なら「本物そっくりに描ける」といった能力を指すだろう。だがモデルにいかに近づけるか上手い・下手が評価の指標となると、昔から作品に触れてデータを蓄積している、文化資本に恵まれた人が有利となりやすい。
ならば既存の土俵ではなく、別の土俵でセンスを磨けばいい。著者は土俵を移すために、「センス=ものごとをリズムとして捉える」という定義を新たに持ちだしてくる。作品や事象を音楽のリズムのように捉えて、複数の要素の並びや出てくるタイミングを面白がれる。それが本書において、センスの良さとなる。たとえば、こんな具合に……。
〈まず、餃子を口に入れたときに熱の感じがある。熱い。表面のパリッとした感じ。噛むと、皮が割れて中の柔らかい部分へと進むわけですね〉〈タレのことも忘れてはいけませんね。醤油の味がメインなんだけれども、酢の酸味と鼻にツンとする感じがあり、ラー油の辛みもある……(略)強い「バンッ」と弾ける刺激と、より穏やかな「ツー」とでも言えるし持続的な刺激がリズムになる。「バンッ、ツー、バンッ、ツー……」みたいな感じですね。餃子のリズムは複雑で、多層的に絡み合って展開していきます。音楽ですね。餃子は音楽なんですよ〉。
著者が披露する、出身地である宇都宮名物の餃子を使った「ものごとをリズムとして捉える」の例はユニークな漫談のようで、真似をして自分の好きな食べ物とリズムの関係性を文章にしてみたくもなる。こうしたセンスであるとか、芸術・哲学といった高尚にも感じるような事柄を、身近な物と結びつけて説明してくれる親しみやすさは、本書の大きな魅力の一つだ。
身近といえば、我々の生活に欠かせなくなりつつあるAIが、センスに与える影響についての話題も興味深い。AIに大量のテキストや画像を学ばせてうまくパラメータを設定すれば、センスのいい作品はおそらく生成可能であるという。鑑賞する側は、それをリズム的に捉えて楽しむこともできてしまう。そんな現代においてもAIが生成できない、芸術に含まれる要素として著者の挙げるのが、人間の「どうしようもなさ」である。
倫理や規範意識からはずれた悪の部分。特定のものごとへの執拗なまでのこだわり。その人の生活からにじみ出る野暮ったさ。人に不快な印象を与えるかもしれないが強烈な引きにもなる「どうしようもなさ」を抱える一方で、正しくあろうセンス良くあろうともする作り手のジレンマ。そこから作者独特のリズムを持つ、真のセンスが生まれる。
だからといって、突飛さや露悪的なものを目指せばいいというわけでもない。狙ってしまうとそれはそれで類型的になってしまうのだから、ピカソやゴッホのように個性のある絵を描くというのは、仕組みがわかってもすぐに実践は難しいかもしれない。とはいえ、芸術は作ることだけがすべてではない。すでにある作品を、じっくり何度も鑑賞して楽しむという選択肢もある。