“トンデモ日本史”で賛否両論の『将軍』なぜドラマ化に成功? 世界観で圧倒する“新しい時代劇”の可能性
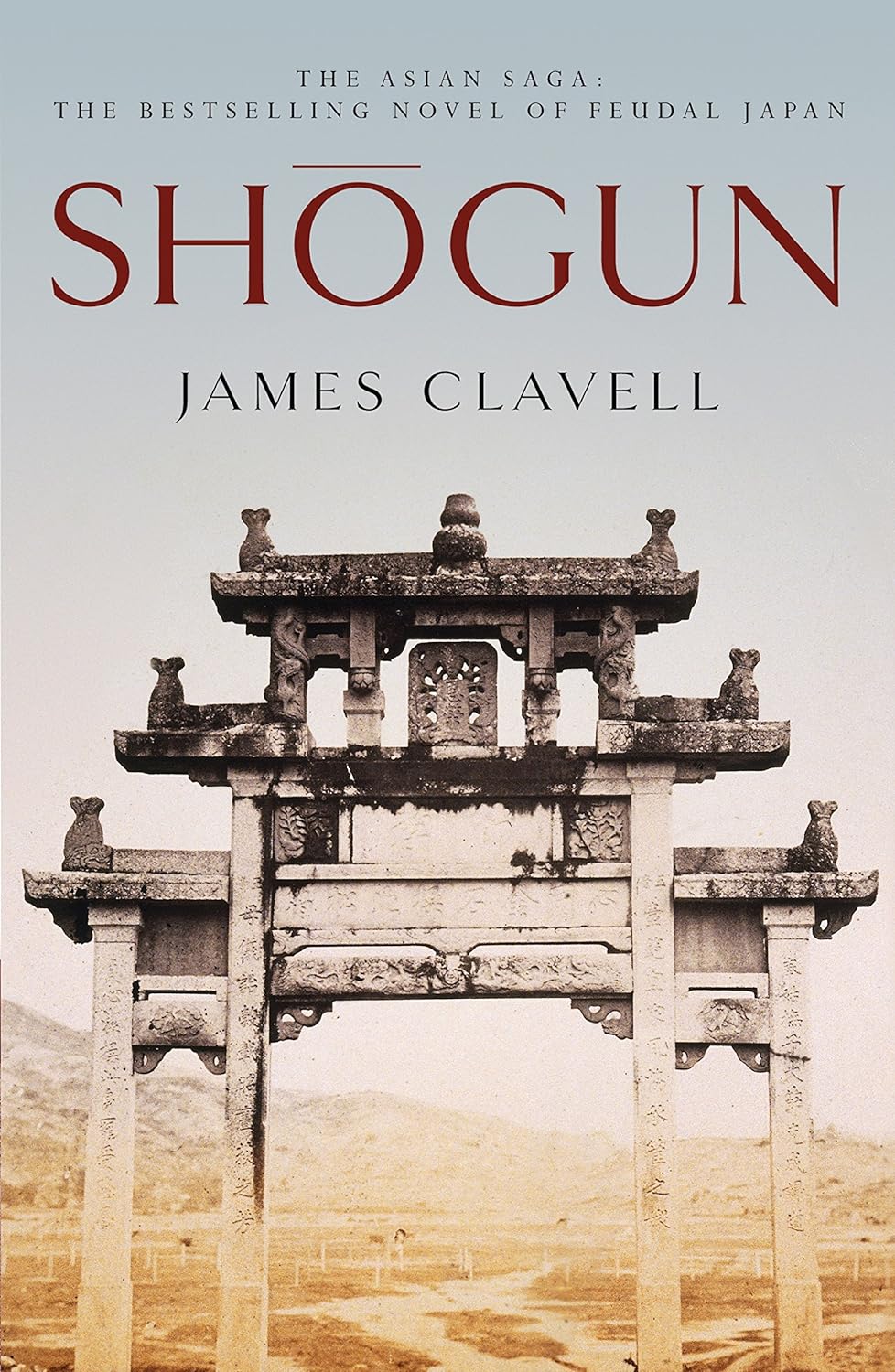
歴史・時代小説ファンとして、事前段階から大いに注目していたし、実際大きな期待も寄せていたけれど、これほどまで「解像度」の高い映像作品になるとは、正直思っていなかった。いわんや、それが結果的にこれほどまで、本国アメリカをはじめ世界各国で高評価を集める作品になろうとは。現在ディズニープラスの「スター」で独占放送中であり、この23日に日本でもいよいよ最終回を迎えようとしているドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』のことだ。
本作の原作は、ジェームズ・クラヴェルが1975年に発表したベストセラー小説『将軍』だ。1980年には、アメリカでドラマシリーズ化され、これが空前の大ヒットを記録。同年、その日本版が出版されると同時にドラマのダイジェスト版が日本でも劇場公開され、さらにその翌年にはドラマシリーズの放送が日本でもスタートするなど、大いに話題となった作品だ。しかしながら、それが海外と同じように日本で受け入れられたかというと、案外そうでもなかったのではないだろうか。なぜなら、そのドラマの内容が、「関ヶ原の戦い」前夜の徳川家康(と、その家臣となったイギリス人、ウィリアム・アダムス/三浦按針)をモチーフとしながらも、我々日本人の多くが知っているそれと、大きく異なっていたからだ。
もちろん、歴史・時代小説は、多かれ少なかれ、すべて「フィクション」である。なので、その細部に目くじらを立てるのは、この場合は少し違うだろうとは思いつつ……そこにはやはり、限度というものがあるのだ。無論、多くの歴史・時代小説がそうであるように、それが発表された「時代」も、そこには大きく関係しているのだろう。80年代の初め頃、海外の人々の日本に対する興味は、確かにそこにあった。不思議の国、ニッポン。それが西欧的な価値観と違えば違うほど、彼/彼女たちは、ますます興味をそそられたのだろう。そこに多少の「誤解」や「誤読」があろうとも。「征夷大将軍」である以上に、この国の覇者としての「ショーグン」を見たいのだ。しかしながら、今回のドラマ版に関しては、どうも様子が異なるのだ。海外からの評価はもちろん、ここ日本においても、本作の評価は非常に高いように見受けられるのだ。実際、筆者も毎週楽しみに観ている。一体何が違うのだろうか?
その「プロット」は、思いのほか原作を踏襲したものとなっている。1600年、日本に流れ着いたイギリス人航海士「ジョン・ブラックソーン/按針(コズモ・ジャーヴィス)」は、五大老のひとりである「吉井虎永(真田広之)」の庇護を受け、やがてその家臣となる。しかし、虎永を取り巻く情勢は、五大老の筆頭格である「石堂和成(平岳大)」の策謀によって、悪くなる一方だった。亡き「太閤」の側室であり、そのお世継ぎの母である「落葉の方(二階堂ふみ)」を味方につけた石堂は、真綿で首を締めるように虎永を追い込んでいく。一方、虎永の命を受けて通詞となった「戸田鞠子(アンナ・サワイ)」との交流を深めながら、この国の情勢や価値観を徐々に理解し、自らの生きる道を模索する按針。彼らの運命は、果たしてどこに行き着くのだろうか。
「プロット」は、ほぼ同じ。しかしながら、今回のドラマ版は、その「ナラティブ」を大胆に変更しているのだった。西欧人が感情移入しやすいキャラクターとして主人公に設定された「語り部」ジョン・ブラックソーン/按針を、今回のドラマ版では一歩引いた場所に置き、彼が見た「不思議の国ニッポン」という構図ではなく、やがて彼も深く関わることになる虎永を中心とした諸勢力の駆け引きという「ドラマ」部分を、今回のドラマ版では、より前面に押し出しているのだ。その意味で本作は、原作や以前のドラマ版、あるいは日本人が慣れ親しんできた「時代劇」よりも、むしろジョージ・R・R・マーティンの小説及びそれをドラマ化した『ゲーム・オブ・スローンズ』に近い印象を受けた。「王座」をめぐる諸勢力の戦いだ。しかし、それ以上に今回のドラマ版に関して多くの人々が驚かされたのは、冒頭にも述べたように、その世界観の「解像度」の圧倒的な高さなのだった。美術をはじめとする、その作り込まれた世界観の細やかさとスケール感は、我々日本人にとっても初めて見たような、実に衝撃的な仕上がりとなっているのだった。























