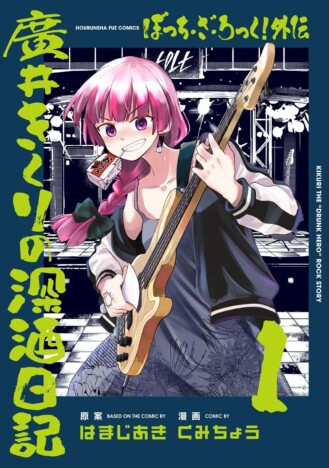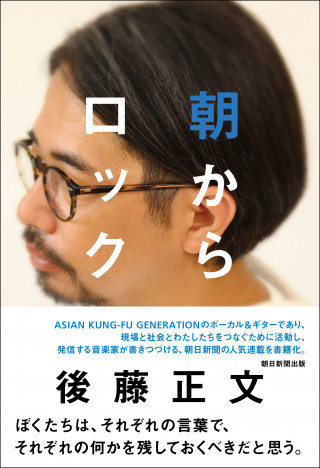日本のライブの灯を絶やさぬためにーー「新宿ロフト」多くの人気ロックバンドを生み出した創業者の“信念”

時々SNSなどで、ライブハウスの「内輪ノリ」を批判する声を見かけることがある。
たしかに、狭いコミュニティの中だけで満足し切っているような、ましてや、自分たち以外の存在を認めようとはしないバンドとその取り巻きなどは、私もあまり好きではない。だがその一方で、新しい表現を模索しているミュージシャンたちや、その姿勢に共鳴する人々が集う“場”として、ライブハウスはいまでも充分機能しているのではないかとも思っている。
誤解を恐れずにいわせていただければ、そういう“場”がなければ、時代を変革するような表現は生まれないともいえるのだ。
たとえば、日本のパンクムーブメントの仕掛人の1人でもある、写真家の地引雄一はこう語っている。
僕なんかもそうだけど、カメラをやっている奴やデザイナー、ミニコミを作っている人、そしてこういう音楽を求めてライブ会場にやってくる観客の人たち、それらの総体が東京ロッカーズだったんじゃないかと思う。いち音楽のシーンに限らず、ファッションや文化全体を含め、ライフスタイルの変革こそがあの頃は一番重要なことだった。(後掲書より引用)
「東京ロッカーズ」とは、リザード(紅蜥蜴)、ミラーズ、ミスター・カイト、S-KEN、フリクションという5バンド(およびその周辺のバンド)のことだが、70年代末から80年代初頭にかけて、彼らが起こしたインディペンデントなムーブメントが、日本のパンクの「起点」の1つだといわれている。
そして、それは日本のパンクの始まりであるだけでなく、ある意味では後の「インディーズブーム」(80年代半ば)や、「バンドブーム」(80年代末〜90年代初頭)の原点でもあり、そんな彼らの活動を陰で支えたのが、1976年にオープンした新宿ロフトをはじめとした、いくつかの伝説的なライブハウスだったのは間違いない。
日本のライブの灯を絶やさぬために
先ごろ刊行された平野悠の『1976年の新宿ロフト』(星海社新書)は、ライブハウス「ロフト」創業者である著者が、新宿ロフトオープン前後の日本のアンダーグランドのロックシーンを振り返った、すこぶる面白いドキュメンタリーだ(前述の地引雄一による写真も数多く収録されている)。
いや、より正確にいうならば、「日本のアンダーグラウンドのロックシーン」というか、当時はロックそのものが、(一部の例外的な存在を除き)日本の音楽業界ではまだまだマイナーなジャンルだった。じっさい新宿ロフトも、オープン直後はロック系のバンドよりも、ニューミュージック系(いまでいうシティポップ系)のアーティストの出演がメインであり、書名にもなっている「1976年」に行われた10日間にわたるオープンセレモニーでも、どちらかといえば後者の顔ぶれの方が目立っていた。
だが、しだいに同店はロック色(パンク色)を強めていくことになる。きっかけとなったのは、「DRIVE TO 80’s」という東京ロッカーズ系のバンドが多数出演したイベントだったようだが、それまでの動員記録を更新した同イベントを経て、ブッキングされるバンドの主流は徐々にパンクを中心としたロック系へと切り替わっていく。
その結果、新宿ロフトは数々の伝説的なロックバンドの「根城」になり(有名なところでは、BOØWY[暴威]やザ・ブルーハーツなどが初期の活動の拠点にしていた)、80年代半ばには「ロックの聖地」の1つとして知られるようになったわけだが、先ほども述べたように、もともとバンドブーム以前のロックは基本的にはマイナーな、すなわち「ビジネスに結びついた音楽」とはいい難く、また、90年代には「立ち退き騒動」に巻き込まれるなど(1999年、新宿ロフトは西新宿から歌舞伎町へと移転した)、常に順風満帆な経営だったというわけでもない。