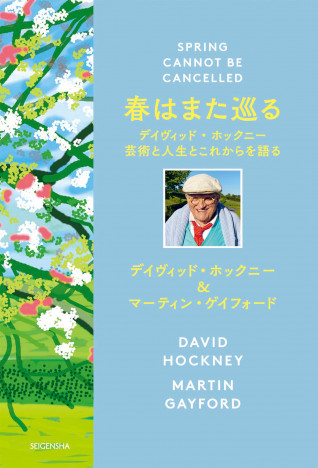宇野常寛×福嶋亮大が語る、Web3と批評的言説のこれから 「人類社会の“時差”を意識することが重要」

ヨーロッパの行き詰まり、アジアの歴史の動き

宇野:福嶋さんの『書物というウイルス』は、要するにいま、本来トランジット、つまり未知の何処かに接続できる可能性を示唆する場所であるべき書物が、情報環境的に行き先が確定している飛行機の機内として受け止められるようになってるという状況認識があり、そのトランジット性を書評という行為で回復しようという試みだと思います。
これは、今の時差の話と通ずるものがあります。一言でいうと、トランジットたりえるものは何かという話だと思うんです。結局、グローバリゼーションが進み、情報技術が発達した現代においても、実際には人間は主観的な時間を生きていて時差がある。それをないかのように振る舞うことによって、いろいろな齟齬が起きてくる。その時差を自覚できる装置が社会には必要です。
そして、本を通して言葉でコミュニケーションするということは、時差を自覚できる装置を担ってきたはずであると。では、何を考えてどのようにアプローチすれば、トランジット性を確保できるのか。僕はこの本を読みながらずっと考えていました。
福嶋さんはマイケル・サンデルやスティーブン・ピンカーを建設的に批判しながら紹介しています。そのなかで思想の言葉と現実をシンクロさせようという動き自体が、非常にプラットフォーム的で時差をなくしてしまう思考だとしている。哲学や思想の言葉が世界から時差をなくして、むしろ現実のきしみを生み出す方向に働いている。
哲学はいろいろな潮流があるから一概には言えないけど、少なくともマクロには読者にむしろそういう語り口が支持されるようになっている。そこでどう抵抗するかというのは、この本の隠れた問題意識ですね。忘れ去られた作家の小説を読む。ある種のアートのあり方を個別に議論する。哲学に対して文学やアートの優位がどこにあるかというと、まだトランジット性を担保しやすい状況にあるということなんですよね。
福嶋:そうですね。哲学も今は業界ごとに細分化されていて、フランス哲学が専門の人はピンカーやサンデルやフクヤマにはたいして言及しないでしょう。それで、いつまでたっても現代思想はフランス中心という認識が温存されている。僕としてはそれに大いに不満があって、中華圏の現代思想を紹介した『ハロー、ユーラシア』(講談社)を書いたり、今回の『書物というウイルス』みたいに「21世紀思想」という括りを試したりしたわけです。
あと、哲学自体はもちろん重要なんだけれど、おっしゃったように哲学という言葉の魔術もあるわけですね。今は哲学が簡単にブランディングの道具になっちゃうんで、とりあえず何でもかんでも哲学を表題につける時代になっている。実はカントの時代にも似たことがあって、かなりイージーに哲学という言葉が使われていたらしい。「哲学という名称の装飾的な使用がモード」になっていたというのね(「哲学における最近の高慢な口調」)。カントはその濫用に嫌味を言っている。
宇野:たとえば、ハラリは現在のリベラル知識人の像の最小公倍数のようなものに過剰適応していて、逆に何も言えなくなっていますよね。一方でウエルベックみたいに出口がないことをわかっていると、知性と教養をひけらかしながらSNS的なおしゃべりを無限に生産するだけになる。ハラリ的な限りなくWHOの公式発表に近いスピーチに、ウエルベック的なSNSのおしゃべり。その2つで引き割かれていると思います。
福嶋:そうですよね。ウエルベックの『セロトニン』で割と面白かったのは農業の話です。フランス人のアイデンティティの危機をどう小説のなかで処理するかというときに、農業の荒廃からアプローチするのはうまいと思いました。ただ、結局ヨーロッパの知識人はこの100年間、自分たちの文明はどん詰まりだとずっと言い続けている。そのシニシズムの行き着いた先がウエルベックなんだと思いますね。
一方でアジアは、どん詰まりのヨーロッパと違って、良くも悪くも歴史が動いているでしょう。ひどいことが起こる可能性も高いけれども、その錯綜した状況を思想的な資源に変えていけばいいと思う。あと、時差の問題と関わるけど、東アジアの内部のなかにも複数の時計があるわけです。
たとえば、台湾や香港や日本はいわば「ユーラシア的」でヨーロッパとアジアがある程度融合している。それに対して、これは恩師の金文京さんの受け売りですけど、朝鮮半島はヨーロッパの影響を相対的に受けていない。それが一因となって、韓国はBTSみたいに一気にアメリカにジャンプしてグローバルな成功を収めたりするし、北朝鮮は前近代的な枠組みを残していたりする。これまで日本と中国の比較は数多くなされてきたけど、台湾、香港、朝鮮半島まで視野に入れると、それぞれの異質な歴史が浮かんでくるわけです。その複数性があるから、東アジアはフクヤマ的な「歴史の終わり」には辿り着かない。
宇野:ウエルベックの自己憐憫が象徴するヨーロッパの行き詰まりを横に見ながら、アジアにおいては戦略的に時差を維持する方向に行くべきじゃないかと。
福嶋:そういうことですね。維持すべきというか、結果的にそうなっているという気がする。もちろん、日本をはじめアジアの状況もきついんですけど、はたから見ていると、ヨーロッパもイギリスを筆頭に大丈夫なのだろうかと思いますね。
そう言えば、エマニュエル・トッドの新しい翻訳(『我々はどこから来て、今どこにいるのか?』もとは2017年の著作)を最近読んだんですが、エリート的なものと大衆的なものの偉大な和解を実現させ、健全な保護貿易への道を開いたっていう理由で、当時のイギリスのブレクジットを評価している。でも、日本語版のあとがきによると、イギリスは今や危機に陥り、ブレクジットは失敗したと(笑)。トッドみたいに家族人類学で政治を裁断するのは、ユニークではあるけれど、それだけでは無理ですね。
あと、最初の話につなげると、東アジアにはもともと砂漠的な感受性が希薄だと思うんですね。そこもヨーロッパとの違いかもしれない。フランスの歴史家フェルナン・ブローデルが昔言ったことだけれど、ヨーロッパの地図を南北逆さまにすると、頭の上に巨大なサハラ砂漠が乗ることになる。その砂漠の影響をいかに遮断するかが、ヨーロッパの多様性の成立する鍵だった。そういう環境から逆にロレンスのように砂漠に憧れる人が出るのは、よくわかるんです。他方で、東アジアにおいては、宇野さんが最後に書いているように、心の内側にしか砂漠はないのかもしれない。