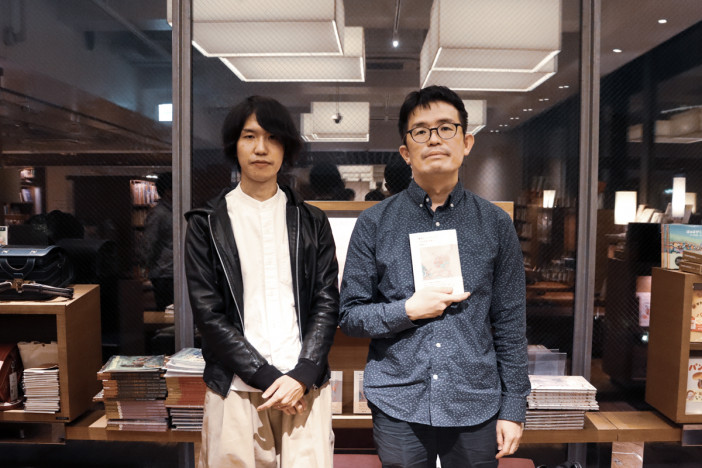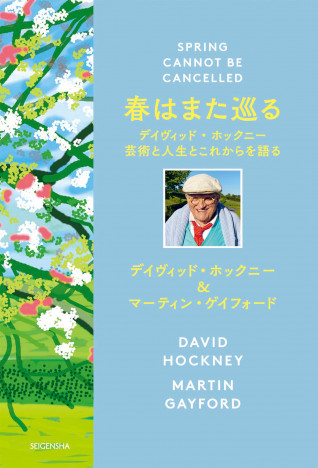宇野常寛×福嶋亮大が語る、Web3と批評的言説のこれから 「人類社会の“時差”を意識することが重要」

WEB3に必要なのは「時差」
福嶋:ところで『砂漠と異人たち』はインターネットの現況への批評でもあるわけですね。
宇野:たとえばWeb3については、僕も単純にワクワクしています。だからこそ、考えることもたくさんある。たとえばこの本はWeb2.0への批判から始まっているのですが、その根底にはSNSの普及以降に散見される「こんなはずじゃなかった。僕らのインターネットを取り戻そう」という発想がある。これはまさにWeb3の推進者の問題意識ですね。本来は自律分散的なインターネットが、SNSプラットフォームの実現によって、事実上のボトムアップの中央集権になってしまったからです。ブロックチェーン技術を応用することによって、技術的に中央集権を解消し自律分散に近づけるというのがその骨子です。もちろん、それは素晴らしい。しかし、考えてみればそもそもWeb2.0もその当初は十分に自律分散的だったはずです。しかしそれがこうなってしまったのは、むしろ人間のつながりたい欲望が、ボトムアップの中央集権の装置を支持したからなのは間違いない。僕はこの流れに期待するからこそ、この問題を過小評価しないほうがいいと考えます。
Web3周辺の人のなかには、こういった「べき」論はWeb3という運動にブレーキをかけるので「するべきではない」という人がいたりする。要するに、未来への期待によってお金を集めている今日の金融資本主義というか、スタートアップカルチャーの論理に従うとこうした人文社会科学的な、文化論的な「べき」論は邪魔だ、というわけです。僕はこうした言説が「出てきてしまう」ことのほうが問題だと思う。それはまさにハンナ・アーレントが帝国主義について指摘した問題と同じです。植民地のヨーロッパ人にナショナリズムはむしろ希薄で、純粋にその土地を開発し、版図を広げる「グレート・ゲーム」のプレイに純粋にアプローチすればするほど、その自己拡張のシステム自体には無批判になってしまったのがその特徴です。今でも全く同じことが繰り返されていて、何も新しくなっていない。
福嶋:そうなると、ねずみ講やバブルと大差ないですからね。全体主義だし、全体主義としても劣化している。先日、樋口恭介氏と対談したときにも言ったんですが、ウェブの進歩そのものもそろそろ飽和しつつあると思うんです。だからこそ、むりやり時計の針を進めて、前に進んでいるという幻想で駆動しようとするムードになっている。でも、そういう無理を重ねても、金儲けしか頭にない悪徳なプレイヤーが増えて場が荒廃するだけじゃないかな。
僕はWeb2.0には失敗が多々あったと思います。今からもしやり直せるならば、SNSはたぶん発明しない方が良いでしょう。その失敗は結局、企業に理念がないことと関係している。Googleだって建前上は“Don't be evil”とか言っていたわけだけど、最近はそれすら言わなくなった。ウェブが人類にとってどんな意味があるかを検証せずに、ビジネスとか動員の話ばかりになっている。根本的な議論を省略したまま、Web3というプロパガンダでとにかく加速を演出しようという感じ。
宇野:Web2.0の前半まではジョブズが生きていて、60〜70年代のヒッピーやカウンターカルチャーの遺伝子がまだ残っていました。僕はどう考えても、Web2.0をやり直すことが必要だと思っています。
今はGoogleの検索結果は広告ページばかり、SNSの検索結果はタイムラインの潮目しか表示されない。要するに、検索しても「みんな」の欲望や顔色しか分からない。検索によって、どこにでもいけなくなってしまっている。つまり、深夜に暇な大学生が好きな作家について書きなぐったような長大な感想文に出会って、それをうっかり読み込んで夜更かししてしまって後悔するような体験がなくなっているわけです。でも、そういうものこそが実はインターネットのいちばんの可能性だと思います。だから、そこをどうやってアップデートするかを考えなきゃいけない。
福嶋:それとも関わるけど、前に宇野さんと対談したときに言ったように、結局のところ大事なのは「時差」を意識することだと思うんです。グローバリゼーションというのは、要するに人類の時計を一つにしてしまおうという運動ですね。フランシス・フクヤマの「歴史の終わり」論は、それを哲学的に裏付けようとしたものです。しかし、ロシアや中国は明らかに別の時計を持っている。人類の時計は当分一つになんてならない。日本国内を見ても、統一教会やその信者は別の時計を持っていて、そこで起きたトラブルが元首相の暗殺みたいな事件に飛躍したりする。
人類社会は時差に満ちている。その時差がないかのように社会を組織しようとしても、結局はうまくいかないんです。宇野さんが指摘するような深夜のネットサーフィン体験は、いわば別の時間を生きているようなもので、そういう時差への感覚を研ぎ澄ますことが重要だと思いますね。