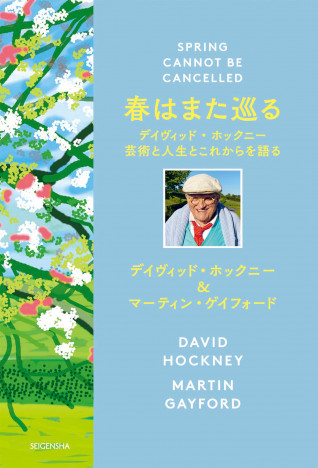宇野常寛×福嶋亮大が語る、Web3と批評的言説のこれから 「人類社会の“時差”を意識することが重要」

評論家の宇野常寛が、10月20日に『砂漠と異人たち』(朝日新聞出版)を刊行した。「情報社会を支配する相互評価のゲームの〈外部〉を求め、『僕』は旅立った」としながら、村上春樹、ハンナ・アーレント、コリン・ウィルソン、吉本隆明、そしてアラビアのロレンスなど先人たちの仕事を、現状のインターネットを取り巻く状況と照らし合わせながら論じている。
宇野と旧知の仲で数々の対話を重ねてきた批評家・福嶋亮大もまた、10月12日に新刊『書物というウイルス 21世紀思想の前線』(blueprint)を刊行している。この10年間に日本で刊行された文芸書および思想書を主な題材として、思考の《現在地》を描き出すことを目指した書評集だ。ミシェル・ウエルベック『セロトニン』、マルクス・ガブリエル『新実存主義』、村上春樹『ドライブ・マイ・カー』、劉慈欣『三体』、スティーブン・ピンカー『21世紀の啓蒙』など、多岐にわたる書物が縦横無尽に論じられている。
WEB3という言葉で新たなテクノロジーが褒めそやされる今、批評的言説はいかにして可能なのかーー。二人の著作で取り上げられた人物や書籍を起点に、批評やインターネットのこれからの可能性について対談してもらった。(編集部)
ロレンスはずっと変身を重ねて、同時に失敗を重ねてきた

福嶋:『砂漠と異人たち』は面白かったですが、まさかT・E・ロレンス(編注:アラブ民族独立に尽力したイギリス陸軍将校)のことをこんなに熱烈に書いているとは知らず驚愕しました(笑)。考えてみると、デヴィッド・リーン監督の映画『アラビアのロレンス』は最初にロレンスのバイク事故のシーンから始まるけど、いわばロレンスって仮面ライダーみたいな人ですね。ロレンスは変身に変身を重ねてアラブの独立にもコミットするわけだけど、それが同時に失敗の連鎖でもある。失敗が同時に成功であるという逆説の人だと思います。『リトル・ピープルの時代』などで仮面ライダーや変身のテーマを論じてきた宇野さんが、ロレンスを取り上げる意味はよくわかりました。
宇野:この本ではロレンスを近代人の「外部」へのロマンティシズムをもっともラディカルに追求した人物として、象徴的に取り上げています。ロレンスは『知恵の七柱』だけではなく、膨大な手記や書簡を遺していますが、そこから伺えるのは彼は愛国者でも、当時の植民地のヨーロッパ人にしばしば見られた冒険家的なメンタリティの持ち主でもなく、非常に内面的な動機で砂漠に赴いたということです。その動機はとても複雑なのですが、強いて言えばいわゆるロスト・ジェネレーション的な当時の欧米の若い知識人層や文化人に見られた脱社会志向を、それこそもっともラディカルに実践したというのが一番近いと思います。そして重要なのは、その結果として彼は自己の救済に失敗したことです。要するに、メディアの中で英雄「アラビアのロレンス」になってしまったことで、彼はどこにも行けなくなってしまった。その後、彼は内部にとどまり、そして「変身」を繰り返そうとする。具体的には変名を用い、一兵卒として軍に勤務しながら、スピードとマゾヒズムに耽溺する。しかし、やはり彼は救われなかったと思われる。
この、徹底して外部を求めた結果として、もっとも閉塞した場所にたどり着いていまう……というロレンスが陥った逆説は、僕には今日のインターネットが重なって見えるわけです。革命を断念し、世界ではなく世界の見え方を変えることを選んだアメリカ西海岸のヒッピーたちの、探求手段の一つだったコンピューターカルチャーが生み出した、究極の外部=フロンティアがインターネットだったのですが、いまこのインターネットがいちばん人間を不自由にしている。だからこそ、僕たちはロレンスがどうすれば「変身」できたのかを考える必要がある。これがこの本の中心になる「アラビアのロレンス問題」です。
……なんてのは、本を書くというときに考えたことで、僕はロレンスと「外部」というテーマについていつか書こう、とずっと思っていたんです。最初にロレンスのことを知ったのは、高校の世界史の授業で、先生に映画の『アラビアのロレンス』を勧められたときです。それで夏休みにTSUTAYAでなんとなく手に取ってみたんです。
福嶋:1962年の映画ですね。砂漠で変身を重ねながら、最後は加速するバイクから吹き飛んで、ある意味で無残な死を迎える。そのストーリー自体が、その後のヒッピーカルチャーを先取りしていたと思うのね。たとえば、1969年には映画の『イージー・ライダー』があるし、日本でもヒッピーとは言い難いけれど『スローなブギにしてくれ』(1976年)の片岡義男のようにバイクに憑かれた作家が出てくる。テレビ版の仮面ライダーも70年代ですね。万博に象徴される国家的な成長のストーリーが飽和したところに、マシンを通じた意識や身体の変性のテーマが出てくる。ロレンス論はそういうサブカルチャーの文脈を改めて考えるきっかけにもなるし、意外性もあって面白く読みました。
宇野:20世紀は総力戦の世紀であると当時に、エンジンによる身体拡張の快楽に人類が取り付かれた時代です。ロレンスは砂漠という外部に接続しても救われなかった代償として、戦後にスピードに取り憑かれていく。要するに、身体拡張の快楽が失われた外部を埋め合わせていた。70年代という政治の季節が退潮後のタイミングで自己解放のアイコンとしてオートバイが劇映画でやたらと用いられていたわけですが、ロレンスの人生はその問題を先取りしていたのかもしれませんね。
福嶋:よくわかります。ロレンスというとても良い素材が発掘された気がします。あと映画版の監督のデヴィッド・リーンもなかなか面白くて、スティーヴン・スピルバーグもいわばポスト・リーンの監督として位置づけると色々クリアになると思う。
例えば、スピルバーグ監督の『未知との遭遇』(1977年)はメキシコの砂漠のシーンから始まって、やがてオタクっぽい主人公がUFОと遭遇する。最終的には、フランス人のフランソワ・トリュフォー演じる科学者に見送られて、主人公が家族を置き去りにしてそれに乗り込むわけですね。あれは『アラビアのロレンス』への応答になっている。リーンないしロレンスが非ヨーロッパ的な砂漠に外部を求めたとすると、スピルバーグは砂漠を宇宙に変換したわけです。そもそも、暗闇の中でピカピカ光るUFОっていうのは、要はシネマのメタファーでしょう。スピルバーグはあのピカピカにやられて、宇宙人ないしシネマへと飛躍してゆく。『アラビアのロレンス』を基準点にすると、それ以降のスピルバーグたちがどこに外部を求めたかが明快になると思います。
宇野:僕がスピルバーグで良かったと思う作品は、『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』(2002年)、『宇宙戦争』(2005年)、『ミュンヘン』(2005年)など、ゼロ年代前半の作品です。要するに、この頃は近過去やSFを描きながらも、虚構を通して同時代のアメリカと格闘しているわけです。『ミュンヘン』はブラック・セプテンバーの話なんだけど、近過去のことを描きながら同じことが『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』や『宇宙戦争』でも言えますね。
ただ、そこから先のスピルバーグは、『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』(2011年)、『戦火の馬』(2012年)、『リンカーン』(2012)など、言ってみれば自分が肯定できるアメリカの、都合よく漂白された正の歴史をファンタジーとして描くようになった。一言で言えば、司馬遼太郎みたいになってくるんですね。これは言ってみれば、偽史によるヒーリングで手法的にもCGの支配力が高くなっていく。
福嶋:同感です。スピルバーグの『E.T.』(1982年)のラストで宇宙人が“come”というのに対して、エリオット少年は“stay”と返す。『未知との遭遇』の主人公とは違って、地球にステイして頑張るよ、ということでしょう。それで90年代以降のスピルバーグは、ある意味で愚直にアメリカ史や人類史を回顧し始めるんだけど、ここ十年はそれもかなり煮詰まっている気がしますね。その点では、歴史の流れが壊れている、というか歴史そのものがトラップだというイギリス人監督のクリストファー・ノーランのアプローチのほうが面白くなっている。
宇野:一方でこの本で取り上げた村上春樹は、同じような問題に直面していたはずだけれど、その道を歩まなかった。要するに、ロレンスの生きた時代にはまだ、それが偽物だと分かっていたとしても「外部」という幻想が機能していた。しかし、第二次大戦後にその幻想は縮退していく。この本でも取り上げた三島由紀夫は、そのことに感づいていたからこそロレンスに嫉妬し、彼を批判したのだというのが僕の理解です。三島は戦争に間に合わなかったことの代償を、文学への動機の一つにしていたのだけど、そのせいで外部に触れたとしても救われないこと、外部を求めてしまうこと自体が罠であることに気づかなかった。対して、70年代の終わりに作家活動をはじめた村上春樹は、マルクス主義という最後の外部が退潮したあとの世界から出発しているところにアドバンテージがあったと思います。
福嶋:なるほど。三島由紀夫は晩年の四部作『豊饒の海』で、日本の近代史を偽史としてやり直そうとしたわけですね。最初は貴族の美青年の話から始まり、それがなぜかタイ人の王女に転生して、最後は主人公らしき青年が実は偽物だったということが判明する。それで、あとには空っぽの庭だけが残る。まさにロレンス的に変身を重ねていく話で、しかもロレンスよりも悲惨です。それが宇野さんのおっしゃる「間に合わなかった」という問題と関係するでしょうね。
村上春樹のテーマは、もともと三島の隘路をどう抜けていくかにあった。それで90年代には、同世代のスピルバーグと同じく、歴史というか偽史にコミットするわけですね。でも、それを象徴するはずの『ねじまき鳥クロニクル』では、満州とかノモンハンとかの歴史の話は前半に集中していて、後半になると歴史はほとんど蒸発してしまう。その代わりに、行方不明の妻と出会う、というか出会い損ねるという神話的なテーマが前面に出てくる。
『書物というウイルス』に収録した濱口竜介/村上春樹評でも書きましたけど、『ねじまき鳥クロニクル』は共同幻想が故障しているのを何とか修復しようとしているうちに、対幻想のほうがおかしくなって、最終的には修復できないところにいってしまったという話だと思うんです。そういう幻想のスライドのさせ方が、良くも悪くも面白いアプローチではあった。
宇野:村上春樹は吉本隆明を意識していたはずなんだけど、だからこそ絶対に距離を取っていたところがあると思います。『共同幻想論』はあくまで、『遠野物語』と『古事記』をテキストにした彼の提唱する自己幻想、対幻想、共同幻想の関係を記述したものなのだけれど、当時の若者たちはむしろ吉本のプレゼンスの生む、メタ・メッセージを中心に受け止めていた。要するに、共同幻想に対抗するために「対幻想に依拠することでの自立を模索する」ということです。
村上春樹は、しかしそことも距離があり、あくまで「個」であることに拘泥していた。それが変化するのが、『ねじまき鳥クロニクル』でデタッチメントからコミットメントへ変化し、歴史に対して距離感を表明しなければいけなくなったからか、対幻想に依拠することになった。僕はここがターニングポイントだったと思う。一言で言えば、直子を断念する自己幻想の作家だったのが、直子を再召喚する対幻想の作家になった。
福嶋:言ってることとやってることがズレてったんでしょうね。