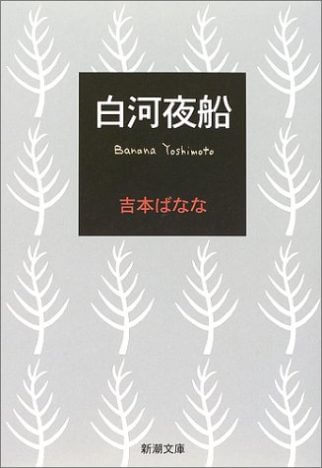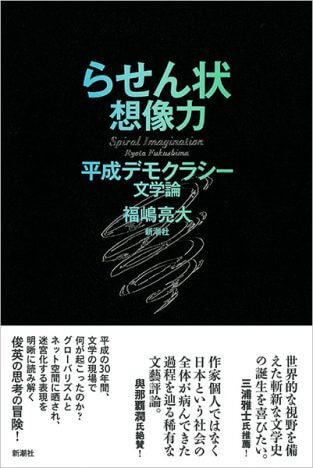福嶋亮大に聞く、中華圏における現代思想の大変動 「2010年代半ばはアジア政治史の重大なターニングポイント」

中国文学者・批評家である福嶋亮大氏の書籍『ハロー、ユーラシア 21世紀「中華」圏の政治思想』(講談社)は、21世紀のユーラシアにおけるイデオロギーがどのような状況にあるのかを、「ユーラシア大陸を横断する巨大な帝国の成立=中国」と、「アジアとヨーロッパの文化的混血に根ざしたハイブリッドな自我の創造=香港」という二つのテーマを軸に読み解いた画期的なエッセイだ。
中国の大国化、香港の大規模デモ、さらにパンデミックに到る東アジアの政治的な暴風域などについて著された本書は、深刻かつ複雑な状況を迎えているユーラシア大陸の今を知る上で必読の一冊といって良いだろう。
中国の天下主義、香港の本土主義といった重要なキーワードについてを中心に、福嶋亮大氏に話を聞いた。(編集部)
中立的な立場であることはもはや難しい
――『ハロー、ユーラシア』は、日本ではあまり馴染みのない中華圏の現代思想を通して、現代が大きな歴史の転換点にあることを改めて認識させられる一冊でした。昨今の緊迫した世界情勢について考える上でも、本書の視点は意味のあるものだと感じます。本書の狙いを改めて教えてください。
福嶋:日本で中華圏というと経済や政治の話題が中心になりがちですが、当然ながら人文系の思想も存在しているわけです。しかも、中国の現代思想は2000年代に入って大きな変動を迎えていた。それは一言で言うと「政治的転回」です。『ハロー、ユーラシア』では、中国の「天下主義」と香港の「本土主義」をそのポリティカル・ターンの両翼として捉えています。日本には中華圏のイデオロギー状況に関する本がほとんどないし、中国の現代思想もあまり体系的に紹介されていないので、書く意味があると思いました。
ただ、中華圏の思想は現在進行形なので、結論ありきの論文よりは、エッセイの形式がふさわしかった。前例の少ないイデオロギー状況を「斥候兵」として偵察するのに、機動力のある文体が必要だったわけです。もともと小林秀雄以来、批評の真髄はエッセイ(試行)ですから、著者としては、未知のものをレーダーで計測することこそ批評の仕事だと言いたいですね。
あと、現状はちょっとSF的でもあるんですね。今の中国と香港はそれぞれ、これまでとは異なるアイデンティティを纏おうとしている。中国は成長の衝動に突き動かされてシルクロードの再創造に向かっているし、香港はそれまでの集合的記憶なき金融都市からテイクオフして、むしろ中国化に抗するネーション(香港人)を樹立しようとしている。20世紀と比べて、中国および香港の人格そのものが急速に変わったわけです。僕の本では、SF作家のブライアン・オールディスやJ.G.バラード、劉慈欣なんかも引用していますけれども、それはまじめなリアリズムよりも、突飛なSFのほうがうまく説明できる部分も多いからです。
――本書の第一章「球の世界、道の世界」でも、「エッセイのスタイルこそ批評の精神を自由にし、拡張し、活気づける」と書いていましたね。ユーラシアの思想という正体不明のものにアプローチする上で、ヨーロッパ圏はもとより日本の思想家たちの言説も取り入れながら話を展開していくのもスリリングで、稀有な読書体験でした。冒頭部では特に、カントのいう球の世界ーーつまりグローバル化によって、人々は地球という球体に閉じ込められてしまったために、気の合わない隣人とも忍耐して付き合わざるを得ず、だからこそ平和を「創設」しなければならないとの記述が印象的でした。一方、中国は歴史的に見ても、国家がたくさんあるということに対して忍耐できない傾向があるとも書かれています。
福嶋:ヨーロッパの場合、比較的小さなエリアに個性的な国家が並立する多国家的状況が続いてきたわけです。特に、イタリアはもともと都市国家の集合体で、常駐の外交官の制度もあり、それが後の「国際社会」の雛型にもなる(ついでに言えば、ペスト対策でもイタリアは非常に先進的でした)。他方、中国はまったく逆で、きわめて広大なエリアにおいて「一つの国家」をたえず志向してきた。春秋戦国時代や三国時代のように、バラバラになるときはあるけれども、結果的には「大一統」(一統をたっとぶ)の原則がいつも勝つ。それがなぜなのかは歴史的な謎ですね。
ただ、中国も歴史の進路が多少変わっていれば、ヨーロッパ的な多国家的世界になっていた可能性はある。『三国志』が面白いのは、まさにそのオルタナティブな可能性を内包しているからです。金文京氏によると、三国のなかの魏と蜀は「一つの中国」をめざしたけれども、呉は複数の皇帝の共存を認めていた。もしこの呉のロジックが支配的になれば、中国もヨーロッパのようになり、日本史も劇的に変わったでしょう。しかし、実際には中国は浮き沈みはありつつも、一つの大国となることを志向し続けてきた。
むろん、中国にも国際関係はありました。本では書かなかったけれど、清とロシアの結んだ17世紀のネルチンスク条約なんて再評価されてよいと思います。というのも、この条約のなかで「中国」という国家意識が、ロシアとの関係のなかで再設定されたからです。でも、それもやはり、ウェストファリア体制のようなヨーロッパの国際社会のモデルとは違いますね。
ちなみに、今おっしゃったカントは大学では地理学を長年講じていて、いよいよグローバル化の兆しが見えてきた時代にグロティウスの国際法を批判的に検証しながら、永久平和論を書いている。面白いのは、カントが当時のインフルエンザの流行を、それまでの地理学の常識を超えた事態として捉えたことです。つまり、カントはパンデミックの時代の入り口で哲学をしていた。現代の状況と照らしても、きわめて興味深いことです。
――中国の思想を特徴づけているものの一つに「天下」という概念がありました。この概念が今の中国が掲げる一帯一路構想に繋がっているのも、極めて重要なポイントだと思います。
福嶋:中国ではときにアルカイック(古代的)な概念が蘇るときがあるんですね。今の中国は一面では世界をリードするハイテク国家だけれども、それを支えているイデオロギーは、世界を「天下」として包摂しようという古代の宇宙論に近かったりする。この「天下」というおおざっぱな概念をリブートして、西洋の個人主義や民主主義を超克しようというのが趙汀陽の「天下主義」です。習近平に直接影響を及ぼしているわけではないですが、結果的に、国家間のウィンウィンの互恵的関係をめざす一帯一路構想ともシンクロしているように見えます。
これはちょうど戦時下の日本哲学のあり方を思わせます。日本が大東亜共栄圏を掲げ、それを京都学派の哲学者たちが「近代の超克」とか「世界史の哲学」とかいう観念的なイデオロギーで補完した。実際、趙汀陽の天下主義は、京都学派の三木清の「協同主義」とよく似ています。僕のような日本人の書き手からすると、一度不活性化したはずの日本哲学のウイルスが、中国哲学において再活性化したという気がしますね。
――かつての大東亜共栄圏のような構想が、テクノロジーの発展と国力の増大によって現実性を帯びた面もありそうです。
福嶋:そうだと思います。テクノロジーとイデオロギーの共犯関係は重要ですね。レーニンの『帝国主義論』(1917年)によれば、鉄道建設のようなインフラの整備は一見すると平和的に思えるけれども、それこそが帝国主義のあらわれということになる。このレーニン的な見地からすると、かつてのシルクロードをテクノロジーの力で復興しつつ、情報やエネルギーのインフラを掌握しようとする一帯一路構想は、まさに帝国主義的です。それを中国のイデオローグは「天下」という宇宙論でくるんでいる。
日本にとっても、対岸の火事ではありません。日本もすでに大なり小なり、中国の政治状況や権力構造のゲームに巻き込まれている。日本人の研究者が、以前中国で拘束されたこともありますから、専門家にも暗黙の「自主規制」が働かざるを得ない。政治的に中立的であることはもはや難しい。だからこそ、我々は中華圏のイデオロギー現象についての認知地図を、大急ぎで更新する必要があります。
かつてアメリカの政治学者フランシス・フクヤマは、アメリカの自由民主主義がソ連の共産主義に勝利したことで、歴史は終わったと述べました。人類の歴史にはもう結論が出たから、後はその微修正とメンテナンスをやればよい、と。でも、その楽天的なストーリーは破綻したと思います。自由民主主義は人類のファイナル・アンサーではなく、たまたま冷戦後の一時期に支配的になった思想だと考えないといけない。
現に、2013年前後には、西欧のリベラルで世俗主義的な価値観に対するバックラッシュがアジアを席巻したわけです。中国で一帯一路構想が掲げられる一方で、インドではモディが首相になり、トルコではエルドアンが大統領になった。それに伴って、近代の世俗化の原則に逆らって、むしろ「再宗教化」の機運も出てくる。エルドアンなんて、イスタンブールの博物館アヤソフィアをモスクに転換してしまったくらいですからね。2014年の香港の雨傘運動やウクライナのユーロマイダン革命は、まさにこのバックラッシュのなかで「ユーロ」と「アジア」の価値観が衝突した事件です。なぜかあまり指摘されていませんが、2010年代半ばはアジア政治史の重大なターニングポイントだと思います。