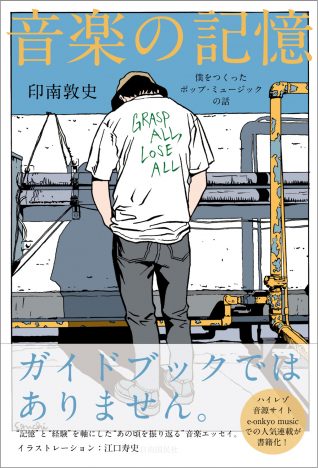ペリー来航から始まった「ニッポンの音楽批評」の行く末は? 栗原裕一郎×大谷能生が綴る、ドラマチックな批評の物語

CD売り上げのピークとなった1997~1998年を経て、次第に縮小していく日本のレコード産業。音楽雑誌もその影響を受けて次々と休刊に追い込まれていく。さらに音楽ジャーナリズムがフォローしてこなかった、アニソンやゲーム音楽を経由したアーティストも珍しくなくなる。コロナ禍になるとネットでの音楽ビジネスが盛んになり、動画を見た人々の口コミによってヒットが生まれる。存在感の薄れてしまった音楽批評はこれから先、一体何ができるというのか。
〈批評はもうアーカイヴィング作業みたいな方向しか命脈がないかもね。歴史の再構成と文脈づくり。未来方向へ向けて価値を付ける役割はもう音楽コンシェルジュやプレイリスターに盗られたんだよ(笑)〉(栗原)。
〈今は映像とコミで音楽聴く感じになっているので、視覚情報も埋まっちゃって、それがいい感じなんだと思うけど、どっかでそのあたりもう一回切断して、文字に戻る可能性はあると思う〉(大谷)。
私が思うに…なんて、音楽批評の方向性を決める会議に同席しているような気分となり、これまでに得た知見を活かしてアイデアを出したくもなる。とはいえ、音楽にまつわるあらゆる物事が多様化した今、そう簡単に答えは見つからない。
ここはひとまず、こたつの上に蜜柑と本書を置いて、日本レコード大賞や紅白歌合戦でも見ながら令和の批評の在り方を考えてみる。これが今年の理想的な年末の過ごし方というものだろう。