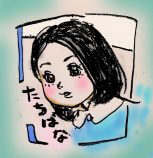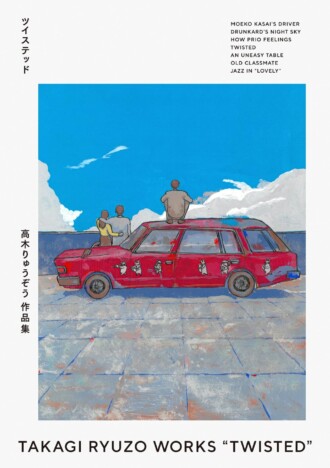肩書や属性を越えて人と向き合えるか? 高野ひと深『ジーンブライド』が放つ刃の鋭さ

高野が本作を描こうと思ったきっかけのひとつが、『男も女もみんなフェミニストでなきゃ』というエッセイを読んだこと。著者はチママンダ・ンゴズィ・アディーチェというナイジェリア南部出身の女性。作中には、こんな文章がある。
もっと対等な世界を。自分自身に誠実であることで、より幸せになる男性たちとより幸せになる女性たちの世界を。これが私たちの出発点です。私たちの娘を違うやり方で育てなければいけないのです。私たちの息子もまた違うやり方で育てなければいけないのです。
これが、高野の決意でもあるように思う。そして、ふりかえれば『私の少年』で描かれていたことも、根っこは同じだったんじゃないのかと。
出会ったときは30歳だったOLの聡子と、12歳の真修。母親はなく、ややネグレクトぎみに育っていた真修を夜の公園で見かけた聡子が、保護するように声をかけたのがきっかけで出会った二人は、まるで親戚のような距離感で親しくなっていく。ところが、真修の父親の了解なしに育まれていったその関係はやがて問題視され、二人は引き離されてしまう。
社会倫理の面で考えれば、当然である。聡子は、間違いなく迂闊だった。けれど、幼い真修が救いを求めていて、その手をとることができたのは聡子だけだったことも、事実。中学生になった真修と聡子が再会したあとも、そのジレンマは常に二人の関係にはつきまとった。
結果、〈聡子のこと女として思ってるんだろ〉と挑発した聡子の同僚に対し、真修の放った〈聡子さんのことは人間だと思ってます〉の一言は、ジレンマに対するひとつの答えだったのではないかと思う。聡子と真修は、常に互いを、人間として見ていた。大人と子供で、女と男。その属性は決して切り離すことはできないし、社会的に考慮されるべき問題だと自覚したうえで、それでも、子どもだから、女だからといって相手の心を侮るようなことは決して、しなかった。それは同性同士でも、同い年同士でも、あんがい難しいことだからこそ、二人は互いを特別な存在として認めていったのではないだろうか。
『ジーンブライド』で高野が描こうとしていることもまた、根本では同じなのではないかと思う。男性の放送作家との打ち合わせがセクハラ皆無で進行した際、依知は〈話がめちゃくちゃ上手い…好きだ…〉と思う。インタビューした映画監督のことも同じで、作品が大好きだからこそ真剣に話を聞きたかった。男女の属性をむきだしにされず、対等な人間として接していられる限り、依知は彼らのことを憎まず、愛することができるのである。
そんな彼らとの対比として、蒔人もいる。経験値による依知の警戒心に肩透かしをくらわせるように、まるで「女」として扱ってこない彼の、そのまんまの行動が依知の心をほんの少しほぐしていく。恋でも友情でもないその「同じ社会で生きている」彼との関係は、とても尊いもののように、読んでいて強く感じられた。
どうすれば人と人とが、肩書や属性を越えて対等に手をとりあい、生きていくことができるのか、高野は今作を通じて『私の少年』以上に深く探っていくのではないかと思う。SF展開がどのように花開いていくのか、依知の傷はどのように克服されていくのか。高野の覚悟を、2巻以降も見届けたい。