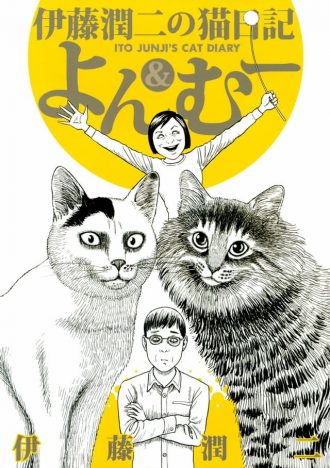後藤護の「マンガとゴシック」第2回
後藤護の「マンガとゴシック」第2回:楳図かずおと恐怖のトートロジー 『神の左手悪魔の右手』における鏡・分身・反復

「反復型」のコマ割り——アンチ・フレームの美学
楳図かずおマンガを特徴づけるものとして、異様に細かい反復的なコマ割りが挙げられるだろう。それは1955年刊行の単独デビュー作『別世界』に既に見られる傾向で、90年代の代表作であるSF長編『14歳』に至ってはチキン・ジョージがズボンとパンツを脱ぐという一動作のために、計4ページ、計26コマを費やすまでに進化(?)している。マンガ表現のエコノミーからすると非効率極まりないわけだが、これが独自の効果やリズムをもたらす楳図文法であるのも事実。高橋明彦は『楳図かずお論』(青弓社)の中でこれを「反復型」と名付け、以下のように説明している。
「「反復型」とは、細かい分節により、そこに予想以上の時間をはらむことで生まれる重量感の表現であるが、明確な意味(言語)に還元されないものである。純粋なニュアンスの表現とも言えるだろう。」(243ページ)

こうしたスローなコマ運びを大阪のマンガ家・酒井七馬から学んだと楳図は語るが、本人にも独自の理屈があるようで、こう語っている。
「これ[=反復型のコマ割り]は、僕がセリフで説明するのではなく、動きで読ませたいという気持ちがより強いからなんです。動きを見せたいときには、読者が連続した画面を見ているうちに、コマの積み重ねによって、動きがズンズン伝わってくるような処理を心がけています。」(同書、249ページ)
更にもう一点重要なことを楳図は付け加えている。フレームに生命を持たせたくない、フレームを意識させたくない、マンガの形式ではなく中身に没入して欲しいからこそ「反復型」のコマ割りを多用している、といった旨のことを言うのだ。このアンチ・フレームの姿勢はゴシックでいう「ピクチャレスク」美学を打開するマンガ思想である。
ピクチャレスクとは18世紀英国のゴシック美学を支えた概念で、どんなにおぞましい光景でも距離をもって安全圏から眺めれば快楽に変わるという倒錯美学。我が国で言う「対岸の火事」の論理である。大惨事であっても絵画(ピクチャー)に描かれ、フレームに収められた時点で恐怖は緩和されるのであり、この感性が極まると世界は一枚の絵のごとしとなる。楳図はその安全圏に住まう読者が気に入らない。それゆえワイリー・サイファー風に言うならば、楳図の「反復型」は現実の模倣(ミメーシス)というより、読者をそこに参画(メセクシス)させることを志向していると言える。
恐怖のトートロジー
と言って「反復型」のコマ割りが単に読者を巻き込むリズムやグルーヴに帰する問題かというと、それだけではない気がする。単純に似たようなコマが続くことは不気味で不吉ではないか? これは「トートロジー」の恐怖である。トートロジーとは同義反復のことで、簡単に図式化すると「A=A」となる。しかし「私は私である」とか「ペンはペンである」とわざわざ言うとき、実は言外の意味が付与されているのであって、本当に「A=A」ならそもそも発語する必要もない。
アイデンティティ・クライシスや認識論的同一性に亀裂が走ったときトートロジーは発動するのであって、それはつまり似て非なるものである双子に感じる恐怖のようなものだ。あるいはルネ・マグリットの「これはパイプではない」を前にした際の妙な居心地の悪さ、不気味さを思い出してみてもよい。だから本当は「A=A」は「A≒A′」なのであって、トートロジーは差異をもった反復を前提とする。
思わず「双子」と口走ったが、楳図のトートロジー的なコマ割り技法は、実のところ鏡・分身といった楳図マンガに頻出するダブルイメージ(似て非なるもの)の主題と連動している。例えば「かげ〈映像〉」という作品では、巨大な洋館に住むヒロイン絵美が、夜眠りにつくと嫌な心地がして目覚め、その正体を探るうちにシンボリックな大鏡の前に行き着く。

ここで「反復型」のコマ割りが適用される。絵美と背中合わせの鏡像のペアが、似て非なるものとして6コマにわたって反復される。ここでは「鏡による分身」という作品テーマに沿うように、コマ自体が6つに分裂して「分身」を創り出しているごとくで、主題と技法の見事な一致が確認できる。とりわけ上段三コマは時間的推移やリズムを示す以上に、似て非なるものの連続体(トートロジー)ゆえに不吉な予感を漂わせている。
超現実としてのトートロジー

ある意味トートロジーとはAという世界の「鏡映し」としてのA´とも言える。いわば微妙な差異をはらんだ「向こうの世界」であり、内島すみれ『トートロジー考』(北冬書房)の表紙にあしらわれた、つげ義春「李さん一家」の一コマのように、二階にいながら「二階にいるのです」と発語されることで異化された現実的非現実。
超現実というものは、ふと現実が微熱を帯びて入ってしまうような地上2、3センチ浮かんだ世界である(大意)と巖谷國士が『シュルレアリスムとは何か』で語るごとく、楳図的トートロジーもまたさりげなく超現実の扉を開く。楳図版スプラッターホラー『神の左手悪魔の右手』で主人公・山の辺想が「地下室で見たガイコツだ」と叫びをあげるシーンを取り上げてみよう。

このケースはどちらかと言うと言語上のトートロジーである。「地下室にあったガイコツだ‼」という旨のセリフが計三回変奏されるが、それぞれに違った認識レベルにあることが分かる。まず一回目は発見の驚き、二回目は他者への説明、三回目は疑心暗鬼である。2ページ前に姉・泉の口から吐き出されたガイコツ(※泉の内臓と外部にある地下室が通底しているという設定)が二度描写されるが、三コマ目でガイコツは想を見つめ返すような、問わず語りのヴァニタス的沈黙を湛えている。それに作用されてか、三回目の想のセリフは確信が揺らいで懐疑のニュアンスが生じている(従ってラストのコマでは「ほんとだよ‼」と念押しすることになる。まるで自分に言い聞かせるように)。このようにトートロジカルな構成は、気づかない、微妙なレベルで世界を超現実的に変成しているのだ。
なぜ神が左手で、悪魔が右手なのか?
ところでゴシックがテーマの連載にも関わらず、僕がアホみたいに「超現実」と連呼してきたのは、シュルレアリスムの父アンドレ・ブルトンが昔々のゴシック小説を発掘、再評価し、その荒唐無稽ぶりをして「俺の祖先に相応しい」と認めたことに関連している。ゴシックもシュルレアリスムも「夢の論理」ないし「鏡の論理」に憑かれた芸術という意味では同一線上であり、『神の左手悪魔の右手』もその系列にある、と言いたいのだ。
夢と現実が絶え間なく相互嵌入し続け、両者の境界があいまいとなる楳図版『エルム街の悪夢』と言える本作は、全体にトートロジカルなコマ運びやセリフが頻出・反復することで、「A=A」の固定した世界観に常に揺さぶりをかけ、微妙に位相をズラし、「A≒A′」の超現実への扉を開く。
内容を超かいつまんで言うと、神であり同時に悪魔である子供の桁外れの想像力(=世界の根源としての「ヌーメラウーメラ」)が炸裂するスプラッターホラーで、因果関係のあるようでない、破天荒な物語展開はほとんど夢の論理であり、マニエリスム的奇想の数々がグロテスクに肉体の穴という穴から夥しく排便(?)される。

しかしタイトルが引っかかる。宗教人類学的に言えば不吉とされるのは本来左で、ロベール・エルツ『右手の優越』やロジェ・カイヨワ『反対称』のような古典的名著から、現代まで(そこはかとなく)続く左利き差別まで踏まえれば、本体タイトルは「悪魔の左手」であるべきだ。とは言い条、「神の左手悪魔の右手」を鏡に映せば、その鏡像は左右反転して「神の右手悪魔の左手」になっている筈だ(「ヌーメラ」と「ウーメラ」も言語的にAとA´の双子関係を身ぶりしている)。「われわれの両手ほど似ているものがあるだろうか」とはエルツの言である。
似て非なるコマの連続体、現実のような超現実、左手のような右手、悪魔のような神……楳図的恐怖の根源とは、A′が恰もAのような顔をして振舞う、自分によく似た分身が「不気味なもの」としてトートロジカルに回帰する恐怖なのかもしれない。