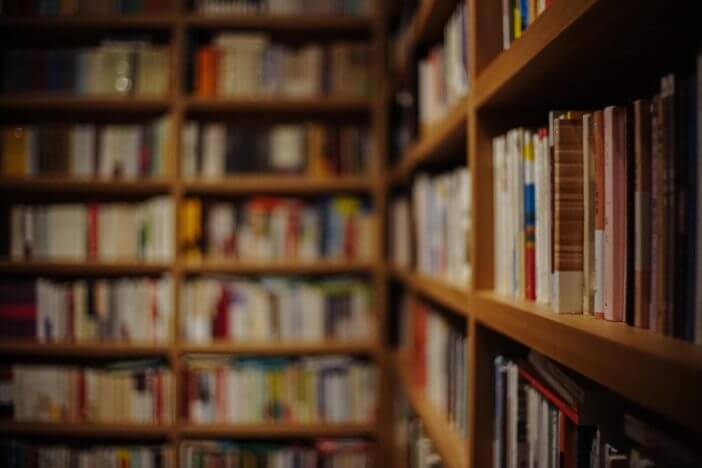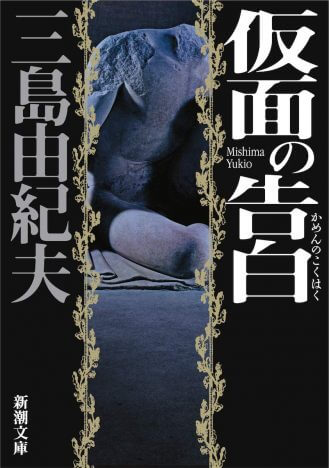千葉雅也×宮台真司が語る、性愛と偶然性 「そこで経験する否定性を織り込んで生きていく」

恋人がタクシーで去っていくとき

ここ最近、小山田圭吾の件もあって90年代のカルチャーは悪趣味だったと叩かれており、たしかに一部にそういうグロ系を扱ったコンテンツはあったと思いますが、少なくとも僕はそういうものを重要視はしていませんでした。ただ、セックスに関してはリスクとともに生きるという感覚が今よりずっとあった時代だと思います。昨今は、90年代当時はよくなかったとする反省モードに入っていて、自分もそういう状況にいたにも関わらず誰かを糾弾するような人もいますけれど、僕は全くそれを反省しない小説を書いていて、むしろ今こそ偶然性と、そこで経験する否定性を織り込んで生きていくことを、もう一度言うべきだと考えているんです。
宮台:『サブカルチャー神話解体』(1993年)で書いたけれど、性愛的なコミュニケーションの享楽はまさに偶然性にあります。例えば、テレクラには早取り式とフロント式があるんだけれど、マニアは早取り式を好むんですね。フックを連打してカチャッとつながるんだけど、どこにつながるのかは完全なる偶然。僕の場合は「早取りくん」というハイテク機器を使っていたので、さらに偶然性が高くて、0.1秒遅れたら違う人間とつながっていたという感覚を生きていました。90年代に入るぐらいまでは、その偶然性が、若い世代から主婦や中年男まで含めて、間違いなく享楽の種だったんですよ。
でも、以降になると、0.1秒遅れていたら他の人と出会っていたはずだという偶発性が、トラウマティックな傷だと感じられるようになり、『サブカルチャー神話解体』でも紹介したように心を病んでしまう女も出てきました。必然性を探す人たちが若い世代から増えたのですね。そうした期間を挾んで、90年代後半からの25年間は、統計的にも僕のリサーチから見ても、男女とも性的に退却していきました。長く一緒にいることから始まる性愛が衰退し、ナンパやテレクラが盛り上がった短期間が過ぎると、偶発性が有害だと感じられて、偶発的な出会いに心を閉ざすようになったのですね。千葉さんの教え子の学生さんたちは、偶然性の享楽についてどのように受け止めていると思われますか。
千葉:どうでしょう。エロスはリスクとともにあるものじゃないかと言えば、それなりに受け止めてくれるとは思いますが、彼らがどういう生き方を選ぶかは、やはりかつてと比べてはるかに無難なものになっているように思います。
宮台:若い世代になるほどそうでしょうね。統計リサーチによると、こんなにも経済的に苦しくなったのに、大学生の生活満足度はどんどん上がってきています。社会学でいうところのアスピレーション・レベル、つまり願望水準が下がっているからです。願望しなければ、がっかりもしないというわけです。
関連して、この十数年、僕のゼミにときどきクレームがつくんですが、その内容が「授業が濃すぎる」というものなんです。さらに、性愛の話題を授業で扱うと「扱わないで欲しい」というクレームがつきます。今まで十件クレームがありましたが、全て男子からです。
千葉:性愛を引き受けられないというか、自分がそのことによって何か責められているような感覚が「つらい」のかもしれませんね。
宮台:フラットな生活をつまらないと言われるのが「つらい」。そういう若い人になりきって千葉さんの小説をもう一度読むと、性的な身体性や肉体性が想像の埒外である人は他人事だと感じ、それを想像できる人は、羨望や嫉妬を掻き立てられるんじゃないかと思いました。「千葉っていうのは頭がいいだけじゃなく、性的にも幸せじゃねえか」と。
千葉:ははは、すごく単純なルサンチマンですね。
宮台:そう。単純すぎるルサンチマンがこの十数年、驚くほど蔓延している。そうした状況を考えると、千葉さんの小説はある種のアジテーションで、「お前らそれでいいのか?」と挑発している感じがしました。そこで改めて質問したいのですが、そうした時代にこうした小説を書くことの意義についてはどう考えておられますか。
千葉:僕の小説をゲイ小説として捉えた時に重要なのは、昨今は性的に多様な人がいるので社会的包摂の権利をより公的に認めていこうとする流れがありますが、そうなった時に忘却されるのがビート的セックスであったり、偶然性のエロスなんです。難しい問題ですが、例えば同性婚を認めようというアジェンダがあって、それを邪魔しようとは思わないけれど、無批判に同性婚を良いものかのように扱うのはやめてくれと考えています。アメリカにも同性婚批判の文脈はありますし、国際水準の議論として疑問を向けるのは当然のことです。同性婚という形で結婚を規範化されたときに、何が失われるのかは示そうとしていますね。
宮台:同感します。僕もナンパや不倫を奨励しつづけてきました。結婚つまりマリッジは、人類が定住するようになってから、財産の保全と配分と継承のために作られた制度で、以前は交尾つまりメイティングしかなかった。子供を作ったら3歳ぐらいになるまで一緒に暮らし、その後は別の相手とメイティングしてまた子供を作るというのが普通でした。現在は、これだけ多くの人が財を剥奪されて貧乏になっているんだから、「結婚なんてどうでもいいじゃん」という考え方は、ゲイの側からも主張してほしかったところです。ゲイの界隈で、同性婚の権利はそれほど重要なのでしょうか?
千葉:ゲイ界隈には、一方ではマジョリティ同様に結婚の権利を求める人も多いわけですが、同時に、「結婚なんてどうでもいい」と、独自の生き方にプライドを持つ価値観も存在してきました。でも、いま表に出ているリベラルな傾向の人たちは同性婚の権利を主張するのが当然であるかのように見せている。しかし、表には出てこないような層ーーたとえばネットにエロ動画を上げているようなゲイアカウントを見ていると、状況はそんなに単純ではないと思います。
宮台:社会学者として言えば、もちろん機会の平等はあった方がいい。だから、ノンケができることは、ゲイもできていい。でも「ノンケと同じことをしなければいけない」ということはない。統計をみると、小学生から大学生まで9割が将来は結婚したいと言っています。これだけ性的に退却していて、いろんなスキルも不足しているのに、9割も結婚できるわけがありません。そうした現状をみても、同性婚は認められていいけれど、いつかは結婚したいという規範を自明に内面化していることはすごくおかしい。だからこそ千葉さんがそのような意見を持っていることに勇気づけられます。
千葉:ミシェル・フーコーが今生きていたら同性婚をどう言ったかわからないですが、フーコーは、いかにゲイとして生きるかは発明し続けるべきことなのだ、と言っています。小泉義之さんが『群像』に『オーバーヒート』の書評を書いてくださったのですが、それがまさにフーコーを踏まえたものでした。フーコーが書いた「恋人がタクシーで去るとき」という素敵なエッセイがあって、ゲイセックスの最高の瞬間は、恋人がタクシーで去っていくときで、永遠の結合とは逆であり、そこにもっとも美しいものを見るというんです。『オーバーヒート』は、言ってみればパートナーを信じ直すという話なのですが、小泉さんはフーコーのエッセイを文字って、「恋人とタクシーに乗るとき」というタイトルを付けてくださった。なかなかエモいと思ったんですけれど、でも今はなかなかそういう価値観が通用しない時代なのかな。
宮台:フーコー的な「不可能性を前提にした美学」についての感覚は、この30年くらいどんどん通じなくなってきたと思います。ところが最近、急に若い人たちにこういう話が通じるようにもなっていて、僕のゼミも大盛況になっています。「もはや可能性の追求の中には未来の実りはないんだよ」という考えを一貫して話してきているんだですが、彼らにその感覚が通じるようになりつつあるのは、願望水準の引き下げとは別の、従来の生き方への諦めがあるからかもしれない。彼らの世代が頑張っても、父親と同程度のポジションに付くのは難しいのが象徴的ですが、ゼミ生をみると「それをしたところでなんぼのもんじゃい」という見切りがあり、見切りの果てにそれでも生きる意欲を見つけようとしていると感じます。
千葉:ニヒリズムが深まるところまで深まったってことですね。そうなったらユーモアにいくしかない。となると、近年はネオリベラリズム的な偶然性の増大に脅かされてみんなが安定志向に向かっていたけど、いよいよとなったら諦めるしかないので、徹底的なニヒリストになって、再びなりすましあるいはユーモア的な二重の生を生きるようになりつつあるのかもしれないですね。