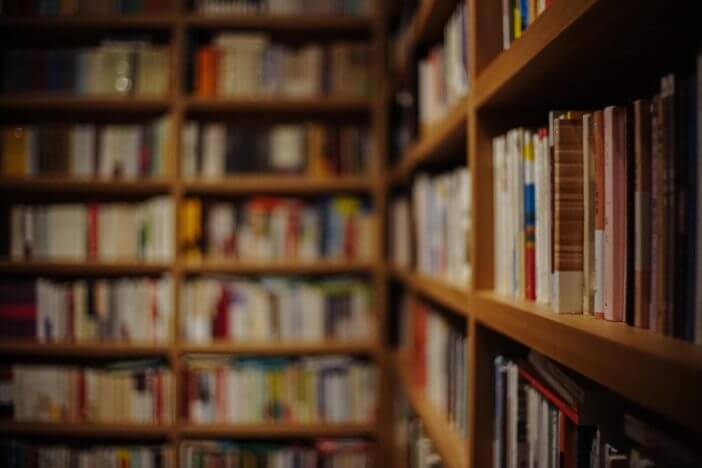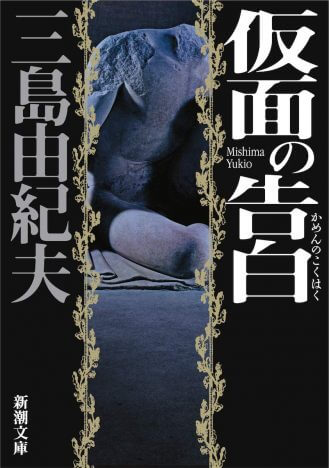千葉雅也×宮台真司が語る、性愛と偶然性 「そこで経験する否定性を織り込んで生きていく」

東京はある種のバーチャル空間

宮台:『デッドライン』の方には、女の子を好きになったことがあるとも書かれていました。多くの男の子には、自分がノンケなのかゲイなのか曖昧な時期があると思いますが、千葉さんの場合はどのようにしてセクシュアル・アイデンティティーが固まったんですか。
千葉:『デッドライン』も『オーバーヒート』もあくまで小説なので、自分自身と全く同じではないのですが、それはそれとして、性の揺らぎというものはバイセクシャリティとはまた違うんですよね。つまり、ゲイのなかにも女性と関係を持ったことがあって、結婚して子どももいるという人もいますし、全く女性と関係を持たないという人もいる。その揺らぎを、青春時代のいろんな出来事の中で描くということをやってみたんです。いわゆる同性愛小説でそういう揺らぎを書いたものは、特に現代日本を舞台にした作品では他にないと思います。
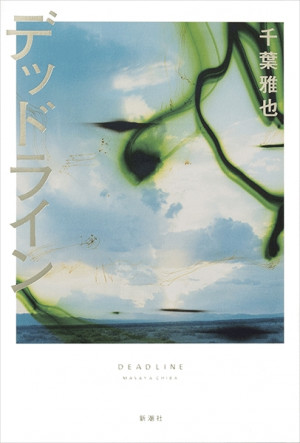
宮台:僕も御多分に洩れず、中学から高校1〜2年にかけては、男子校だったこともあって、男の子ばかり好きになりました。性交の手ほどきも先輩から受けました。最初に他人からチンコをしこられたのも男の手によってです。『デッドライン』を読んで、そういう曖昧な時代があったことを思い出しました。
それで、『デッドライン』や『オーバーヒート』ではそういう揺らぎも含めて、ゲイの身体性や肉体性を通奏低音として描きながらも、大学教員としての生活や修士の学生としての生活をメロディーパートのように描いています。そのメロディーは「どうとでもあり得る」感があって、僕の言葉でいうと「なりすまし」感、千葉さんあるいはドゥルーズ的にいうと「ユーモア」感。それがすべてに漂っているという印象を受けました。
千葉:別に学問じゃなくてもよかったかもしれないというのはときどき思います。ユーモア的選択としてやってるという感じはあります。
宮台:千葉さんの二つの小説のメロディーパートでは、大学界隈のコネクションと、実家がある宇都宮界隈のコネクションが描かれて、そのメロディーの対照も面白いと思いました。あえて本書の主人公を千葉さんだと仮定すると、この対比にはどんな意味がありますか。
千葉:素朴な答えになるんですけれど、やっぱり18歳で東京という街に出てきた時のショックがすごくあったんです。僕は95年にインターネットの世界に入ったのですが、それは栃木県では結構早い方でした。父親が広告の会社をやっていて、仕事の関係で家でもプロバイダを契約したんです。それで匿名のチャットに入り浸ったり、ゲイサイトを見たりしたわけですが、僕にとってその体験は東京へ行く前触れでもあった。地元では親から期待される規範、たとえば結婚して家庭を作ることとか、そういう空気が常にあるのですが、インターネットはそこから全く違うバーチャルな世界にバーンと飛ばしてくれるもので、それはイメージとして東京と近いような場所でした。だから僕の中では、東京はある種のバーチャル空間に感じられるところがあって、ネットの空間と見分けがつかなくなっている感覚があります。対して地元は、出たかった場所であり、すごい重力で飲み込んでくるもの。母親的な安心できる空間でもあるけれど、飲み込まれてしまったら簡単に抜け出せないような秩序がある。だからこそ『オーバーヒート』では母方の実家がキーになっていて、そこから自由になった先にゲイの空間や大学のインテリの空間がある。でも、『オーバーヒート』では、東京から大阪という全然縁のない土地に飛ばされてしまって、東京に対するノスタルジアを抱き、ますます自分の居所がわからなくなってしまうんです。
宮台:母的なものに飲み込まれかねない地元と、自由なカオスとしてのインターネットや都会があるという構図は、僕とは世代的な感覚の違いがあるかもしれません。僕は小学生の頃、京都に住んでいたのですが、当時の生育環境を思い出すと、むしろ地元がカオスでした。小学校には本当にいろんなやつがいて、会社員の子、農家の子、商店の子、医者の子、ヤクザの子なんかがグチャグチャに混ざっている感じ。学校にローラースケート持っていって帰りに山科盆地を走り回ったり、虫カゴにマムシを入れて教室に持参したり、月に一度は教室で取っ組み合いの喧嘩が起こっていたりしました。
でも、6年生になって東京の三鷹市に引っ越したら、喧嘩はしないし、花火の横撃ちもしないし、ブランコの柵越えジャンプもしない。僕が京都でやっていたような遊びは全然なかった。さらに、山科盆地は、北には自殺の名所である池があるとか、東に見える山は性犯罪の名所だとか、このあたりは被差別部落のエリアだといった、方角に色がついている感覚があったのですが、東京のほうは、フラットで等方的な空間が広がっている印象でした。85年から11年ぐらいナンパをしていましたが、初期を除くと全然幸せな感じがなくて、千葉さんが描いているような内から湧き上がるビート感からは見放されていたと思います。
千葉:なるほど、たしかに地元は母的な空間ではあったけれど、おっしゃるようなカオスな側面もありましたね。僕は国立中を受験したものの、学科の後のクジで落ちてしまって、公立中学に行ったんですけれど、そこは本当にワイルドでした。高校から先は学力でフィルタリングされてしまうから、すごく平和だったんですけれど、インターネットを通じてまた中学生のときのカオスが戻ってきたというか、これこそが社会なんだと納得したんだと思います。ところで、僕はBLを経由してゲイカルチャーに入っていて、初期のキース・ヴィンセントなんかはBLを批判していましたけれど、僕の世代ではBLによって自分の欲望を肯定された人も多いと思います。東京にはそういう人にとっての隠れ家があるというか、「襞」がある空間なんです。それと比べると僕が過ごした宇都宮はフラットだったし、親族の抑圧もあった。だから、東京は刺激的だったし、同時に、見知らぬ人と突然出会ってタイプじゃなかったらすぐに別れるといった経験はある意味ショックだった。でもそれはトラウマ的だからこそ魅力的に感じたんでしょうね。
宮台:相手は誰でも良くて、合わなかったらすぐ相手を取り替えていくという流動性の過剰さが、僕にとってはむしろ退屈だったのかもしれない。社会学では昭和的な生活形式を「昭和すごろく」と言って、その一部が「性と愛と結婚の三位一体」だよという言い方をするんだけど、80年代後半の奇跡の数年間を過ぎると、ナンパ界隈には流動性が高いがゆえのフラットな時空しかなくて、それが辛かった。でも、千葉さんの小説を読むと、その流動性を否定的なものとして描いていなくて、そこがゲイカルチャーの良さなのかなと思いました。