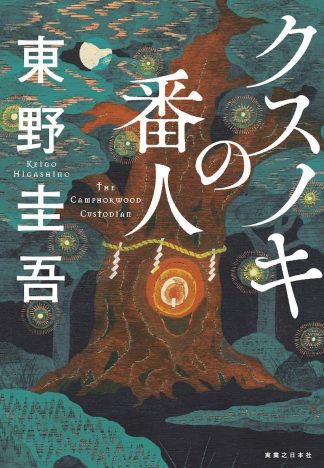老人のイヤイヤ期、脚フェチ、現実逃避……『恍惚の人』から50年、作家たちが描いてきた「老い」とは?


老いとは、人生における救いなのかもしれない。そんな気持ちにさせてくれる小説が、50歳男女の等身大の恋愛を描いた『平場の月』で一昨年に山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみの最新刊『にぎやかな落日』だ。
主人公は北海道に住む83歳の女性・おもちさん。夫は数年前にすっかり弱ってしまい、特別養護老人ホームへ入った。一人暮らしになかなか慣れないが、ご近所さんたちと集まって遊ぶこともあるし、東京に住む娘が1日に2回電話をかけてもくれる。〈ヤア、いっつもお電話ありがとう〉〈ごはん、食べた?〉〈食べたよ。納豆サ。それとおトーフのおつゆ〉。
ある日「持病」が悪化して入院を余儀なくされてしまった、おもちさん。すぐ退院できるだろうと思っていたが、何回も指から血を抜かれたりお腹に注射をされたりと、どうも様子が違う。無意識のうちに大量のおやつを家で食べていたのを看護師の田中さんに指摘されて、〈なして、あたしのすることなすこと、気にくわないんだろう〉と不思議がるおもちさん。病院で先生が病状を説明してくれるけど、それを聞いて理解するための集中力が続かない。〈騒々しい不安に駆られ、いてもたってもいられないのに、なぜかしんとした、ばかのようなきもちになる〉。
本人の認識と現実の乖離が顕わとなっていく中で、途切れ途切れの記憶から浮かび上がる過去への郷愁と後ろめたい感情。どこか不穏な雰囲気も漂う物語の中でおもちさんにとって救いとなるのが、「今」だ。お気に入りの口紅、愛飲しているペットボトルの緑茶、娘に買ってもらったユニクロの細いズボン。好きなものに囲まれていると、覚えていたほうがよかったのかもしれないことも、老いていく不安や淋しさも過去の色々も忘れてしまう。頭の中で共存する記憶の衰えと今を楽しもうという気持ちが、おもちさんを毎日幸せな気分へと導いてくれる。
老後の自分はまだまだ元気なのか、煩悩から離れられないのか、衰えと上手に付き合えているのか?老人になって老人文学を読んでみたらどんな感情を抱くのか?一筋縄ではいかない老いを描いた小説は、読者に老いへの尽きない興味を持たせてくれるはずだ。
■藤井勉
1983年生まれ。「エキサイトレビュー」などで、文芸・ノンフィクション・音楽を中心に新刊書籍の書評を執筆。共著に『村上春樹を音楽で読み解く』(日本文芸社)、『村上春樹の100曲』(立東舎)。Twitter:@kawaibuchou
■書誌情報
有吉佐和子『恍惚の人』(新潮文庫)
田辺聖子『姥ざかり』(新潮文庫)
谷崎潤一郎『瘋癲老人日記』(中公文庫)/『鍵・瘋癲老人日記』(新潮文庫)
朝倉かすみ『にぎやかな落日』(光文社)