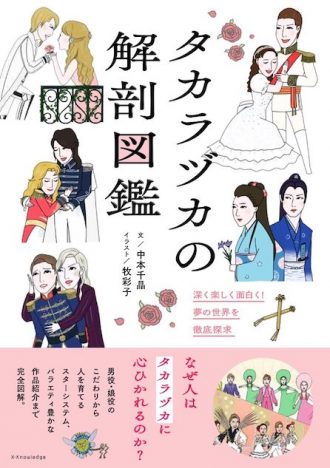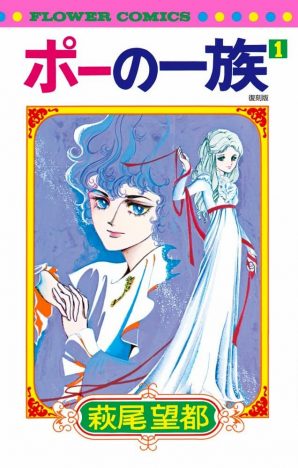宝塚花組でも上演 色あせない『はいからさんが通る』の魅力とは?

昔、ニュージーランドでアメリカ人の老夫婦と出会いました。彼らは戦後すぐに日本の帝国ホテルで結婚式を挙げたといい、思い出話の中にちょいちょい「朝鮮戦争が」とか近代史で習うような出来事が出てきて、長く生きるって歴史を体験することなんだと感動しました。今のコロナ禍も、恐らく50年後、100年後には社会現象のひとつとして語られる出来事になるのでしょうね。専門家が渋谷スクランブル交差点の写真を見て「ああ、道行く人がマスクをしていないので2019年のものですね」とか解説したりして。
歴史といっても私たちは、明治からこっちの近代史はあまり学校で学びませんね。受験に出ないことが理由だそうですが。『はいからさんが通る』は、そんな私たちにとって未知の時代を教えてくれる名作です。
主人公は女学校に通う花村紅緒さん。ある日女学校から帰ると、家にやってきたイケメン陸軍少尉が自分のいいなずけだと教えられます。その理由が、明治維新。花村家は代々徳川に仕える旗本でした。イケメン少尉の伊集院家はお公家。紅緒さんのお祖父さまと少尉のおばあさまは、恋仲だったけれども運悪くそれがご一新前夜だったのです。官軍と朝敵という間柄で仲を引き裂かれてしまいます。いつの日か身分の差のない平和な世になったら、ふたつの家をひとつにしようとふたりは誓い、彼らの子どもは両家とも男子だったため、紅緒さんと少尉にくじがまわってきたのでした。
お話の舞台は大正なのですが、きっかけは明治維新まで溯るというわけです。そしてふたりに降りかかる日露戦争。そこから、ロシア革命、米騒動、満州建国、関東大震災と、歴史の教科書に載っているような社会的な出来事が彼らの人生を翻弄していきます。その合間にも、大正の文化や政治情勢などが細かに語られていくんです。ひとりの平凡な女性の人生に、社会というのはこんなにも影響を与えるのですね。時代を生きるってこういうことなんだなと今さらながらに思います。
それに加えて、強烈に訴えられるジェンダー問題。女性らしくあることを押しつけられるジェンダーロールに、紅緒や学友の環は、猛烈に反発します。女性の社会進出を描いたのも、男女雇用機会均等法施行前の70年代らしい主張です。自分の人生をどう生きるか、女に生まれたという枷をどう乗り越えていくのか、作品には数々の強烈なメッセージがあります。
それなのに、『はいからさんが通る』は全編を通してコメディなんですよ。社会情勢、ジェンダー、大正文化の紹介と、情報がギッシリ詰まっているのに、ギャグ満載なんです。すごくないですか?
もう何度読んだかわからないのに、ストーリーは全部頭に入っているのに、また読み返してしまう吸引力。そしてそのたびに、「プッ」と吹き出したり、その直後にボロボロ泣いたり。私の脳みそは大変な勢いでこの作品に侵されていて、九州は小倉と聞けば「いいところ」だと思っているし、満州と聞けば馬賊がいると思っています。お抹茶は「に・がーい!」と叫ぶほどのお味のはずです。
子どもの頃は、少尉を奪ったラリサが大嫌いだったけれど、大人になると、彼女の苦しみもわかるようになりました。そして少尉や紅緒さんの葛藤も。インネン中佐は変わらず嫌いですけどね。