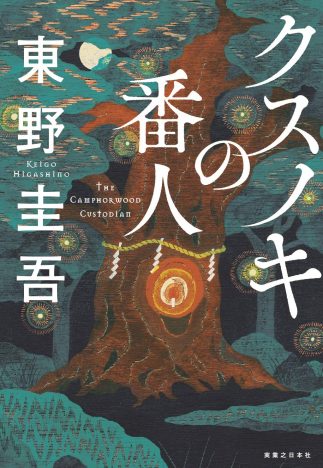『半沢直樹』は現代の歌舞伎か? 池井戸潤の優れたエンターテインメント性

放送中の人気テレビドラマ『半沢直樹』を見ていると、これは現代の歌舞伎だと思ってしまう。歌舞伎役者が4人出演していることや、歌舞伎の所作を取り入れた演技だけが、そう思った理由ではない。ストーリー自体が歌舞伎を彷彿とさせるのだ。
そもそも歌舞伎は大衆芸能であり、庶民に受けるストーリーが演じられてきた。舞台の上の喜怒哀楽に、庶民は喝采を送ったのだ。『半沢直樹』の原作である、池井戸潤の「半沢直樹」シリーズには、それと同質の喜怒哀楽がある。一連の池井戸作品を俯瞰しながら、この点について述べてみたい。

池井戸潤は、1998年、元銀行員という経歴を生かしたミステリー『果てる底なき』で、第44回江戸川乱歩賞を受賞した。その経歴とデビュー作のインパクトから、銀行を題材にした作品が多く、銀行の内幕を暴く書き手と目される。だが、高原の町で起きた連続殺人の真相を駐在所の警官が追う『MIST』のような秀作もあり、けして銀行という題材だけを売りにした作家ではない。
さらに銀行を題材としながらも、しだいにエンターテインメント性を強めていった。2004年に、事務処理を抱える支店を指導する“臨店指導”を行う、東京第一銀行の花咲舞の活躍を描いた『不祥事』を刊行。2007年には、東京中央銀行の大阪西支店で融資課長を務める半沢直樹が、5億円の債権回収騒動の渦中で悪党どもを痛快にやり込める『オレたちバブル入校組』(現『半沢直樹1 オレたちバブル入校組』)を刊行。これが「半沢直樹」シリーズの第1弾となる。そして当時の作品から、池井戸エンターテインメントの核となる“ジャイアントキリング”が、物語から伝わってくるようになるのだ。
ジャイアントキリングとは、主にスポーツで使われる用語である。格下が格上の相手を倒すことを指す。日本語でいえば番狂わせだろう。サッカー漫画『GIANT KILLING』によって、広く知られるようになった。半沢が自分より立場が上の銀行員の非を暴き、徹底的にやっつける『オレたちバブル入校組』は、まさにジャイアントキリングであった。
このジャイアントキリングは、2006年の『空飛ぶタイヤ』でも描かれている。走行中に外れたトレーラーのタイヤにより起きた死亡事故。その責任を押しつけられた小さな運送会社の社長が、欠陥隠しをする巨大自動車会社と対決するのだ。小さな会社と巨大企業という図式が、ジャイアントキリングを際立たせている。同年に刊行した『シャイロックの子供たち』もエンターテインメントを強く意識しており、作者の方向性が決定した年といってもいいかもしれない。
その後、下町の製作所がロケットの部品や、心臓に埋め込む人工弁の開発に挑む「下町ロケット」シリーズや、業績が低迷している足袋製会社がランニングシューズ開発に乗り出す『陸王』などの快作を連発。小さな会社と大企業という図式を踏襲しながら、次々と新たな題材を扱い、多くの読者を満足させたのである。また、社会人スポーツを題材とした『ルーズヴェルト・ゲーム』『ノーサイド・ゲーム』も、少し形を変えて先の図式を当て嵌めている。