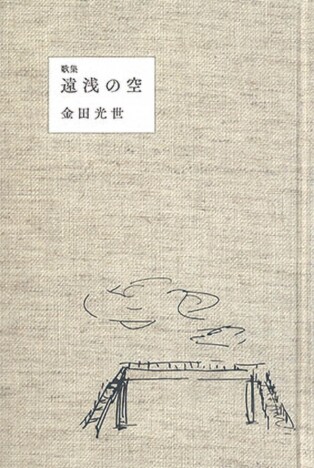町へ出られないコロナ禍に、寺山修司を探す旅へ出よう 生誕85周年記念復刊『寺山修司記念館』

『寺山修司記念館』(笹目浩之監修,トゥーヴァージンズ)とは、7月14日に寺山修司生誕85周年を記念して復刊された、寺山修司記念館公式カタログのことである。元々は2000年より全国で開催されていた「寺山修司展」の公式図録であった。
ページをめくるとそこはもう、夢と幻想、母親への愛憎と郷愁に満ちた寺山修司の世界だ。立川直樹による寺山修司との「架空対談」(全日空「翼の王国」1998年1月号より転載)にはこんな言葉がある。
〈高校生の時に買った新書館から出ていた詩集の中で、あなたが“淋しいという字は、木が2本並んでいるのになぜ淋しいんでしょう”と書いていた。僕はそれでもう完全に寺山修司に捕まってしまった……。〉
他ならぬ私自身もそうだ。寺山修司と出会って以来、「さびしい」という字を書く時、「寂」ではなく木が2本並んだ方の「淋」で必ず書いてしまう病になってしまった。今から7年前、寺山修司監督作品『田園に死す』に魅せられた私は1人、無数の風車が強風でグルグルと回り続ける恐山にいた。そこには「シュッシュ」と汽笛の口真似をして通り抜ける白塗りの少年もいなかったし、黒いドレスを突然脱ぎ始める新高恵子もいなかった。私に話しかけてくれたのは、イタコの老婆ではなく、雨の日に一人恐山行きのバスに乗る女子大生を心配してくれた親切なおばあさんだった。私もまた彼の「映画の上を歩」かずにはいられなかった一人だ。他に交通手段がなくタクシーで行った寺山修司記念館の傍には、首を傾げたビクター犬が佇んでいた。
粟津潔のデザインをもとに作られた寺山修司記念館の中は、それこそこの本の副題どおり「きらめく闇の宇宙」だった。「スクリーンとプロジェクターの間にある観客席が必ずしも安全地帯ではないこと」を暴こうとした寺山映画が常に観客に「ただ観る」ことをさせてくれなかったように。1975年30時間市街劇『ノック』がまさしく事件となり当時の新聞の社会面をにぎわせたように。寺山修司記念館は、「観る人」も参加せざるを得なくなる、一風変わった記念館だ。
彼の立ち上げた演劇実験室・天井桟敷の舞台セットを髣髴とさせるような空間の中には、柱時計や人力飛行機、シンちゃんや空気女といった彼の作品のモチーフたちが息づいている。そしてあるのは、いくつもの机。「観客は立会いを許された覗き魔である」という彼自身の言葉通り、観客は、その机の引き出しを開けて覗くことを特別に許される。そこにある資料の数々、自筆の書簡の数々には、寺山修司の歴史が、言葉が、思考の数々が詰まっている。ある引き出しを開けると、黒電話が入っていて、受話器を取ると、寺山自身による短歌「田園に死す」と詩「アメリカよ」の朗読が聞こえてくるなんていうファンの心臓をドクドクと波打たせる仕掛けまであるのだ!
資料として興味深いのは、学生時代、ネフローゼを患い入院していた時期、恩師、中野トクへ当てた多数の手紙に書かれている「ちえッ。生きてえな」「失恋しました。僕、やせました。僕、背が伸びた。今に、みよ」という病気のために活動できないジレンマや生への渇望が伝わってくる言葉の数々である。同時期に読んだ書物の言葉を何冊ものノートに抜き書きしていたのも興味深い。写真の切り抜きやイラストと共に綴られる文章の数々が、現在も多くの人に親しまれている文庫本『ポケットに名言を』(角川文庫)のベースになっているのは間違いないだろう。
3年の闘病生活を経て、寺山の創作意欲は堰を切ったように溢れだし、俳句や短歌、詩など文学に留まらず、ラジオドラマ、テレビ、演劇、映画、歌謡曲、はたまた競馬評論と、ありとあらゆるジャンルで活躍することになる。1983年、肝硬変で亡くなるまで駆け抜けた、47年の生涯。



![高橋一生×浦井健治×藤田俊太郎『天保十二年のシェイクスピア』を語る『act guide[アクトガイド] 2020 Season 5』](/wp-content/uploads/2020/01/0129_actguide-330x468.jpg)