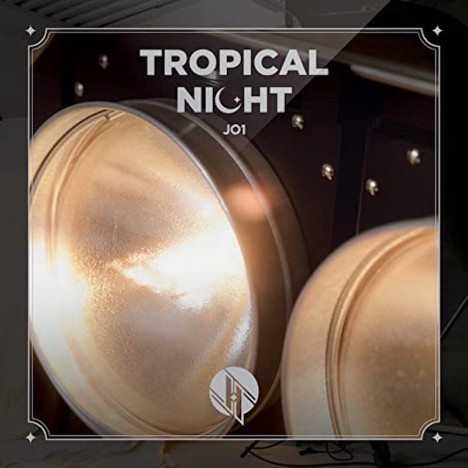Lucky Kilimanjaro、3年間の“闘い”の果てに到達したカタルシス コロナ禍の日々と感情を音楽に昇華した幸福な夜

美しい夜だった。
何かが完全に解決されたわけではないし、そもそも生きていて、何かが本当の意味で解決されるなんていうことは、きっと稀なことなのだが。それでも、自分が生きてきた日々……特にこの3年間のことを胸に浮かべながら、踊った。胸に浮かべながら、というより、その音に身を委ねていると、どうしようもなく浮かび上がってきた。なかったことにはできない苦しさや哀しさもあるが、同じくらいの、なかったことにできない喜びや楽しみの記憶も噛みしめながら、踊った。翌日、ちょっと足が痛くなるくらいに。「俺たち、生きてきたよね!」と、思わず近くにいる人とハイタッチしたくなるような、そんな夜だった。7月2日、東京・豊洲PIT。Lucky Kilimanjaroが今年4月にリリースしたアルバム『Kimochy Season』を携えて、全国8カ所9公演を回ったツアー『Lucky Kilimanjaro presents. TOUR “Kimochy Season”』。そのファイナル公演。

開演時間である18時の10分ほど前、大瀧真央による場内アナウンスが流れた。大瀧はそのはっきりとした美しい声で、この日のライブが声出しOKであることや、マスク着用も個人の自由であることを告げた。振り返れば、Lucky Kilimanjaroがメジャーデビューした年、世界はコロナ禍に突入した。Lucky Kilimanjaroの、時に軽やかで、時に内省的で、時に力強いメッセージ性をはらんだダンスミュージックの現時点での大半は、何かが変わっていく、変わってしまう、変わらなければいけない……そんな時代の渦中に産み落とされた。その、聴く者の心と体の緊張をほぐすようなしなかやなグルーヴも、包み込むような温かなシンセサイザーの音色も、私たちが未知なる次の一瞬に1歩を踏み出せるよう、自分自身の深さに向き合えるよう、勇気と癒しの音として、この3年間、鳴り響き続けた。

時代、人の心……彼らがこの3年間に向き合ってきたものと、それゆえに生み出された音楽の繊細な強さを思う。彼らのポップなイメージにはそぐわないかもしれないが、Lucky Kilimanjaroは「闘ってきた」バンドだ。この3年間、喜びを諦めず、闘ってきた。大瀧の晴れやかなアナウンスは、同時に、私にそのことを改めて思い出させた。