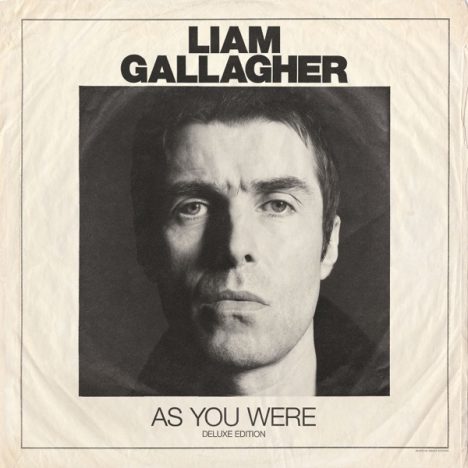リアム・ギャラガー、自在な歌声でソロ活動の集大成へ 音楽性が格段に広がった3rdアルバム『C’mon You Know』徹底解説

リアム・ギャラガーの魅力は、何と言ってもその唯一無二の歌声にある。「いまさら何を言っているんだ」という声が聞こえてくるような気もするが、彼が所属していたロックバンド、Oasisの解散は約13年前の出来事であり、さらに言えば同バンドの全盛期にあたる90年代中盤からはすでに30年近くが経過している。リアム・ギャラガー、あるいはOasisという存在を“過去の出来事”としてスルーしている人々は決して少なくないはずだ。だが、その歌声は今なお唯一無二で、全くもって替えのきかないものであり、今聴いてもリアルな体験として感じられるほどに圧倒的だ。それは、これまでにリリースしてきた過去のソロ作品や、Oasis、Beady Eyeの作品群を聴かずとも、5月27日にリリースされた最新作『C’mon You Know』を聴けば一発で理解することができるだろう。なぜなら、本作は「Oasis的な何か」という期待であり制約から完全に解き放たれ、史上最も自由にその歌声を響かせている作品だからである。

今作でもこの方向性は引き継いでいるが、これまでの作品の成功で完全に確証を得たチームは、過去作よりも遥かに自由に、その創造性を爆発させている。その象徴とも言えるのが、本作のリードシングルである「Everything’s Electric」だ。なにせ、本楽曲にはあのデイヴ・グロールがソングライティング/ドラムで参加しており、まさにハードロック的なリフが冴え渡るイントロや高揚感に満ち溢れたフックの楽曲展開など、これまでのリアムの作風では考えられなかったようなアプローチをふんだんに取り入れたロックソングになっているのである。だが、それは決して単なるFoo Fightersの模倣ではない。サイケデリックな酩酊感の中で言葉を一つひとつ叩きつける構図や、スライドギターやピアノの音色が折り重なるフリーキーなアレンジ、そして何よりデイヴの力強いドラミングに正面から張り合うように歌声を響かせるリアムの存在感が本楽曲をユニークで特別なものへと引き上げているのだ。それは、もはや彼が歌っていない場面でも、その存在感を強く感じられるほどである。
この「リアムの存在感」はアルバム全体の肝となっており、逆に言えばそれを最大限に活かすために楽曲が作り上げられていると言っても良いだろう。少年聖歌隊による荘厳な雰囲気の「More Power」によって幕が上がる本作だが、この空間でリアムが歌い出した瞬間、まるで十字架の前に立った彼がこれまでの人生を振り返りながら祈りを捧げるかのような光景が目の前に広がっていく。神々のような口を利く連中を批判しながら、一方で自らが傷だらけの存在であることを認め、その上で「もっと力があれば」と願う姿は、まさに尊大で脆弱なリアムの姿そのものだ。その願いは神聖さに満ちたオーケストラの音色とサイケデリックロックの音像がぶつかり合いながら、やがてThe Beatlesの「A Day in the Life」を彷彿とさせるほどのビッグバンによってスパークする。自らの中に存在する宇宙がどこまでも広がっていくのだ。
続く、軽快なギターリフとドラムの絡みから始まる、一見するとカジュアルで親しみやすいロックチューンの「Diamond In the Dark」も、絶妙に施されたリバーブ処理、サイケデリック性を増していくアレンジや音像も相まって、これまでにないほど自由で開放的な楽曲だ。そして、歌声によってどこまでも視界が広がっていく瞬間が訪れる。この体験を味わうと、これこそがリアムの歌声を活かす上でのベストな選択肢だったことが分かる。そのサイケデリック性は「Don’t Go Halfway」でさらにドラッギーさに歯止めが効かなくなり、自身がソングライティングを手掛けた「C’mon You Know」で一つの到達点を迎える。これまでの自作曲と言えばBeady Eyeのデビュー曲「Bring The Light」に象徴されるような、ストレートにThe BeatlesやThe Rolling Stonesの影響を感じさせる、一つのフレーズを反復するシンプルな作風という傾向が強かったが、今作ではその反復が徐々に拡大していき、やがてコーラス隊による高揚感、シンセサイザーやメロトロンによるスペーシーな音空間、アバンギャルドなサックスのフレーズ、どこまでもサイケデリアを拡大するバンドの演奏によって一つの宇宙が誕生する。この楽曲がスタジアムで演奏されようものなら、完全にその空間を支配することは確実であり、ある意味ではこの特大スケールの音空間こそが「Oasis的なもの」から解放された今のリアム・ギャラガーにとってのスタジアムでの戦い方なのかもしれないと感じさせる。