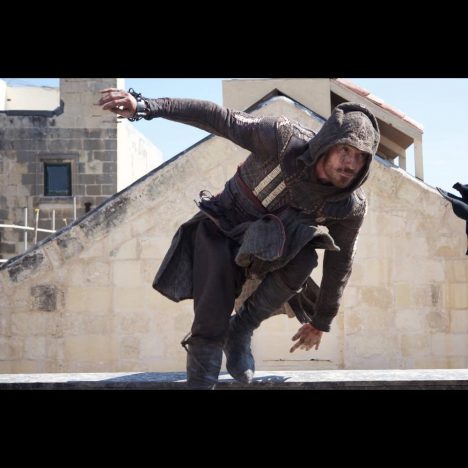エドワード・ヤン幻の傑作、『クーリンチェ少年殺人事件』 は“映画”そのものである

ヌーヴェルヴァーグを思い起こさせる実験性が世界的に評価された、80~90年代に隆盛した「台湾ニューシネマ」。その旗手といわれた天才監督、楊徳昌(エドワード・ヤン)が59歳で亡くなったのが、2007年のことだった。本作『クーリンチェ少年殺人事件』は、ヤン監督の遺された作品群のなかでも代表作だと評価される。しかしながら、日本では権利の関係で、初公開以来25年の間DVD化されず、望まれながらも観ることが困難だった映画である。そのことも本作の価値を高め、日本のコアな映画ファンの間で「幻の作品」となっていた。
本作を愛するマーティン・スコセッシ監督が設立したフィルム・ファウンデーションと、クライテリオン社が、このたび共同で行ったフィルム修復事業により、「4Kレストア・デジタルリマスター版」として本作『クーリンチェ少年殺人事件』 は甦り、日本でもめでたく再上映されることとなった。さらに、公開版より長い、約4時間の長尺版である。映画ファンとしては、ぜひともこの劇場公開の機会に、目に焼き付けておきたい作品だ。

1960年代初頭に台湾で起こった中学生同士の実際の殺傷事件を基に、その頃やはり思春期を迎えていたヤン監督が、当時の実感を込め、子どもたちの社会に起こる出来事を中心に描きながら、台湾の一時代を切り取っていく。本筋として描かれるのは、小四(シャオスー)と小明(シャオミン)の間の淡い恋愛関係である。だが本作は、そういった作品にありがちな、ひたすら郷愁を楽しむような多くのものとは印象が異なり、高度に洗練されていると感じる。それは、被写体とカメラとを絶妙な位置に保ち、登場人物の感情と距離をとった撮り方をしていることと、劇伴(伴奏音楽)が流れない、硬質な演出に起因している。本作は、この「現実の空気を立ち上がらせる」抑制された手法によって、抑圧のなかで生きる子どもたちのやさぐれた日常とたくましさ、そして繊細な感情を、昼間の明るい陽光とノワール調の闇夜を交互に配置しながら描いていく。
ここで映し出されている明暗の表現は、ときに強いコントラストを帯びて登場人物の上に乗りかかり、それは登場人物の表情や、場面や物語の説明よりも明確に優先されている。「映画」というものが、光と闇によってかたちを結んでいるように、また本作のオープニングが、暗闇を照らす電球の光によって始まるように、さらに、本作に登場する映画スタジオの光景がそうであったように、この映画は、明暗によって「映画」そのものに限りなく接近しているように感じる。本作を特別なものにしているのは、映画の美しさを根源的なところから追求しようとする意志なのであろう。それだけで、『クーリンチェ少年殺人事件』を観る価値は十分にある。

だが本作の魅力は、それだけではない。味わっておきたいもうひとつの点は、生活者の視点によって描かれた小世界が、台湾の歴史をダイナミックに浮かび上がらせているという部分である。監督自身もそうだったように、主人公・小四は「外省人」と呼ばれる、蒋介石率いる中国国民党が、毛沢東率いる中国共産党に敗れたあと台湾に移住してきた、中国系の民族である。小四の父親は上海から渡ってきたインテリだが、共産党との関係を疑われ、しつこく尋問を受けるなど、閉鎖的で排他的な空気に疲弊しており、その姿を通して監督の親の世代の苦しみも想像される。そのような不安が本作の子どもたちに伝播し、彼らを暴力的な行動に駆り立てていく。
その暴力の象徴として、日本刀や拳銃が子どもたちの遊び道具となる。台湾は、監督の親の世代が移住する前の時代、日本の植民地となっていた。その名残が、日本刀や日本家屋として台湾に遺されている。台北のクーリンチェは、高い塀に囲まれ、うち捨てられた日本家屋が並ぶ地域である。その後、アメリカが共産圏に対抗するため、台湾を統治した中国国民党を支援するなど、時代によって台湾という国は様々な国の思惑によって利用されてきた。ある時代の子どもたちは日本語を習うことを強制され、またある時代は国民党の政治的教育を受けることで、国本来のアイデンティティーを喪失してきたのである。その意味で外省人は加害的な立場だともいえるだろう。60年代当時の若い世代は、アメリカからの援助物資とともに流入したエルヴィス・プレスリーなどの文化に夢中だったことも示される。