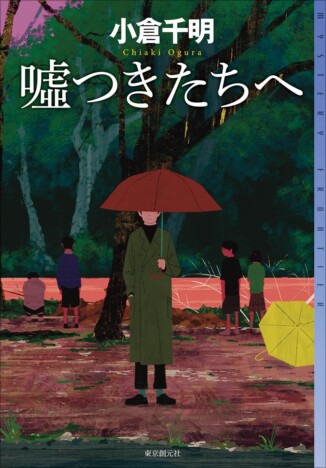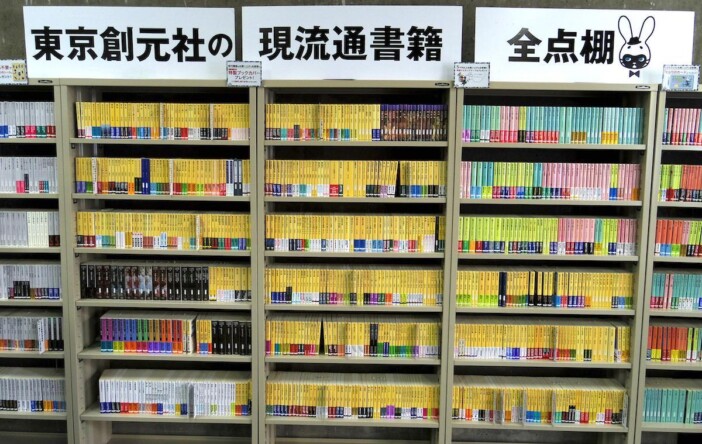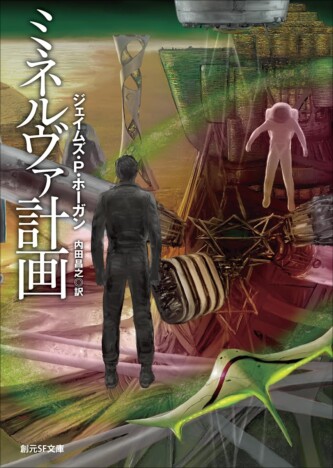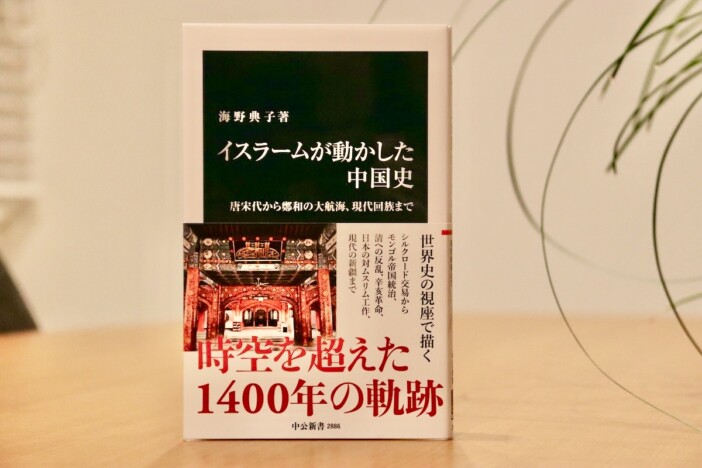『愚行録』から『不等辺五角形』へ 貫井徳郎が語る、「関係者の証言」で紡ぐミステリの新境地

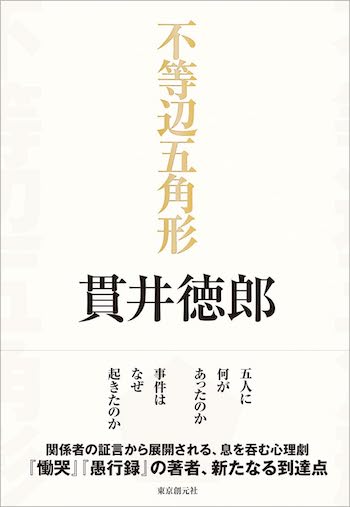
個性を重視した教育が行われるマレーシアのインターナショナルスクールで出会った重成・聡也・梨愛・夏澄・雛乃。五人が久しぶりに顔を揃えた時、一人が死に、一人が殺人を告白した。彼らのあいだに何が起こったのか。貫井徳郎の新刊『不等辺五角形』(東京創元社)は、関係者の証言の連なりから浮かび上がる真実を描いた意欲的なミステリだ。
貫井徳郎の代表作のひとつ『愚行録』(2006年/東京創元社)のような、事件の関係者の証言によって構成されるミステリ小説ながら、そのアプローチは大きく異なっているという。同作の執筆の背景について、ミステリ評論家の千街晶之が迫った。
人間は自分に都合のいいように記憶をすり替えたりする

貫井:リドリー・スコットの『最後の決闘裁判』(2021年)という映画がありますね。あるレイプ事件の被害者と加害者、被害者の夫の視点から事件を描いているんですが、同じシーンなのに、被害者側と加害者側で台詞が違うんですね。最初は違うシーンなのかと混乱したんですが、これは、それぞれの主観ではそういうことになっているんだとびっくりしたんです。僕はこれまでも、一つの事件を複数の視点から描く小説を書いてきたのですが、台詞は同じにしていたんです。でも考えてみたら、人間は自分に都合のいいように記憶をすり替えたりするわけだから、台詞は違っててもいいんだというのを面白く感じました。ただ『最後の決闘裁判』は実話を元にしていますし、加害者は合意があったと主張していても、現代の視点だとどう見てもレイプで、ミステリとしての見どころはない。ならば、これをミステリでやろう……というのが着想の原点で、だから三人の視点なんです。もう一つ言いますと、『完璧な殺人』(1993年/早川書房)というリレー小説があって、完全殺人の方法を複数の小説家に考えてもらうのですが、次の小説家が前の小説家の考えを否定するんですね。面白いのはリレーで書いてる人たちが、二周目で前の意見に反論するんです。それで今回の小説でも二周させました。
――最初、タイトルから『プリズム』(1999年/実業之日本社)のような五通りの多重解決が出てくる話なのかと予想したのですが、読んでみると『愚行録』に近い構成でした。貫井さんが、証言の連なりで構成されたミステリを好んで書くのは何故でしょうか。
貫井:今回はそういう発想だったものですから、たまたま『愚行録』に似たのですが、版元が東京創元社ですし、『愚行録』の評判が良かったからさらに寄せるかと(笑)。でも実際のところは全然違っていて、『愚行録』はイヤミスのはしりみたいな作品でしたが、今回はイヤミスではない。僕の子供に「今回は白『愚行録』だよ」と言ったら、意味がわからないと(笑)。ただ、証言の連なりで書くのが得意という意識はないんです。『愚行録』は沢山の証言の中で一つだけ事件に関係していたわけですが、今回は証言の全部が真相に関わっているという逆のスタイルなので、『愚行録』より書くのが大変でした。
――登場する五人の関係は、書いている途中で変化したりとかはありましたか。それとも最初の予定通りでしょうか。
貫井:両方といえば両方でしょうか。書いていて、「ああ、こういう人だったのか」と思ったこともなくはないですが、当初の予定からは外れていなかったり。でも、どっちだと言われたら予定通りですね。僕は書いているうちに脱線していくタイプなので、その意味では珍しいです。ただ、全部事件に関係あるエピソードにしようと思うとネタが尽きるんで、中盤以降は間接的に関係があるエピソードが増えました。
――序盤で印象的だったのが、事件発生を知った重成が聡也に知らせるシーンで、二人の証言が全く食い違ってますね。記憶というものが捏造されるということがそこでわかる構成になっています。
貫井:今回、誰の言うことが真相かわからないよ、というのをそこで示したつもりだったんです。書いている途中で思ったんですが、夏澄のパートで「会話の内容まで事細かに憶えてたら、その方がおかしいと思いません?」と言っていて、本当にそうだよなあと。
――「ミステリの登場人物、記憶力が良すぎ」問題ですね。普通はそうでないと話が成立しないわけですが。『愚行録』ほど登場人物全員が嫌なやつではなく、ひとりひとりは善人というのもコントラストだったと思います。
貫井:基本的に仲良しのグループなので、一週目はまだ気が立っててギスギスしていますが、二周目になると気持ちが落ち着いて友達の悪口を言わなくなったりとか、そういう変化もつけました。
意識の変化に追いつけない人が問題を起こすことが増えている

貫井:そうですね、特にここ数年は、昔はOKだったのに駄目になったことが多々あって、その意識の変化に追いつけない人が問題を起こすことが沢山ありますね。僕自身は大丈夫だと思ってるわけじゃなくて、僕も怖くて、特に今は日本推理作家協会の代表理事なので絶対失言はしちゃいけないと気を張ってるところがあります。そういう気持ちが作品に反映されている気がしますね。
――梨愛の父親のような、自分ではアップデートしたつもりでも全然駄目みたいな人物の描き方の解像度の高さを感じました。
貫井:自分がそうなってないことを祈りながら書いている感じです。
――五人とも個性を重視することを求められるインターナショナルスクール育ちなのに、保守的な両親に反撥していたはずの梨愛が、日本人的な仲間の和を過剰に意識した人間になってしまったり、何事も理想通りにはいかないという皮肉さも感じました。
貫井:さっきの質問につながりますが、梨愛はわりと書きながら考えたキャラクターなんです。お父さんやソフィーのエピソードは当初はなくて、書きながら思いついたんです。なので、梨愛の意識の持ち方が皮肉に見えたとすれば、辻褄を合わせたせいでそうなっているんだと思います。
――貫井作品といえば『微笑む人』(2012年/実業之日本社)、『壁の男』(2016年/文藝春秋)、『悪の芽』(2021年/KADOKAWA)のように動機がわからない作品の系列があって、今回もそれかと思わせておいて……というあたり、ご自身の作風をミスディレクションにしたようにも感じました。
貫井:作風をミスディレクションにしたというか、行き詰まりを感じていて、変えなきゃと思っていて、従来やってないことをやったというところはあります。
――書きやすかった登場人物は。
貫井:誰が書きやすかったというのはなかったですが、最後の梨愛は書いてて面白かったですね。こういう証言形式って、普通に書いたほうが楽なんです。特に、独白ではなく誰かに質問されている形式だと、相手に何を訊かれているかを明示しなきゃいけないわけで。『愚行録』の時は相手に聞き返すかたちでそれを描いてたんですが、今回は一段階テクニックが上の書き方をした分、難しかったですね。ともかく、語り形式もそうだし、ミステリとしてもそうだし、読者にはあまり伝わらない難しいことをやって苦労しています(笑)。
――登場人物で最初に人物像が固まったのは誰でしょうか。
貫井:聡也が感覚がアップデートされていない発言をしてしまうシーンは最初はなかったので、聡也ではない。さっきも言ったように梨愛でもない。だから重成か夏澄ですね。重成は最初の語り手なので、おっとりした人物に描く必要がありましたし。
――被害者である雛乃の真意だけは描かれる機会がないままですが、彼女が重成を試すような真似をした理由は、最後の梨愛の推測が正しいのでしょうか。
貫井:あれも、梨愛がそう思ってるだけで、本当は違うかもしれない。僕自身も違うことを考えていて、書いてるうちに梨愛が勝手にそういうことを言い出したので、矛盾がないか検証したくらいでしたね。