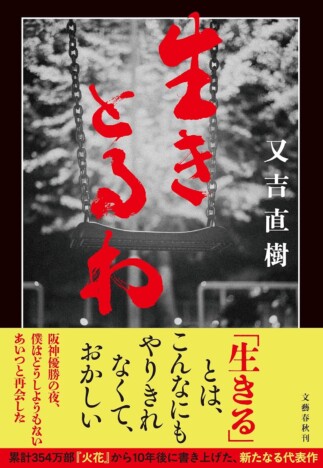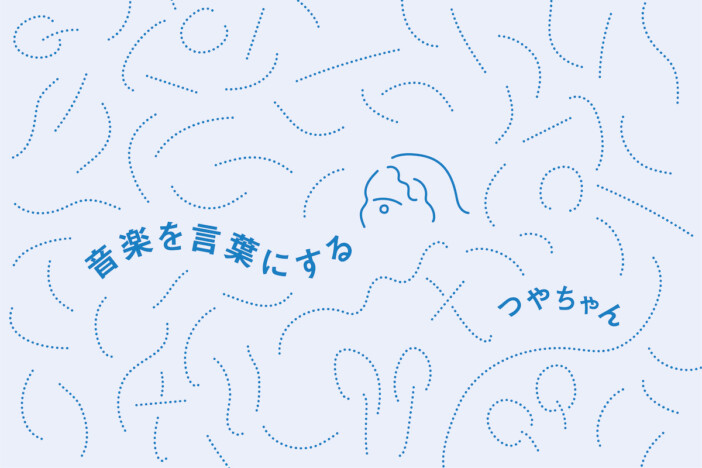【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第13回:心的なワークスペースとしての小説

3、内面に先行する世界

心(ないし心のシミュレーション)が、いかなるメカニズムによって組織されるのか――それは21世紀を特徴づけるアクチュアルな問いである。例えば、AIとゲームの研究者である三宅陽一郎は「どのように生物の持つ主観的な世界を形成すればよいか」という問いを、自らの探究の核としている(※6)。つまり、ニューロンを基盤とする生物の主観性を、いかに機械的なプログラムによって代替できるかが問われているのだ。
私が『世界文学のアーキテクチャ』で取り組んだのは、いわばこの三宅の問いの文学版である。小説は文字の集合にすぎない。それなのに、小説がまるで固有の主観的な世界を形作り、心を表現しているように思えるのは、実に奇妙なことである。文字の生み出す心は、脳神経の生み出す心と同じではない。しかし、われわれは小説の生産する心のシミュラークルを、心そのもののように錯覚してしまう。つまり、人間ならざる言語的なワークスペースの活動に、人間の心を読み取ってしまう。私はこの錯覚の仕組みを、文学が進化的に獲得した能力として論じたのである。
かつて柄谷行人は『日本近代文学の起源』で、言文一致文という新たな文の創出によって「内面の発見」がもたらされたと論じた(※7)。言語と心の距離を無化し、主人公の声そのものと一致しているかのような文体が、内面を発見させる――この柄谷の洞察は傾聴に値するが、恐らくそれだけでは小説の心を解明しきれない。

繰り返せば、小説の心の成立には、一人称の語りによってモジュール間を交流させ、ニューロナル・ワークスペースらしきものを形作るというピカレスクロマンの発明が決定的に重要であった。それに続いて、モジュールの結合範囲を飛躍的に拡大するきっかけとなったのが、17~18世紀のヨーロッパを起点とするグローバリゼーションである。18世紀イギリスのデフォーやスウィフトは、グローバルな世界を主人公の冒険の舞台に仕立て、このワークスペースを根拠としながら、心的な運動を描き出した。『世界文学のアーキテクチャ』で論じたように、「内面の発見」よりも「世界の発見」のほうが先行していたのである。
ただし、小説が「発明」したのは、たんなる活動的・冒険的なグローバリストではなかった。それどころか、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』(1719年)は、マクルーハン用語で言えば「関与」から「分離」への移行を鮮明にした小説と言うべきである。ロンドン生まれの放蕩息子クルーソーは、海洋貿易のブームに関与するものの、植民地での事業には挫折し、その後漂着した無人島に長期的にひきこもることになる。つまり、クルーソーの「島」は、グローバリズムの勝利の証ではなく、むしろその浮ついたゲームから撤退した人間の避難所なのだ。ポストコロニアル批評の文脈では、デフォーはしばしば西洋の植民地主義の尖兵のように評されてきた。それは誤りではないが、彼が同時に、グローバリズムの限界を摘出した著述家であったことも忘れてはならない。
クルーソーの心は、当初、他者の心を鏡としていた――彼の行動は、アメリカの「新世界」に熱中した他のヨーロッパ人を反射していたのだから。しかし、このグローバリズムへの同化がやがて幻滅に変わったとき、クルーソーはむしろ人間の相互模倣のゲームから自らを分離させ、大量の事物に満ちた無人島の環境に住まう。デフォーはいわばビッグデータの作家であり、『ロビンソン・クルーソー』にせよ『疫病の年の日誌』(邦題『ペスト』)にせよ、そこには事物をして語らしめるような経験主義的な態度が貫かれていた。
繰り返せば、ヒュームの心は、他者を「鏡」とする心であった。逆に、デフォーの心は人間たちの鏡像的な反射から逃れて、むしろ事物の繁殖するワークスペースとしての「島」と一体化する。この二つのタイプの心は、それ以降もさまざまな形態で反復されることになるだろう。マクルーハン的な「関与」および「分離」のモデルはそれぞれ、18世紀前半の哲学者と文学者によって早くも象られていたのだ。
※6 三宅陽一郎『人工知能のための哲学塾』(ビー・エヌ・エヌ新社、2016年)30頁。なお「心的なワークスペースとしての小説」という構想は、宇野常寛を交えた三宅との以下の対話において具体化された。https://www.youtube.com/watch?v=6JJMEqbbbNg
※7 柄谷行人『定本 日本近代文学の起源』(岩波現代文庫、2008年)第2章参照。
4、≪遅いメディア≫としての小説

私は小説を≪心的なワークスペース≫として理解したい。そこは多様なモジュールを圧縮し、交流させる舞台である。ボッカッチョの「庭」からデフォーの「島」に到ったとき、小説は事物とのコミュニケーションを実現するワークスペースを獲得し、他者への「関与」の要求を緩和させた。事物に満ちた島は、いわば他者の反射率をその環境の作用によって低下させたのである。
私は前回、21世紀のソーシャルメディアが、情報化した物語に覆われていると述べた。それはまさに、物語が情報のフィードバックを加速させる鏡に近づいていることと等しい。それに対して、小説は反射率の悪いメディアである。つまり、円滑なフィードバックを阻むようなディテールが、小説においては肥大化している。先述したように、小説は物語であり情報でもあるが、そのいずれにも還元できない。それはまさに、小説という心的なワークスペースが≪遅いメディア≫だからである。
意外なことに、それを把握していたのは、『ロビンソン・クルーソー』刊行の五年後に生まれた哲学者カントであった。カントの講義録には、小説に関するきわめて興味深いコメントが認められる。
小説を読み耽ると心に様々な変調をきたすだけでなく、また放心が常態化するという結果を生む。というのは、本当の話を伝える場合には必ず何らかの意味で筋が通っているのでなければならないが、小説を読む場合は、(多少の誇張が入るにしても)現にいそうな様々な人物模様が描写されているので、たしかにまるで本当の話の場合のように一つの筋が想像されていく一方、しかし同時に、読んでいるあいだに心はついでに脱線を楽しむ余裕も与えられている(つまりストーリーとは関係のないことを思い巡らす)せいで頭のなかの想像の流れが断片的となり、その結果同じ一つの対象についての表象が散漫になって、悟性の統一に則って繋ぎ合わされるのでなくて心のなかで戯れることになるからである。(※8)
カントにとって、小説はぼんやりとした「放心」の状態を促すメディアである。それは読者の注意力を散漫にし、思考を脱線や戯れへと導く。心ここにあらずの状態に陥った読み手の理解は、統一性を失って、いわば穴だらけになるだろう。小説という≪遅いメディア≫を読むことは、規則正しい等速の理解を挫折させ、心そのものを「不在」の状態(absent-mindedness)に近づけるのである。
小説という心的なワークスペースでは、確かに複数のモジュールが連結される。しかし、その結びつきは必ずしも緊密なものではない。特に、気の散った読者において、この結合はほどけ、たんなる散漫な文字列に戻ってしまうだろう。だからこそ、小説のテクストをあえてもはやモジュールとしても機能しないレベルにまで断片化し、過剰に戯れさせることもできる。1950年代にカルト作家ウィリアム・バロウズの駆使したカット・アップの技法は、まさにその実践であった。
カントは認識能力につきまとう「心の弱さ」を問題にした。小説を読むことは、まさに気の散りやすい人間の弱点を暴露する。しかし、この「心の弱さ」を拡大した小説は、たえず情報に注意しながら、フィードバック・ループに即時的に関与せざるを得ないネットワーク社会の人間にとって、むしろ取り戻すべき価値を備えたメディアではないだろうか。≪遅いメディア≫としての小説は、まさにその反射の「のろさ」によって、鏡の国からの逃走路を示しているのだ。
※8 「実用的見地における人間学」(渋谷治美訳)『カント全集15』(岩波書店、2003年)142頁。