『翻訳者の全技術』はあらゆる仕事に応用できる? 山形浩生の新書に学ぶ、「永遠の二流」の“仕事術”
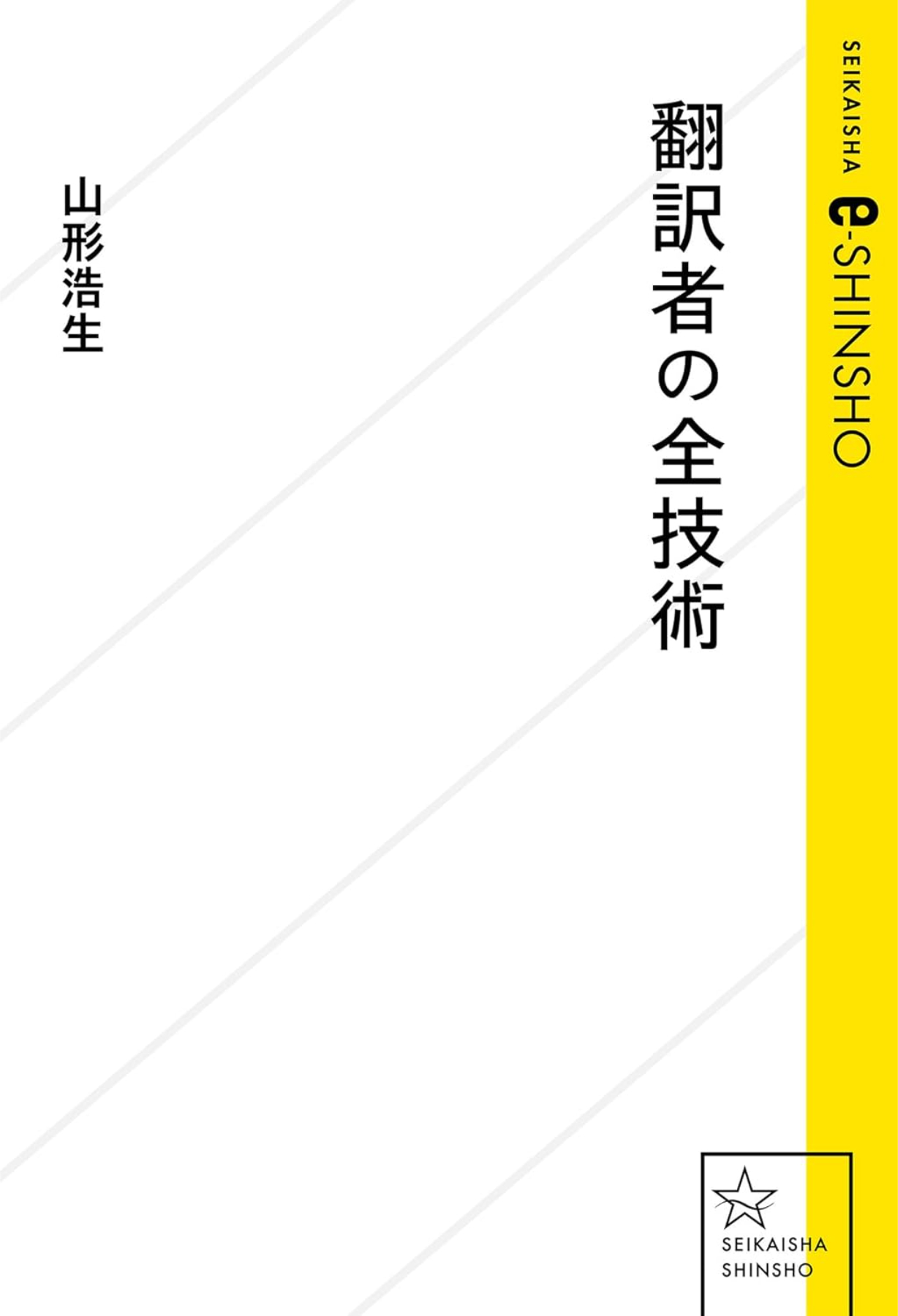
わからない文章はわからないまま訳すのが正解
かつてアメリカに、ウィリアム・S・バロウズという作家がいた。破天荒な生き方と、カットアップやフォールドインという実験的な技法で知られる、ビート・ジェネレーションを代表する作家の一人だ。
カットアップとは、自分や他人が書いた文章をランダムに切り刻み、フォールドインとは、テキストが印字された2枚の紙を断裁して(あるいは折り曲げて)並び替える、いわば文章や言葉のコラージュのことだが、カットアップ技法をバロウズに教えたブライオン・ガイシン(画家・詩人)は、「文学は絵画より少なくとも50年は遅れている」といっていたという。
その結果、文学がアートより“先”に行けたかどうかはともかく(あるいは、その技法自体の面白さはともかく)、カットアップやフォールドインで作られた文章を、読み手が完全に理解できるかといえば、そんなことはないだろう。強いていえば、原文(英語)でなら、なんとなく作者(バロウズ)が意図したイメージをつかむことができるかもしれない。
しかし、それ(カットアップなどで作られた文章)を他の言語に置き換えたとき、もともと意味をなしていない(はずの)文章は、さらにわけがわからなくなるのではないか。ましてや、そのわけがわからない文章を、無理矢理意味が通じるようにするのは、もってのほかではないか。
もしかしたらその“ズレ”をさえ、バロウズは面白がるかもしれないが、私としては、なるべくなら原文に忠実な、つまり、わけがわからない言葉のコラージュのまま、翻訳してもらいたいと思っている。このことについて、『翻訳者の全技術』の中で、山形浩生はこう書いている。
そのバロウズが創作に使ったカットアップやフォールドインという手法は、雑誌や新聞をハサミでちょん切り、あるいは適当に折って、それを適当に並べ、良さげな文章にするというものだ。つまり、まともな文章ではないのだから、それを普通の文章と同じように訳してはいいわけがない。これぞまさに、辞書を引いて単語をそのまま並べるべき翻訳だったりする。普通の意味での文脈がないことこそ、そこでの文脈で、したがってまともな文章にせず、本当に単語の羅列にしなくてはならないわけだ。
ところが、既存の翻訳の多くはそれを必死で普通の文章にしようとしていた。(中略)たとえば「赤いにんじん、机、それが川の上流ぼくは何を緑のちょうちん」というようなバロウズの文章を訳そうとして、必死でなんとか言葉を補って「赤い川辺にある机の上に置いてあったにんじんは、上流から流れてきた時に僕が見つけて、何を思ったか緑色のちょうちんと並んでいる」とでっちあげるわけだ。それはまずいでしょう。
〜山形浩生『翻訳者の全技術』(星海社新書)より〜
たしかにまずい。ただ、勘違いしてほしくないのは、別に山形はここで「直訳」を勧めているわけではなく、作者の意図をきちんと理解した上で、本来あるべき形で、つまり、わからないところはちゃんとわからない形で、日本語に置き換えようといっているということだ。
バロウズの場合でいえば、たぶん彼のカットアップやフォールドインの根底にあるのは、“システムの破壊”だ(単なる“手抜き”かもしれないが……)。それを日本語で表わすなら、どんなスタイルで訳すのが最も望ましいのかを最初に考えてみるべきだろう。





















