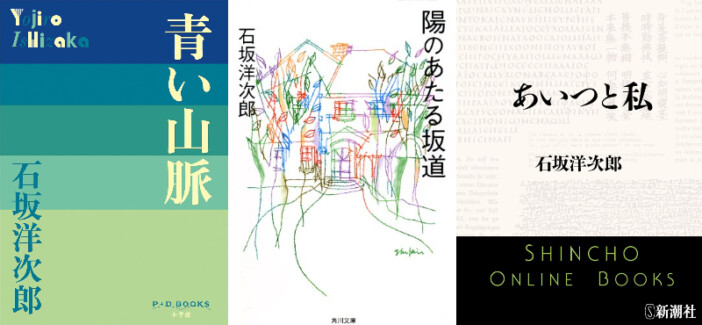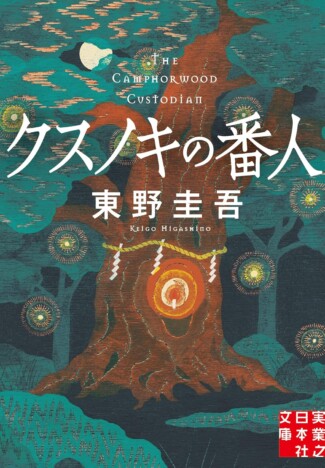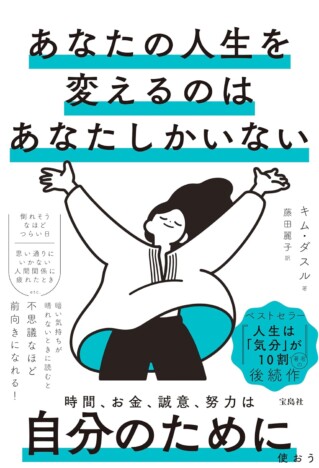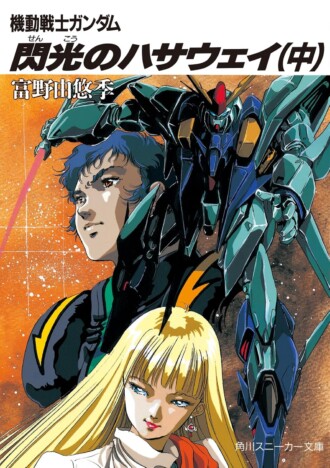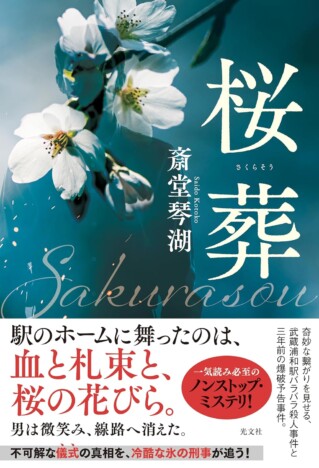「立ち読み」はいつ始まり、庶民の読書文化を形作ってきたのか? 謎多き近代出版史に迫る一冊

コンビニで雑誌 立ち読みしてた 昨日の僕に Bye-Bye
(嵐「サクラ咲ケ」より)
某予備校のCMにも使用された曲の歌詞ではないが、筆者もだいぶ前、コンビニで雑誌を立ち読みしていたかつての自分にはBye-Byeした。もっとも、それは筆者が何かしらの人間的な成長を遂げたという意味ではない。近年、コンビニにおける雑誌や書籍の取り扱いは減少傾向にあり、そもそもコンビニに行けども、雑誌がないというケースが少なくない。また、雑誌の取り扱いがあったとしても、多くの場合は開封禁止シールが貼られており、ページをめくっての中身のチェックはほぼ不可能になっている。つまり、物理的に立ち読みができなくなったので、コンビニ立ち読み愛好者としての自分にはBye-Byeせざるを得なくなったということである。
筆者の他愛ない習慣の終わりからまずは書き出してみたが、しかし、「他愛ない」という言葉だけであっさりと片づけるのも、少し惜しいようにも思う。というのは、この個人的なエピソードには、あんがい、「立ち読み」という習俗を考える上で重要なヒントが含まれているように感じられるからだ。
ひとつには、立ち読みは書店やそれに類する店に立ち寄った客の、自主性や能動性に左右される行為のように思われつつ、その実、立ち読みを物理的に許す環境があることが、まずは基盤として不可欠ということである。
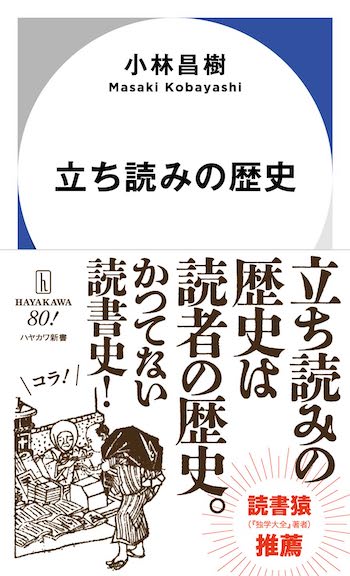
図書館情報学を研究し、国立国会図書館で長年レファレンス業務に従事してきた著者・小林昌樹による本書『立ち読みの歴史』(ハヤカワ新書)においても、読みながら実感できることのひとつは、立ち読みのための環境の重要性だ。本書の序盤では、まず立ち読みの起源についての考察が深められる。現在の意味での「立ち読み」がいつ日本で始まったのか、ピンポイントで指摘することは難しいものの、おおよそ明治20年代に発生したと考えられるという。とはいえ、その当時まで本屋がないというわけではなかった。本書の解説によると、江戸時代にはすでに、ある程度の上流層に利用者は限られていたとはいえ、学問の書籍など高額な本を中心に扱う本屋は存在していた。加えて、そのような本に手が届かない、また関心も薄いであろう庶民のために、より大衆的で安い「地本」を売る「絵草紙屋」や、本を売るかわりに比較的安い値段で貸しだす「貸本屋」も存在していた。
では、ビジネスとしての本の売り買い、および貸し借りがある程度は浸透していたにもかかわらず、なぜ「立ち読み」は明治期に至るまで生まれなかったのか。もちろん、当時の日本人に発想力が欠落していたからでも、または「買わないかもしれないのに本を汚してはならない」といった強い道徳心がそれを抑制していたからでもない。本書は明治の初期まで、本屋が「座売り」であったということに着目する。
小林の説明によると、「座売り」とは図書館でいう「閉架」式の本の出し方である。すなわち、基本的に本は客の見えないところにしまわれており、客が欲しい本を言うと、その都度店員が出してくるというスタイルが採用されていた。つまり、本の在庫が客にオープンになっていないので、物理的に「立ち読み」が発生する余地がなかったのだ。しかし、書店が「座売り」から現在のような「陳列販売」になったことが、大きな分岐点となる。その開始は先行研究により、明治36年(1903年)前後であったことがわかるという。
因果関係としては、明治期に本屋の形態が変わり、物理的に立ち読みができるようになったから、「立ち読み」は生まれた――。筆者のような素人の目線では、これで立ち読みの起点は整理できたように感じられる。しかし、ことはそう簡単ではない。そして、簡単に解き明かすことのできない立ち読みの起源や範囲に粘り強く向き合っていくことに、本書の特色と魅力は詰まっている。
かりに本屋の形態の変化と、立ち読みの起源がリンクするのであれば、立ち読みの起源は明治36年(1903年)前後となるだろう。しかし前述したように、小林はそれに先立つ明治20年代に立ち読みのはじまりを見出している。その根拠として小林があげるのは、ジャーナリスト・宮武外骨の大正7年(1918年)の証言である。宮武は神保町の書店で万引きが少なからず見られ、その原因の一端が立ち読みにあるという主張を述べたうえで、明治20年代にはすでに立ち読みが発生していたことに(直接的にではないが)言及しているというのだ。
では、それはどこで行われたのか。宮武の証言では、「雑誌屋」で行われてきたという。戦前に存在した、雑誌を中心に売る小売店だが、いわゆる本屋ではないこともあり、戦後はほとんど忘れられた存在となっていた。また、研究文献も近年までは存在せず、その詳細を知ることは簡単ではなかった。しかし、小林は粘り強く資料にあたり、店舗の数やその起源、当時の雑誌文化の検証に加え、その店舗構造を雑誌記事や挿絵などから精査する。その結果、当時の「雑誌屋」で物理的に立ち読みが可能であったことを突き止め、宮武の証言に一定の信憑性を認めるのだ。
とはいえ、それでも小林は、軽々しく立ち読みの起源を断定しない。そもそも、立ち読みの定義とは何で、何をしていれば立ち読みと言えるのか――。小林はやがて、立ち読みの定義の明確化や、江戸時代における「立ち見」から近代における「立ち読み」への深化までの過程に、卓越したリサーチ能力を駆使して向き合っていく。が、これ以上内容を詳細に述べれば、本書を手に取ること、本書を「立ち読み」することの面白みも縮減してしまうので、内容についての記述はこのあたりにしておこう(念のため述べれば、小林は本書が「立ち読み」される可能性に積極的な面白さを見出している)。ここではあくまで、小林の立ち読みに対する粘り強い探究の一端を提示するにとどめておく。
しかし、もう少し述べておきたいこともある。それは本書の帯文にもある、「立ち読みの歴史は読者の歴史」という言葉の内実である。